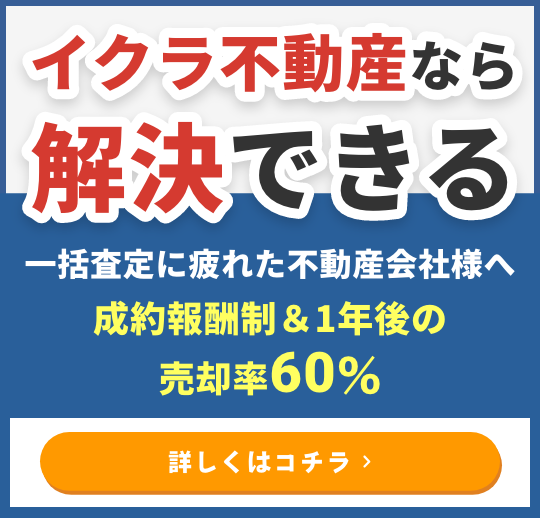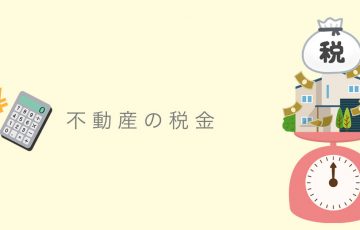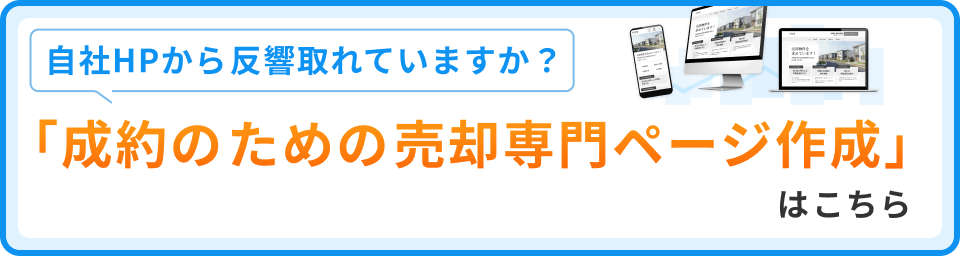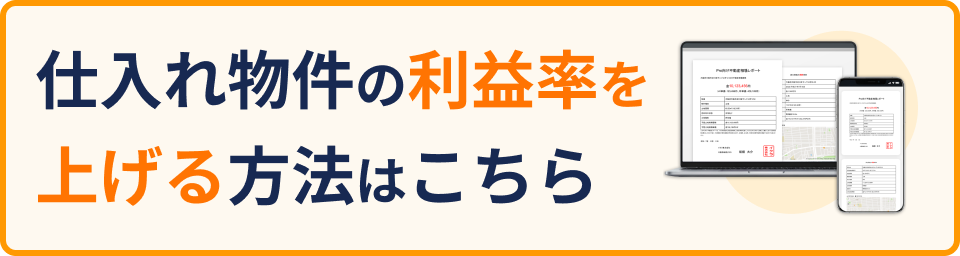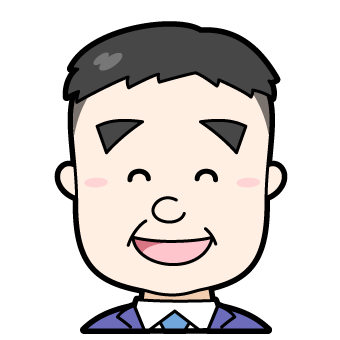
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「公租公課等の分担」という項目があります。
|
(公租公課等の分担) 第12条 売主、買主は、本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等のの公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担について、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は1月1日とします。 |
「公租公課等の分担」の意味と内容
「公租公課」とは、国や地方公共団体に納める負担(税金や保険など)のことをいいます。
一般的には「公租(こうそ)」が「税金」で所得税や住民税などを指し、「公課(こうか)」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。不動産で「公租公課」というと、固定資産税、都市計画税、不動産取得税のことをいいます。不動産取得税は、取得した人、つまり買主にかかる税金なので分担しません。つまり、こちらの条項の「公租公課の分担」とは、固定資産税・都市計画税を売主と買主とで、どのように分担するかを定めた条項になります。
具体的には、現に使用収益(自ら使用したり、それによって利益を得ること)する人や使用収益できる状態にある人が、税金などの負担をするのが公平であると言う考え方に基づき、使用収益の分かれ目である引渡完了日(実際に引き渡しを行った日)を基準にし、引渡完了日前日までの分を売主に、引渡完了日以降を買主にそれぞれ負担させることを定めています。賃貸中の物件の賃料収入などの収益の配分についても、同じく引渡完了日が基準になります。また、ガス、水道、電気料金などの負担金についても、同じく引渡完了日が基準になります。
清算対象の公租公課とは?
上述したように、ここでの公租公課の税金は固定資産税と都市計画税のことです。不動産売買契約の決済時に、こちらの条項の定めに従って固定資産税と都市計画税の清算が必要になります。
「精算」と「清算」の違い
「精算」は、金額を細かく計算し、結果を出すときに使われます(例:スーパーで買った物を精算する)。一方、「清算」は、今までの貸し借りをすべて整理して後始末をつけるときに使われます。また、過去の関係に始末をつけるという意味もあります(例:友人から借りていたお金を清算した。)。
「精算」と「清算」を使い分けるのは、非常に難しいです。人間関係を解消するときや過去の事柄に決着をつけるなど、お金以外でも何かをきれいに整理するという意味があれば「清算」を利用します。
固定資産税は地方税のため、市町村(東京23区では東京都)が課税しています。納税する義務がある人(納税義務者)は、所有権者であるかどうかを問わず、その年の1月1日の現在の所有者(登記名義人)です。納税通知書の名義人は、当然売主ですので、買主が税金の日割りの清算金を売主に支払うことによりこの清算を終了させます。
起算日と清算方法について
こちらの条項では、公租公課の起算日(期間を計算し始める第一日)は1月1日としており、売主と買主は各々の負担分を1月1日から12月31日の365日で日割計算します。
なお、中部圏以西の地域では4月1日を起算日とするのが慣習です。年税額は毎年4〜5月に納税通知書が登記名義人(所有者)宛に郵送されてきますので、到着後であればこれにより計算することになります。しかし、同一の税務事務所管内に複数の不動産を所有していると、納税通知書は1通となりますので、不動産ごとの内訳を確認しておかなくてはなりません。納税通知書が送達される前に引渡しがあるとき清算方法はどうするか、売主買主協議のうえ定めておく必要があります。清算方法には次の3パターンがあります。
- 納税通知書が届くまで清算を延期する(届いてから精算する)
- 前年度の税額をもとに仮清算して、納税通知書が届いた時に金額が異なっていれば再清算する
- 前年度の税額をもとに清算する(再清算しない)
こちらの条項では、公租公課の起算日は1月1日としてあります。前記のとおり、慣習により4月1日を起算日としているところもあります。1月1日、4月1日の違いにより清算金額が大きく相違しますので、起算日には注意が必要です。
・固都税(固定資産税・都市計画税)の清算(精算)方法についてまとめた
なお、固定資産評価替の年度においては、固都税の税額を3月に閲覧できます。前年度の税額をもとに清算する場合で、売買する土地または建物が税額軽減の特例措置を受けているときは、その特例適用の年限に注意が必要です。前年度が軽減の最終年のとき、本年度から税額は大幅に増加するからです。税額軽減の特例措置については、市町村役場、都道府県税事務所等で確認が必要です。
・固都税(固定資産税・都市計画税)の計算方法についてまとめた
消費税課税事業者が売主である場合の公租公課の清算について
売主が不動産業者など消費税課税事業者である場合、この清算金のうち建物に係るものは建物の譲渡対価の一部を構成するものとして、課税売上に該当するとして取り扱われることに注意が必要です。
消費税法基本通達10-1-6 (未経過固定資産税等の取扱い)
譲渡された資産に課された固定資産税等について、譲渡の時未経過分がある場合、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡金額とは別に収受している場合でも、その未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡金額に含まれるとされる。
(注)固定資産の名義変更をしなかったために譲渡した事業者に課された場合、その事業者が譲渡を受けたものから固定資産税相当額を収受するときは、その金額は譲渡等の対価に該当しない。
つまり、清算金のうち建物に係るものについては、別途消費税等が課せられます。
以下の条件を前提として実際に計算してみましょう。
| (例)固定資産税等の税額が40万円(土地10万円、建物30万円)で、未経過分(買主負担分)が6ヶ月の場合
土地:10万円 × 6/12 = 5万円(A) この場合、(A)+(B)+(C)= 21万5000円が清算金となります。 |
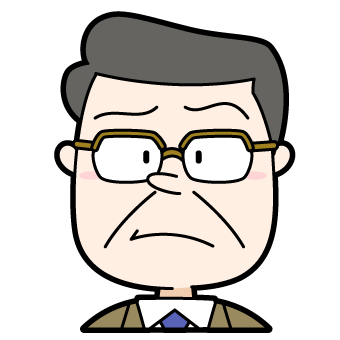
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。