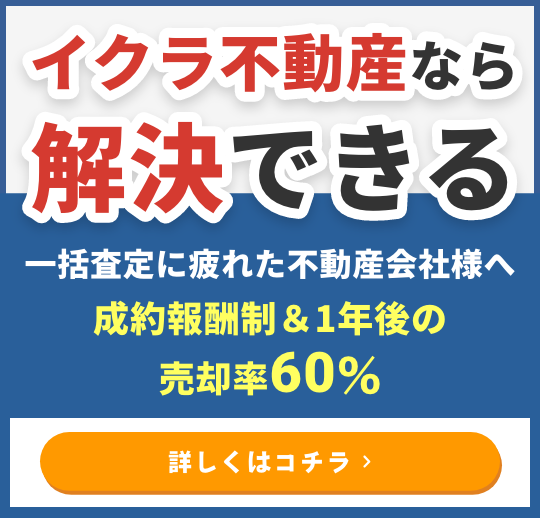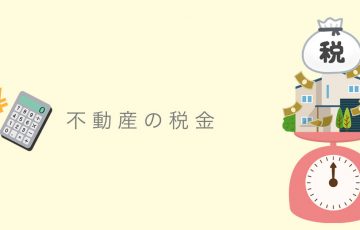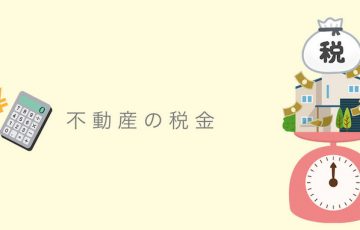不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対してかかる税金(所得税・住民税)、いわゆる譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)を納めなければなりません。
譲渡所得税を簡単にいうと次のような税金です。
- 不動産を売却した利益を譲渡所得といいます。
- 利益が出ている場合には譲渡所得税・住民税を納めなければなりませんが、損失の場合は必要ありません。
- 不動産の譲渡所得は、他の所得税と一緒に計算して相殺することは不可能です。
- 課税方法は所有期間によって異なり、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か5年を超えるかにより大きく2つに分けて判断します。
- 使用の用途を居住用、事業用(非居住用)に分けて、条件が該当する場合には特例や特別控除、繰越控除を受けることができます。
売却して利益が出たかどうかは、売却価格から購入価格を差し引いて計算します。この購入したときの価格を取得費(しゅとくひ)といいますが、取得費を計算しなければ譲渡所得税が計算できません。
こちらでは、譲渡所得の計算に必要な取得費・譲渡費用についてわかりやすく説明します。
譲渡所得に関する計算方法
譲渡所得の計算方法は次の通りです。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得税の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

取得費とは
取得費とは、土地や建物などの取得(購入)にかかった費用のことで、家を買った時の購入費用です。この取得には購入のほか、贈与、相続または遺贈による取得も含みます。
家(土地や建物)本体の購入代金・建築費用に加えて、次のものが取得費に含まれます。
- 購入時に支払った仲介手数料
- 登録免許税(登記費用)
- 不動産取得税
- 印紙税
- 土地の測量費
- 建物の解体費
詳しくは、国税庁HP「取得費となるもの」をご覧ください。
建物の取得費用は、所有期間中の減価償却費(げんかしょうきゃくひ)を差し引いて計算しなければなりません。
取得費に関しては次の①②の金額の内、大きい金額を使います。購入時の売買契約書を紛失しているなど、取得費用がわからない場合は①の概算法(概算取得費)を使います。
①概算法(概算取得費):譲渡収入金額(売却金額)×5%
②実額法:土地・建物の購入代金と取得に要した費用(取得費)から、建物の減価償却費を差し引いた金額
減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少していく固定資産(ここでは不動産の建物部分)を取得(購入)した際に、その耐用年数に応じて取得費用を計上していく会計上の処理のことです。
例えば、家を新築で購入したとして、20年後も「新築と同じ価値です」というのは無理がありますよね。その20年の間には家は劣化が進み、キッチンや風呂などの設備も老朽化しています。
つまり、減価償却とは、時間が経過すると価値が下がる資産の価値を、正しく評価するために行なう作業ともいえます。不動産の土地部分のように、時間の経過や使用により価値が減少しないものについては、減価償却資産には含まれないので、ここで差し引くのは建物部分だけになります。
減価償却費の計算方法
建物の価値は新築のときが一番高く、時間の経過・使用とともにその価値が下落していきます。建物には耐用年数(たいようねんすう)という寿命があります。実際には手入れなどの状況により、建物の寿命は異なりますが、税法はそれとは関係なく、会計上の処理を行うために、建物の構造や材質によってあらかじめ法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)を定めています。
減価(価値の下落)の額は、建物の取得(購入)からその寿命までの間に、均等額ずつ価値が下落するものとして計算した建物の価値の減少を金額にしたものです。減価の額の計算には、建物の購入代金等、残存価額、償却率(耐用年数)の3つの要素を使います。
残存価額とは、寿命がきても最低限残る建物の価値のことです。譲渡所得の減価の額の計算においては、残存価額は取得価額の10%とされているため「建物購入代金等×90%」で算出します。
減価償却費の一般的な計算方法としては定額法と定率法があり、特に届出をしない場合は定額法で計算します。
マイホームは事業用ではないので、非事業用資産の償却率(耐用年数)により減価償却費を算出します。また、1998(平成10)年4月1日以降に取得した建物は、全て定額法により減価償却費を計算します。
減価償却費(定額法)の計算方法
減価償却費(定額法) = 建物購入代金など × 90%(0.9) × 償却率 × 経過年数
定額法の法定耐用年数と償却率については次の通りです。非事業用の耐用年数は事業用の1.5倍で計算します。また、非事業用の経過年数を計算する場合、6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨て(5捨6入)て計算します。
| 建物の構造等 | 非事業用 (マイホーム・セカンドハウスなど) |
事業用 (賃貸マンションなど) |
||
| 耐用年数 | 償却率 | 耐用年数 | 償却率 | |
| 木造 | 33年 | 0.031 | 22年 | 0.046 |
| 木造モルタル | 30年 | 0.034 | 20年 | 0.050 |
| 軽量鉄骨(骨格材3mm以下) | 28年 | 0.036 | 19年 | 0.037 |
| 軽量鉄骨(骨格材3mm超4mm以下) | 40年 | 0.025 | 27年 | 0.052 |
| 軽量鉄骨(骨格材4mm超) | 51年 | 0.020 | 34年 | 0.030 |
| 鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 | 47年 | 0.022 |
※軽量鉄骨の場合、骨格材3mm以下又は4mm超の場合は耐用年数及び償却率が異なるので注意。
※事業用で2007(平成19)年3月31日以前に取得した軽量鉄骨の償却率は0.037となります。
※事業用で1997(平成9)年12月31日までに取得した資産については償却率は別途の数値で計算します。
中古で購入した建物の場合は、こちらの計算式で耐用年数を計算します。
中古で購入した建物の耐用年数の計算方法
(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 20%)
※1年未満の端数は切捨て、2年に満たない場合は2年とします。
マイホーム・セカンドハウス以外の事業用の不動産についてはこちらをご参照ください。

譲渡費用とは
譲渡費用(じょうとひよう)とは、土地・建物を譲渡(売却)するために支払った費用で次のものをさします。
- 土地や建物を売るために支払った仲介手数料など
- 登記もしくは登録に支払った費用(登記費用・登録免許税)
- 印紙税で売主が支払ったもの
- 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらう時に支払った立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊しの費用、建物の損失額
- 測量に支払った費用
- 売買契約後に、他に高い金額で売却するために最初の契約者に支払った違約金
- 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
- その他その資産の譲渡価額を増加させるためにその資産の維持や管理のために支払った費用(リフォーム費用)など
譲渡(売却)のために支払った金額なので、居住していた期間の修繕費や固定資産税などその他不動産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用、物件の抵当権抹消費用などは譲渡費用になりません。
詳しくは、国税庁HP「譲渡費用となるもの」をご覧ください。
取得費の計算(例題)
では、実際に計算してみましょう。
例題
1998(平成10)年5月に2,000万円で建築した木造の建物を2016(平成28)年1月に売却しました。この建物には2011(平成23)年3月に500万円かけてリフォームしています。この場合の建物の取得費はいくらになるでしょうか。
新築部分の経過年数は、1998(平成10)年5月〜2016(平成28)年1月なので17年と8ヶ月となります。経過年数の計算は6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てて(5捨6入)計算するので、18年になります。木造なので償却率は0.031になります。
| 減価償却費 = 2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 23年 = 1004万4,000円 取得費 = 2,000万円 − 1004万4,000円 = 9,956,000円 |
リフォーム部分の経過年数は、2011(平成23)年3月〜2016(平成28)年1月なので、4年10ヶ月となります。5捨6入なので5年になります。
| 減価償却費 = 500万円 × 0.9 × 0.031 × 5 = 697,500円 取得費 = 500万円 − 697,500円 = 4,302,500円 |
建物の取得費は、「9,956,000円 + 4,302,500円 = 14,258,500円」ということになります。