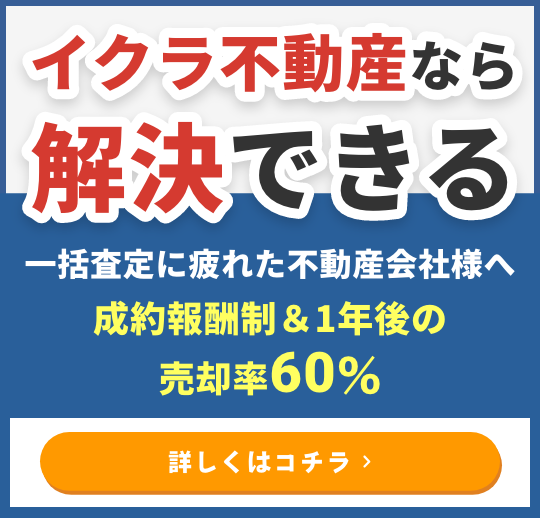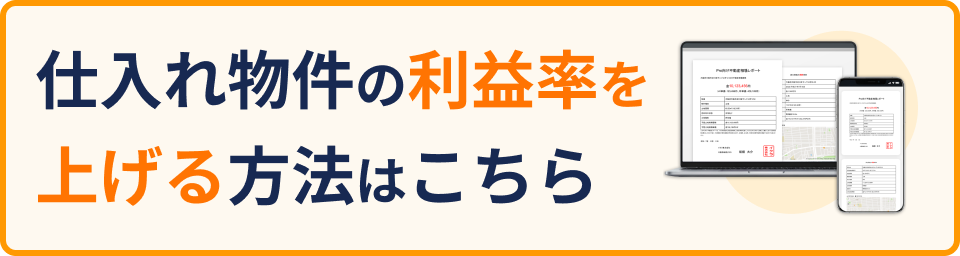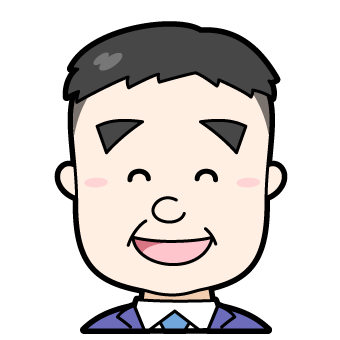
あなたの不動産は道路に接していますか?
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
あなたの不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べることができます。
その結果、道路の種類が43条但し書き(ただしがき)とわかりました。
43条但し書きとはどのような道でしょうか?
43条但し書き(43条2項2号)とは建築審査会の同意が必要な道
| 建築基準法種別 | 内容 | |
| 1 | 42条1項1号 | 4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など) |
| 2 | 42条1項2号 | 都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
| 3 | 42条1項3号 | 既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路) |
| 4 | 42条1項4号 | 都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |
| 5 | 42条1項5号 | 民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。通称位置指定道路 |
| 6 | 42条2項 | 道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路 |
| 7 | 基準法上道路以外 | 43条但し書き(43条2項2号)、単なる通路など |
- 建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある道のことを「43条但し書き(道路と呼ぶこともあるが、道路ではないので通路と呼んでいます)」や「43条2項2号」と呼ぶ
- 43条2項2号の場合は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければならない
- 結論はあくまでも建築審査会に提出しないとわからない
役所で調査する場合
- 「公図」「地積測量図」などを見せながら、現況について説明します。
- 同じ道沿いで、これまでに43条但し書き通路の許可を得た建築物があるかどうか確認します。
- 調査している物件が43条但し書き許可を受けられる見込みがあるか、またはどんな条件をクリアすれば受けられる見込みが出てくるのか確認を取ります。
- また、どのような手続を経て許可を取り、建築できるのかの流れについて、それぞれの市町村によって異なることもあるため確認します。

43条但し書きは建物に対して許可を出すので、再建築の際は許可が必要
建築基準法第43条但し書きは、接道要件を満たさない土地に対して特例を定めたものです。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
【…】
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
※上記は改正前の条文。2018年の改正により「ただし、」以降は、現在の第43条第2項第2号。
但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたものです。そのため、「43条但し書き通路」「43条2項2号」と呼ばれます。
「国土交通省令で定める基準に適合」の基準は、建築基準法施行規則第10条の3第4項に定めがあり、次のとおりです。
- その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること
- その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
- その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、道路に通じるものに有効に接すること
ここから大きく「道路はないけど周囲に広い空き地がある」と「道路みたいなのはあるけど、建築基準法上の道路に該当しない(道路状空地)」の2つに分けることができますが、ほとんどのケースは後者となっています。

(43条但し書き通路の例)
このように、43条但し書きは、現況が道路のように見えても建築基準法上の道路ではなく、建築審査会に認められなければ家を建てることができない通路なのです。建築審査会ということは、特定行政庁に許可を得るということになります。
つまり、あなたの不動産が、43条但し書きにしか接していないと言われると、建築基準法上の道路に接していないということになるため、そもそも家は建てられない土地ということになります。
ただし、特例として今回その土地に家を建てることを許可しているだけで、それが永続性のものではなく、建築のたびに許可を得なければならないため、将来再建築できないケースがあるということは念頭に置いておかなければなりません。
そのため、一般的に建築基準法上の道路に接している不動産より価値が落ちることになるため、銀行によっては住宅ローンの利用を拒否するところもあります。
但し書き通路は1件ごとに指導が異なりますし、役所(特定行政庁)が建築を許可するかどうかは、申請してみなければわかりません。ですが、これではあまりにも不透明なので、前もって許可基準(一括同意基準・包括同意基準)を定めておき、該当する場合は原則として認められることとなっています。
あなたの不動産が43条但し書き通路に接している場合は、特定行政庁の「建築基準法第43条第2項第2号許可に係る一括(包括)同意基準(旧法第43条第1項但し書き許可に係る一括(包括)同意基準)」を確認するとよいでしょう。
「認定制度」について
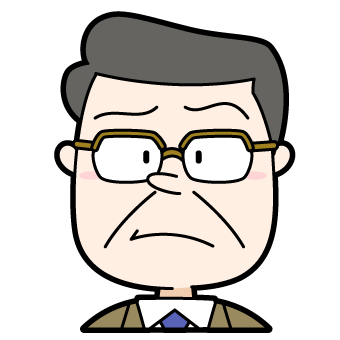
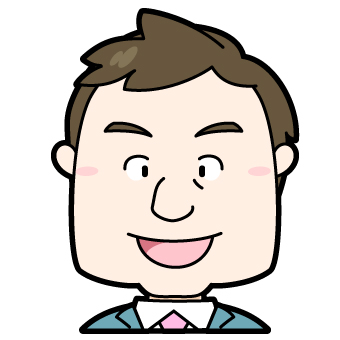
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績の蓄積があるもの(上記「一括同意基準(包括同意基準)」等)の一部について、あらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とする(認定制度)こととなりました。
避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準(※1)に適合する幅員4m以上の道(建築基準法に定める道路以外の道)に2m以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準(※2)に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、接道規制を適用しない
- ※1 「避難及び通行の安全上必要な道の基準」とは、農道等で公共の用に供する道であり、一定の舗装がなされている、あるいは、通路等のうち位置指定道路の基準に適合する道で、道の関係権利者および道を位置指定道路の基準に適合するよう管理する者の承諾(使用合意)が得られていること。
- ※2 「利用者が少数である建築物の用途および規模に関する基準」とは、当該通路等に発生する交通量を制限する観点から、延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅とすること。
なお、2018年前まで、建築基準法第43条本文にあった「ただし、」以降の文言(いわゆるこの項目でいう「但し書き」)については、同法第43条第2項第2号にスライド(項ずれ)して引き続き定められています。
調査方法について詳しくは「42条の建築基準法上の道路と接道義務、調査方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ご覧ください。
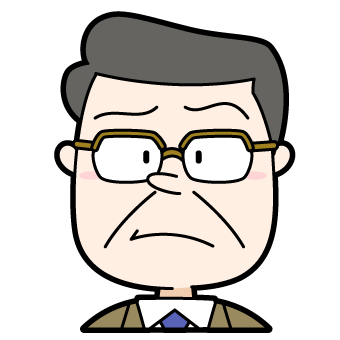
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。