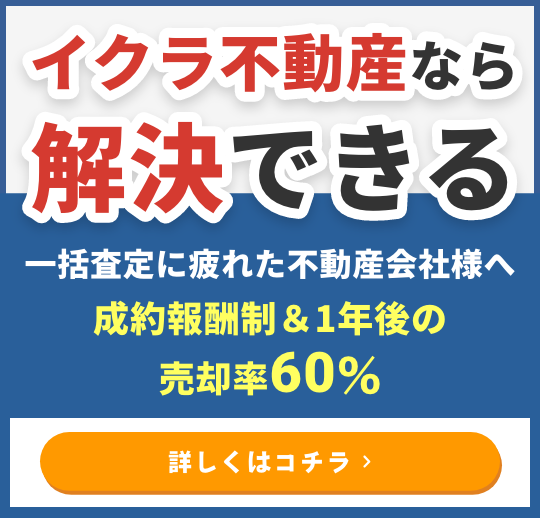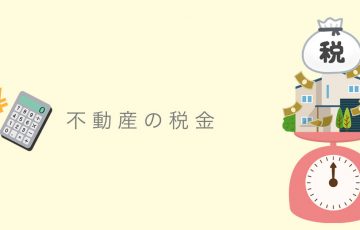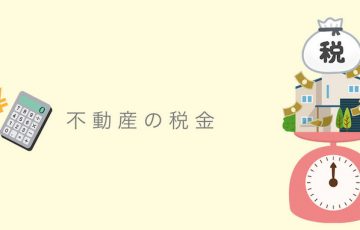あなたが不動産(土地・戸建・マンション)を購入したり、建物を建築するときは登記をします。この登記をする際にかかる税金が「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」です。
登録免許税とはどのような税金で、どのように計算すればよいのでしょうか。また「登録免許税」と「登記費用」の違いは何でしょうか。
ここでは、不動産に関係する登録免許税の計算方法についてわかりやすく説明します。
登録免許税とは
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税する国税で、登記を受けることによって生じる利益に着目して課税される流通税の一つです。税率は他の税金の百分率と異なり、千分率で規定されています。
不動産においては、不動産登記の際に課税されます。不動産登記とは「その不動産の所有はいったい誰のものなのか」などの権利について、法務局(登記所)の登記簿に記載することをいいます。登記簿という証拠書類によって、所有者は自分の土地の所有権を主張できます。このことを法律上では「対抗力」といいます。この対抗力を得ることを利益とみて、登録免許税という税金が課されています。
・登記簿謄本とは?表題部や権利部、甲区や乙区についてまとめた
買主は、購入した不動産が自分の所有物であることを証明するためにも「登記」が必要です。それに対して、不動産を手放す売主には「登記」が必要ないように思えるかもしれませんが、売主に関する登記もあります。
例えば、住宅ローンを完済する場合に必要な「抵当権抹消登記」の登録免許税や、住所を変更している場合に必要な「住所変更登記」は売主が負担しなければなりません。

登録免許税の計算方法
登録免許税の計算方法
登録免許税の税額 = 課税標準 × 税率
※土地の売買による所有権の移転登記については、2019年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。また、一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。
課税標準とは「税金を計算する際の算定基準」のことです。不動産における登録免許税の課税標準は、申請する登記の種類によって、
- 固定資産税評価額(不動産の価額)の場合
- 借りている金額(債権金額)の場合
- 不動産の個数の場合
の3つのパターンがあります。
登記の種類とは具体的に「所有権移転登記」「所有権保存登記」「抵当権の設定登記」などを指します。不動産の登記の種類について詳しく知りたい方は以下をご参照ください。
①固定資産税評価額(不動産の価額)の場合
不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を「所有権移転登記」といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。
所有権移転登記の場合、課税標準は、固定資産台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)になります。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は、「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」を計算する上で基になる金額のことで、3年に一度見直されます。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。
所有権移転登記における登録免許税の計算方法
登録免許税の税額 = 固定資産税評価額 × それぞれの税率
※1,000円未満の端数は切り捨てます。また、税額を計算した金額で1,000円に満たない場合は税額は1,000円になります。
| 土地・建物 | 住宅用建物の軽減 (2020年3月31日まで) |
||||
| 課税標準 | 税率 | 軽減税率 | |||
| 所有権移転登記 | 売買 | 土地 | 固定資産税評価額 | 15/1000 (〜2019年3月31日) 20/1000 (2019年4月1日〜) |
ー |
| 建物 | 20/1000 | 3/1000 | |||
| 相続 | 4/1000 | ー | |||
| 贈与 | 20/1000 | ー | |||
ただし、不動産売買の建物の場合、中古住宅の移転登記の軽減の特例があります。個人の自己居住用の住宅で、住宅取得後1年以内に登記を受けるもので、登記簿面積の床面積が50㎡以上であること、マンションなどの耐火建築物は、取得の日以前に25年以内、木造などの耐火建築物以外は20年以内に新築された場合は、3/1000に減税されます。なお、軽減の適用を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要です。
取得日の年数を超えている場合でも、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの(耐震基準適合証明書)や、既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合には、登録免許税の軽減が受けられます。
さらに、認定長期優良住宅で、マンションなどの共同住宅の場合は1/1000に、戸建の場合は2/1000に、認定低炭素住宅の場合は1/1000に減税されます。
新築の建物における登記(所有権保存登記)
固定資産台帳に登録のない新築の不動産は、固定資産税評価額がないため、類似する不動産の登録価格を基礎として法務局が認定した価格を課税標準とします。それぞれの地域によって異なり、管轄の法務局HPで知ることができます。
・例)大阪府の場合:「不動産登記における評価額のない課税基準について」
そのため課税標準については、不動産を管轄する法務局に問い合わせする必要があります。この新築の建物に行う登記を「所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)」といいます。
新築の建物(所有権保存登記)における登録免許税の計算方法
登録免許税の税額 = 法務局の設定価格 × 4/1000
※1,000円未満の端数は切り捨てます。また、税額を計算した金額で1,000円に満たない場合は税額は1,000円になります。
| 土地・建物 | 住宅用建物(新築建物)の軽減 (2020年3月31日まで) |
||||
| 課税標準 | 税率 | 軽減税率 | |||
| 所有権保存登記 | 法務局の設定価格 | 4/1000 | 1.5/1000 | ||
ただし、こちらにも新築住宅の保存登記の軽減の特例があります。個人の自己居住用の住宅で、新築または取得後1年以内に登記を受けるもので、登記簿面積の床面積が50㎡以上の場合は、1.5/1000に減税されます。なお、軽減の適用を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要です。
さらに、認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅の場合は1/1000に減税されます。
なお、建物の表示登記は非課税です。建物の表示登記(建物表題登記)とは、建物の新築工事が完了して完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記のことです。
②借りている金額(債権金額)の場合
こちらは抵当権(根抵当権)の設定登記の場合で、担保する債権の金額になります(根抵当権の場合は極度額です)。
住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。もし、借りている住宅ローンを返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を「抵当権(ていとうけん)」といい、不動産を抵当権をつけることを「抵当権設定」といいます。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」で、金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。つまり、住宅ローンを借りるときに行う登記です。
抵当権設定登記における登録免許税の計算方法
登録免許税の税額 = 担保する債権の金額 × 4/1000
※1,000円未満の端数は切り捨てます。また、税額を計算した金額で1,000円に満たない場合は税額は1,000円になります。
| 土地・建物 | 住宅用建物の軽減 (2020年3月31日まで) |
|||||
| 課税標準 | 税率 | 軽減税率 | ||||
| 新築建物 | 中古建物 | |||||
| 抵当権の設定登記 | 債権金額 | 4/1000 | 1/1000 | 1/1000 | ||
ただし、こちらにも抵当権の設定登記の軽減の特例があります。抵当権設定登記における住宅用建物の軽減措置は、新築建物、中古建物ともにそれぞれ減税の条件(新築住宅の保存登記の軽減の特例、中古住宅の移転登記の特例)を満たしている住宅に対して行われます。
例えば、所有権移転登記で建物が3/1000に減税された場合は、抵当権設定登記も1/1000に減税されます。
③不動産の個数の場合
住宅ローンの返済が完了した場合には、不動産を売って回収できる権利が消滅したという「抵当権抹消登記」が必要になります。この抹消登記、所有者の住所または氏名の変更登記・付記登記・抹消登記の回復などについては、不動産1個につき1,000円(定額)です。

登録免許税と登記費用の違い
登録免許税は、不動産を登記した際にかかる税金です。その不動産登記を代行してくれる資格ある専門家が司法書士(しほうしょし)です。所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などの登記をする際は、一般的に司法書士に依頼します。このとき、登録免許税・印紙税の他に司法書士へ代行手数料や報酬がかかりますが、これら全てを加えたものが登記費用です。
司法書士の報酬の相場としては、中古物件を購入する際の所有権移転登記と住宅ローンを利用する際の抵当権設定登記をあわせて10〜15万円前後です。
なお、商売として登記の仕事をしない限り、個人でも登記することは可能です。また、新築の「建物の表示登記」については、一般的に土地家屋調査士に依頼し、こちらも手数料や報酬が必要になります。