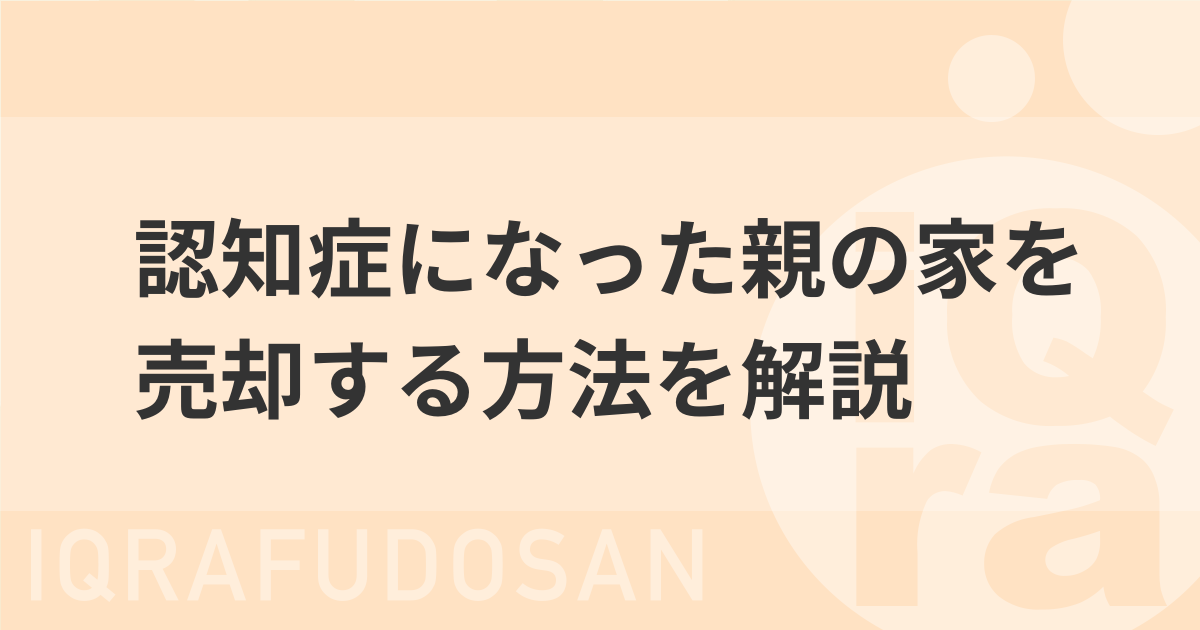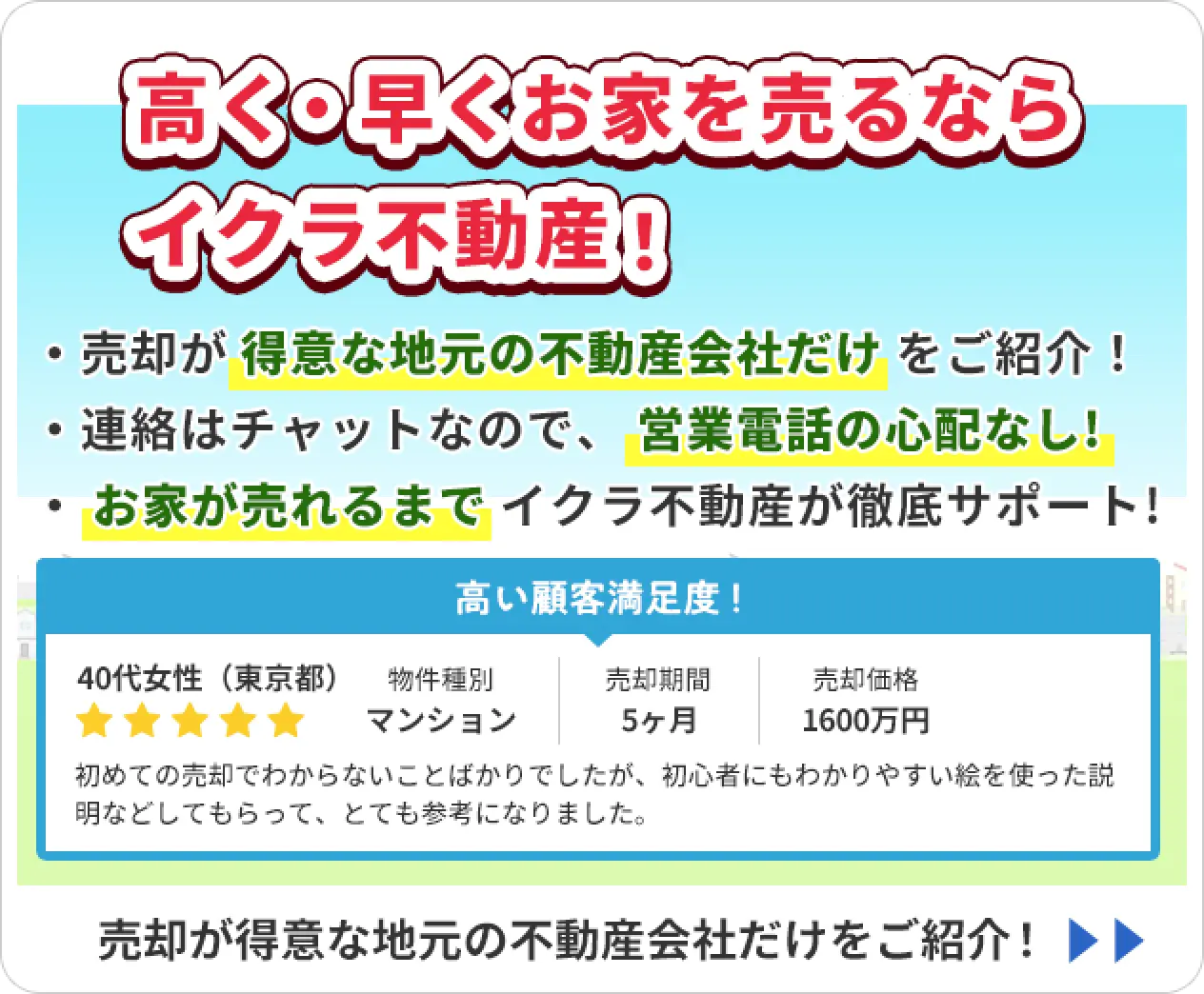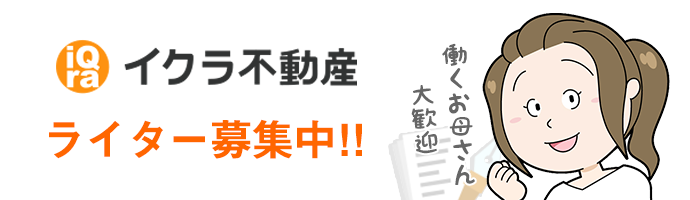高齢者施設への入居費用や介護費用などの捻出のため、親に代わって家を売却したいケースもあるでしょう。
しかし、親名義の家を売却するには、親の「売却したい」という意思確認が必要です。親が認知症や病気などで意思表示ができなければ、家を売ることはできません。
そのような場合は、成年後見制度を利用することになります。
こちらでは、認知症になった親の代わりに家を売却するための成年後見制度の利用方法や注意点についてわかりやすく説明します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 認知症になった親の家を売却するための「成年後見制度」の仕組みについて
- 成年後見制度を利用する際の注意点について
- 成年後見制度の利用申請から不動産売却までの流れについて
- この記事はこんな人におすすめ!
- 認知症になった親の代わりに親名義の家を売却する方法を知りたい人
- 親が認知症になる前に、親名義の家を売ることができるようにしておきたい人
- 認知症の親の家を売るために、成年後見制度の利用や申請方法、注意点などを知りたい人
1.認知症の人は制限行為能力者になる
自分だけで法律行為をすることができる能力を「行為能力」といい、民法においてその行為能力が不足していると考えられる人が「制限行為能力者」です。
認知症の人は、行為能力が不足していると見なされるため、不利な契約を結ばされたりしないように法的に守る必要があります。
そこで、裁判所に申し立てることによって制限行為能力者になり、ほかの人が法律的に支援することになります。これが「成年後見制度」と呼ばれる制度です。
1-1.認知症の人(制限行為能力者)は不動産の売買ができない
判断能力が常に欠けている状態にあるとされる認知症の人(制限行為能力者)は、単独で不動産を売買することはできません。なぜなら不動産の売買は、法律行為である「契約」が含まれるからです。
そのため不動産の売買は、保護者である成年後見人が代理権を行使して行います。
しかし成年後見人は、不動産を含む本人の財産を自由に処分できるのかというと、そのようなことはありません。
たとえば居住用の不動産は、本人にとって貴重な財産であるうえ、売却してしまったら住む場所がなくなってしまうことになります。
成年後見制度は、本人が不利益を受けないようにサポートするための制度であるため、後見人は本人が困るような行為を行うことは許されていないのです。
1-2.成年後見制度を検討する前に
認知症であってもどの程度症状が進行しているのかによって、直ちに意思・判断能力が欠如しているとはされません。
不動産の売却には、司法書士が名義人の本人確認のため、面談を行いますが、そのときに「意思能力が確認できない」と判断された場合、契約がストップします。
認知症が進行していくスピードには、もちろん個人差がありますが、症状の悪化まで8年から10年程かけてゆっくりと進行していくケースも多いです。
そのため、まずは医師の診断を受けましょう。認知症が疑われる場合でも、「意思能力」があると判断されれば、通常どおり親自身が不動産を売却できる可能性もあります。
その際は、医師の診断書(意思能力が欠如していない旨の確認)を取得しておくと安心です。
家の売却方法については「【不動産売却の期間・流れ・費用のまとめ】初めての不動産売却で知っておくべきこと」で、また実家の売却については「実家の売却完全ガイド!売却方法や手順、税金などを生前、相続後、空き家別に解説」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
2.「成年後見制度」について
成年後見制度とは、認知症などで判断能力を喪失してしまった方の代わりに成年後見人などを立てて、不当な契約締結などから守ることができる制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
2-1.将来に備えておくことができる任意後見制度
「任意後見制度」は、認知症の初期症状段階である場合に利用できます。
親の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ後見人を誰にするのか、どのような支援をしてもらうのか自分で決めておくことができる制度です。
任意後見制度を利用するには、親本人と後見人が、親の家の最寄りの公正役場で任意後見契約の公正証書(公証役場の公証人が作成する証書のこと)を作成します。
判断能力が衰えてきたときに家庭裁判所で改めて手続きを行います。任意後見制度では、後述する法定後見制度とは異なり、裁判所の許可がなくても家の売却が可能です。
手続きについては「任意後見の申し立て手続き」も併せてご覧ください。
2-2.判断能力が十分でなくなっているときは法定後見制度
認知症の症状が進行してしまい、判断能力が十分でなくなってしまった場合は「法定後見制度」の利用を検討することになります。
なお、法定後見制度は、判断能力の程度によって、
- 被補助人
- 被補佐人
- 被後見人
の3つのどれかに分類されます。それぞれ保護されるレベルにどのような違いがあるのかを確認しておきましょう。
2-2-1.①被補助人
判断能力が不十分であると考えられる人で、本人の同意により家庭裁判所で補助開始の審判を受けたときには、被補助人になります。
被補助人は、単独の法律行為は制限されていません。審判によって同意が必要とされた法律行為をするときのみ補助人の同意が必要です。
もし同意、または同意に代わる許可を得ないで法律行為をした場合には、補助人が取り消せます。
2-2-2.②被補佐人
被保佐人は、判断能力が著しく不十分である人で、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた人を指します。
被保佐人は、通常の法律行為については単独で行えますが、民法第13条で示されている不動産の売買や借金、相続の承諾や法規、遺産分割など財産処分をするときや、その処分について承認を与えるときには保護者である保佐人の同意が必要です。
保佐人は被保佐人に代わって法律行為を行うことはできませんが、保佐人の同意が必要な行為を同意なく行った場合には取り消せます。
2-2-3.③成年被後見人
判断能力が常に欠けているとされる人で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた人が成年被後見人です。
成年被後見人は、買い物などの日常行為は単独でできますが、法律行為をひとりで行うことはできません。成年後見人の同意があったとしても、本人が単独で行った法律行為については取り消しできます。
たとえ同意があったとしても、判断能力が欠けているため期待通りに行動するとは限らないためです。
保護者となる成年後見人は、代理人として財産にかかるすべての法律行為を行えるうえ、日常生活に関する行為以外の行為のすべてを取り消す権利があります。
法定後見制度の手続きについては「法定後見で後見人などを決める手続き」も併せてご覧ください。
2-3.成年後見制度利用時の注意点
成年後見人制度を利用すれば、認知症になった親の代わりに家を売却することができます。しかし、利用の際には、いくつかの注意点を知っておかなければなりません。
法定後見人制度を利用する際の注意点について説明します。
2-3-1.①必ずしも子供が後見人になれるわけではない
まず、注意すべきなのは、必ずしも子供が成年後見人等になれるわけではないという点です。
申し立てができるのは、本人や配偶者、4親等内の親族などに限られていますが、法定後見制度で法定後見人として認められるためには、「自分が法定後見人になる」という意思を家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。
法定後見人は、本人に代わって財産の管理を行うという重い責任を負う立場となるため、弁護士や司法書士など専門的な観点で資産管理ができる第三者が適任と判断されることも多いです。
特に、次のようなケースでは、親族ではなく第三者が選ばれる可能性が高くなります。
- 親族が本人の財産を使い込んでしまう恐れがある
- 親族間でトラブルなど争いがある
- 高齢の親族しかいない
最高裁判所事務総局家庭局が発表した「成年後見関係事件の概要―令和4年1月〜令和4年12月」を見ても、配偶者や親、子などの親族が後見人に選任されたケースは、全体の約19%しかありません。
| 親族 | 合計7,560件 | ||
| 親族以外 | 合計32,004件 | 弁護士 | 8,682件 |
| 司法書士 | 11,764件 | ||
| 社会福祉士 | 5,849件 | ||
| 市民後見人 | 271件 | ||
(参考:成年後見関係事件の概況-令和4年1月~令和4年12月-)
子供である自分が後見人に選ばれなかったからといって、法定後見制度の利用をやめることはできないため、この制度を使うかどうかは慎重に判断する必要があります。
2-3-2.②第三者が後見人選ばれると継続的に報酬が必要になる
次に注意しなければならないのは、弁護士や司法書士など専門職後見人が選任された場合は、本人の財産から家庭裁判所が決めた額の報酬が支払われるという点です(1000万円程度の財産管理で月に2万円程度)。
さらに、「家の売却が完了したから」といった理由で後見人を解任することはできず、本人が亡くなるか意思能力が回復するまで続きます。
当然、専門職後見人への報酬がずっと発生し続けることにも注意が必要です。
2-3-3.③法定後見人であっても家を自由に売却できない
法定後見人として認められたからといって、自由に家を売却できるわけではありません。
民法では、成年後見人が本人の居住用の建物や敷地を売却するときには、裁判所の許可が必要と定めています。(民法第859条の3)
売却する場合は、あらためて「親が所有している家を売りたい」という家庭裁判所への手続きが必要です。
申し立てを受けた家庭裁判所からの許可を得られれば売却できますが、前述した通り「売却が本人のためになるか」というポイントで判断されます。
たとえば本人の認知症が進み、施設に入ることになったけれども資金が足りない、あるいは生活費や医療費が不足して生活に支障が出ているような正当な理由があれば、自宅の売却が認められる確率は高いです。
また自宅といっても、居住の実態がなければ居住用の不動産とはされず、売却できる可能性もあります。田舎に自宅を残して子どもの家でずっと一緒に暮らしている、すでに施設に入っていて家に戻る予定はないようなケースは非居住用とされ、売却が認められる可能性があるでしょう。
3.成年後見の申し立て手続き
成年後見人等の申し立ては、任意後見と法定後見によって手続きが異なります。
それぞれの手続き方法を説明します。
3-1.任意後見の申し立て手続き
任意後見の申し立てをするには、まずは後見人と任意後見契約を結ばなくてはなりません。任意後見契約は、法律によって、公正証書でしなければならないと定められています。
公正証書とは、法律に関する争いを未然に防ぐために、証明力と執行力を有している公文書です。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人(後見人が契約の内容通りの仕事をしているかを監督する人)が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。
任意後見の申し立ての進め方は、次のとおりです。
- STEP.1本人が任意後見人を選ぶ任意後見人には、家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人にもなってもらうことができます。また、複数人にすることも可能です。
ただし、未成年者や破産者、本人と訴訟をした者など、法律がふさわしくないと定めている事由のある者はなることができません。
- STEP.2契約内容を決める任意後見人にどのような内容を依頼するのかは、当事者間の合意により自由に決めることができます。
任意後見契約で委任することができるのは、財産管理に関する法律行為(自宅等の不動産や預貯金の管理、税金の支払いなど)と介護や生活面の手配(介護サービス締結等の療養看護に関する事務や法律行為)です。
また、上記法律行為に関する登記の申請なども含まれます。
- STEP.3公証役場で任意後見契約を結ぶ本人と任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。
公正証書でない任意後見契約は、無効となります。
- STEP.4必要書類をそろえ、 家庭裁判所で申し立てを行う本人の判断能力が低下した場合は、任意後見契約を開始するために本人の住所地の家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をします。
なお、申し立てを行えるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者です。
- STEP.5家庭裁判所が任意後見監督人を選任する任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」の審判が確定すると、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
なお、任意後見契約は、東京法務局で登記されます。任意後見人は、法務局で「登記事項証明書」の交付を受けることにより、自身の代理権を第三者に証明することができます。
3-2.法定後見で後見人などを決める手続き
法定後見では公正証書での契約は不要です。直接、家庭裁判所に申し立てを行います。
- STEP.1「後見開始の審判」を申し立てる必要書類をそろえ、本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所に成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の選任を申し立てます。
申立てを行えるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者などです。
- STEP.2家庭裁判所の調査官が調査を行う調査官による本人や候補者からの事情の聞き取りや必要があると判断された場合には、医師によって本人の判断能力の診断が行われます。
※補佐・後見の場合は、原則本人の判断能力について鑑定が必要です。
- STEP.3後見(保佐、補助)開始の審理・審判提出書類、調査結果、鑑定結果などが審査され、家庭裁判所は、後見(保佐、補助)開始の決定(審判)を行い、あわせて成年後見人(保佐人、補助人)を選任します。
申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」が送付されます。
- STEP.4後見(保佐、補助)開始の審判確定と登記審判書が送付されて2週間以内に、誰も不服を申し立てない場合は、後見(保佐、補助)開始審判の法的な効力が確定し、東京法務局に審判内容が登記されます。
4.成年後見人が不動産を売却する方法
成年後見人が被成年後見人の不動産を売却する方法は、不動産が居住用か非居住用かによって必要な手続きなどが異なります。
4-1.居住用不動産の売却方法
成年後見制度の目的は、判断能力が不足する本人を保護することです。そのため、本人の財産を処分するには、本人の意思を尊重し、その心身や生活の状態に十分配慮することが求められています。
居住用不動産を売却するときにも、本人の生活、精神状況への十分な配慮が必要です。住む家がなくなってしまうと、本人が非常に困ったことになることは容易に想像できます。精神的にも不安定になり、良い影響を与えるとは考えられません。
そのため民法では、成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときには、裁判所の許可を得る必要があると定めています。(民法第859条の3)
もし成年後見人が裁判所の許可を得ずに居住用不動産を勝手に売却してしまった場合は、その行為自体を取り消すのではなく、法的に無効(最初からなかったことにする)とされます。
売却して受け取った価格を買主に返却しなければならないだけでなく、成年後見人の義務違反となり解任されてしまう可能性も高いです。
なお、成年後見監督人が選任されている場合には、居住用不動産の売却には、裁判所の許可と同時に成年後見監督人の許可も得なければなりません。成年後見監督人は、後見人が本人の利益になる行為をきちんと行うかをしっかり監督する役目があるためです。
ただし、元の任意後見契約書の内容に同意が不要との規定があれば、その限りではありません。
4-1-1.居住用不動産売却の申請方法
居住用不動産を売却するときには、次の書類が必要になります。
- 申立書
- 不動産の全部事項証明書
- 不動案売買契約書の案
- 処分する不動産の評価証明書
- 不動産業者作成の査定書
- 本人または成年後見人(補佐人、補助人)の住民票に変更があった場合、変更があった者の住民票写しまたは戸籍付票
- 成年後見監督人(補佐監督人、補助監督人)がいる場合、その意見書
これらの書類を本人の居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。なお必要書類は家庭裁判所によって異なる場合があるため、必ず事前に確認するようにしてください。
4-1-2.居住用不動産の売却が許可になるかの判断要素
居住用不動産の売却が許可になるかどうかは、次のような項目を判断材料とするのが一般的です。
①売却の必要性
本人の財産状況から考える売却の妥当性
②本人の生活・看護の状況や本人の意向
入所や入院の状況、帰宅の見込み、帰宅となった場合の帰宅先の確保状況
③売却条件
売却条件の妥当性
④売却後の代金の保管
売却代金が本人のために使われるように入金や保管されるか
⑤親族の処分に対する態度
推定相続人の同意の有無
居住用不動産の売却が、成年後見人の勝手な判断ではなく、本人の利益のためと判断された場合に限り、売却許可が下されます。
4-2.非居住用不動産の売却方法
非居住用不動産については、その売却理由が本人の保護・利益につながる正当なものであれば、裁判所の許可を得ることなく売却が可能です。
本人が長く生活していくうえの生活費や医療費が不足してきた、あるいは施設に入居するため、売却によって費用を捻出するなどといった場合は、正当な理由と判断される可能性が高いと考えられます。
ただし、売却の金額が相場とかけ離れて安い場合には、本人の利益にならないと判断される場合があるため注意が必要です。
非居住用不動産の売却についても、家庭裁判所には事前に伺いを立てておくほうが望ましいでしょう。
4-3.居住用と非居住用を見極める方法
売却を検討している不動産が、居住用と非居住用のどちらに該当するのかの判断がむずかしいケースもあります。
民法上での居住用不動産とは、「(本人の)居住の用に供する建物又はその敷地」とされています(民法第859条の3)。つまり、居住用かどうかは、本人の住民票があるかどうかといった形式的な基準ではなく、生活実態によって判断されるということです。
たとえば高齢者の場合、施設に入る、入院するなどでその不動産に住んでいないケースもあるでしょう。しかし過去に生活していた、また将来生活する可能性がある不動産については、居住用不動産に該当すると判断されるのが一般的です。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 親が認知症になり、施設への入所費用や医療費などに充てるためであっても、親名義の家を子供が勝手に売ることはできない
- 認知症になり判断力が低下した親の代わりに家を売りたい場合は、本人に判断能力がない場合に裁判所が後見人を決める「法定後見制度」を利用する
- 法定後見人を利用する際の注意点は次の3つ
・必ずしも子供が後見人になれるわけではない(裁判所から後見人として選ばれるのは弁護士や司法書士などが多い)
・第三者が後見人選ばれると継続的に報酬が必要になる
・後見人になったとしても、家の売却には家庭裁判所への手続きが必要になる - 法定後見人が決定するまでは、1〜3ヵ月程度かかるのことが多い。手続きが大変な場合は、弁護士や司法書士に依頼するという手もある
- 認知症に備えるには、親自身があらかじめ「後見人」を誰にするかを決めておくことができる「任意後見制度」を利用すると良い
- 成年後見人等の申し立ては、任意後見と法定後見によってそれぞれ手続きが異なる
- 成年後見人が被成年後見人の不動産を売却する場合、居住用不動産か非居住用不動産かによって手続きが異なる
- 居住用不動産の売却は、裁判所の許可が必要
- 居住用かどうかは、本人の住民票があるかどうかといった形式的な基準ではなく、生活実態によって判断される
ここまで見てきたように、認知症の症状悪化によって判断能力がなくなってしまった場合、親の家を勝手に売却することはできず、道のりは非常に厳しいです。
まだ、初期症状の段階であれば、あらかじめ後見人を誰にするのか決めておくことができる「任意後見制度」を利用するのがおすすめです。
ただし、認知症であると本人も受け入れることができないケースも多いため、将来のリスクについて親本人も理解し、行動しない限り、なかなか話が進まないということもあるでしょう。
認知症になった親の家を売却したいけど、どうすればいいのかわからないという方はまず「イクラ不動産」でご相談ください。
無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格がわかります。さらに、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選べます。
さらに、不動産の売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも無料で相談できるので安心です。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。