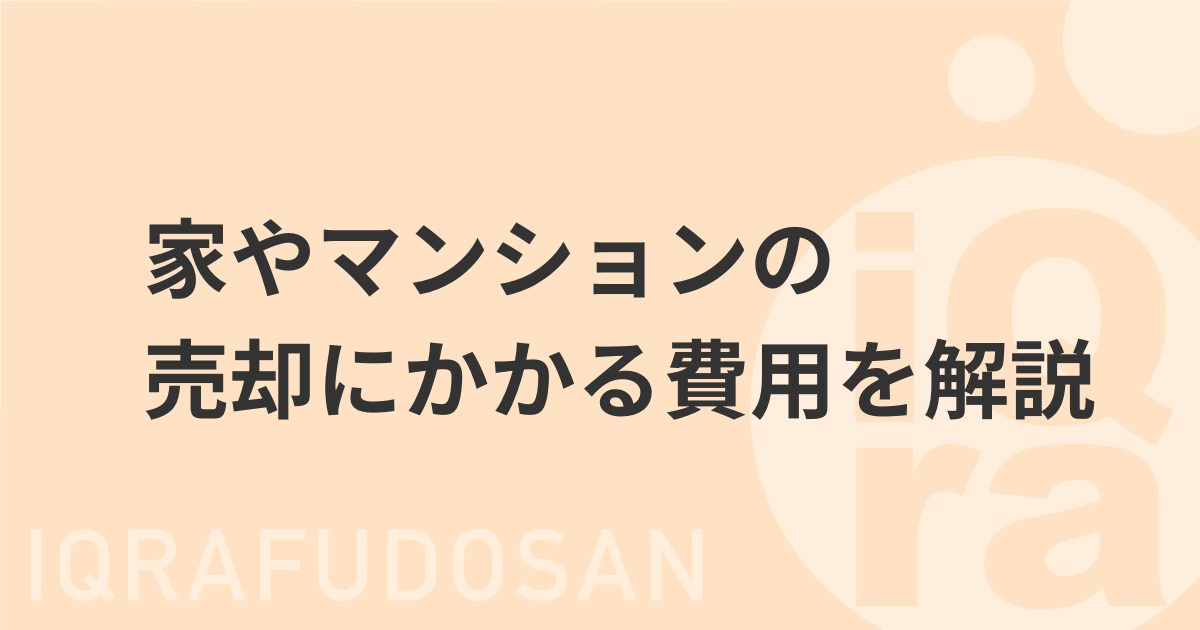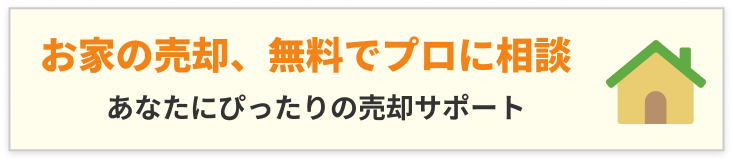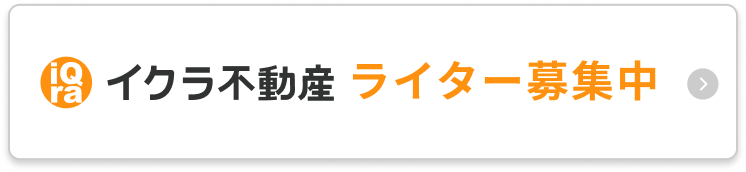家やマンションといった不動産を売却する際は、さまざまな費用が必要です。仲介手数料や売却に伴う税金などを合わせると、一般的に売却額の4〜5%程度の費用がかかります。
こちらは、実際に「イクラ不動産」に寄せられたご相談の一例です。
【実際の相談例】
💬 まとまったお金が必要なので、家の売却を考えています。
でも、家を売るには仲介手数料やいろいろな費用がかかると聞きました。どれくらいかかるのかわからず不安です…。
家やマンションなどの売却代金すべてが手元に残るわけではないことを踏まえたうえで、売り出し計画や資金計画を立てることが大切です。
ここでは、家やマンションの売却にかかる費用やその内訳についてわかりやすく説明します。家を売却したら手元にお金がいくら残るのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 家やマンションの売却で必ずかかる費用についてわかる
- 家やマンションの売却で状況によって必要となる費用についてわかる
- 家の売却で最終的に手元に残る額を計算する方法がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 家やマンションの売却を予定している人
- 家の売却でかかる費用のおおよその額を知っておきたい人
- 最終的に家を売ったらいくら手元に残るかを調べておきたい人
1.家やマンションの売却で必ずかかる費用
3つのポイント
- 家の売却で必ずかかる費用は、仲介手数料、印紙税、所有権移転登記費用、印鑑証明書の費用の4つ
- 仲介手数料は取引額に応じて上限額が定められている
- 所有権移転登記費用は買主が負担することが多いが、必ずしも決まっているわけではない
まず、家やマンションを売却したときに必ずかかる費用を確認していきましょう。
不動産を売却する際に、必ずかかる費用は次の4つです。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代
- 所有権移転登記費用:買主が負担することが多い
- 印鑑証明書の費用:契約書に押印する印鑑の証明に使う
1-1.仲介手数料
仲介手数料とは、家の売却が成功した際に不動産会社に支払う手数料のことです。
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料は上限額が定められており、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。
ただし、一般的には上限額いっぱいに設定している不動産会社がほとんどです。
1-1-1.仲介手数料の計算方法
仲介手数料の上限額と計算方法は、次の表のようになります。
| 売買代金 | 仲介手数料の上限額(税込み) |
|---|---|
| 200万円以下の部分について | 5.5% |
| 200万円超え400万円以下の部分について | 4.4% |
| 400万円を超える部分について | 3.3% |
| (特例)800万円以下の場合 | 33万円 |
たとえば、売買代金が3,000万円(税別)の場合の仲介手数料の上限額の計算は、次のようになります。
ただし、この式だと計算が複雑になるため、400万円を超える売買価格の場合は、次の速算式を使うことが多いです。
1-1-2.仲介手数料上限の最低額は30万円
国土交通省は不動産業界における空き家流通などの業務への参入を後押しするために、2024年7月1日、売買価格が800万円以下の場合については、仲介手数料上限額を30万円(税込み33万円)とすることを定めました。
これにより、売買価格が500万円や300万円といった場合でも、不動産会社が設定できる仲介手数料の上限額は30万円(税込みだと33万円)になります。
1-1-3.仲介手数料には売却活動費も含まれる
仲介手数料には、売却を成約させるために不動産会社がかけた費用のすべてが含まれます。
そのため、売主から特別に依頼した場合を除き、家の査定費用や売却中の広告費用などを別途で請求されることはありません。
また、仲介手数料は、あくまでも売却ができたことに対する成功報酬です。したがって、万が一売れずに売却をやめた場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。
1-1-4.仲介手数料の安さで不動産会社を選ばないようにする
売却費用の中でも仲介手数料が占める割合は大きいため、どうしても仲介手数料が安い不動産会社を選びがちです。
しかし、仲介手数料が安い不動産会社を選んでしまった結果、しっかりと売却活動をしてもらえなかったというケースもあります。なぜなら、先に述べたように、仲介手数料には売却活動の費用も含まれているからです。
数十万円の仲介手数料を節約したために、家やマンションがなかなか売れず、結局、数百万円の値下げをすることになったら元も子もありません。
手元に残るお金を少しでも多くしたいのであれば、目先の仲介手数料の安さではなく、あなたの大切な不動産を高く売ってくれる売却力のある不動産会社を選ぶことが大切です。
仲介手数料については、「家を売るときの仲介手数料はいくら?高い?なぜかかるの?」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-2.印紙税
買い手が見つかって売買契約を結ぶことが決まれば、売買契約書を作成します。
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書なので、定められた金額の収入印紙を貼付して消印することによる納税が必要です。
印紙税の税額は、契約書に記載されている取引額によって決まります。
おもな印紙税の額は、次の表のとおりです。
| 契約金額 | 本属税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 100万円を超え〜500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え〜1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え〜5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え〜1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え〜5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
※2027年(令和9年)3月31日までは軽減税率適用
(国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
売主と買主、それぞれの契約書に印紙税額分の収入印紙の貼付が必要です。一般的には売主が保管する契約書の印紙税は売主が、買主が保管する契約書の印紙税は買主が負担します。
ただし、売主分の売買契約書の原本が必要でなければ、収入印紙を貼付した買主の契約書のコピーで代用することも可能です。その場合は、売主が保管する売買契約書の印紙税はかかりません。
1-3.登記にかかる費用
登記とは、その不動産の現在の状況や権利関係の情報を登記簿に記載することです。
売買や相続、贈与、建物を新築したときなど、不動産(土地・一戸建て・マンション)の登記に変更があった場合は、登記手続きをしなければなりません。
1-3-1.登録免許税
売却して所有者が変わったときは、所有者移転の登記手続きと、手続きのための登録免許税が必要です。
一般的に買主が負担することが多いですが、どちらが負担するかは決まっていないため、売主が負担することもあります。
登録免許税の額は、不動産の売買価格の1,000分の20( 2026年3月31日までの間に登記を受ける場合は1,000分の15)です。
また、住宅ローンを借りて購入した場合だと、購入した不動産を借入額の担保にするために抵当権の設定登記がされています。
住宅ローンが残っている家を売却したときは、ローンを完済して設定されていた抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)が必要です。
抵当権抹消登記を自分で行う場合の登録免許税は、1つの不動産に対し1,000円です。土地と建物は別の不動産とみなされるため、一戸建ての場合は2,000円になります。
そのほか、次のような場合にも売主が登記変更をする必要があるため、登録免許税が発生します。
- 登記簿上の住所と現住所が違う場合
- 結婚等で登記簿上の名字と違う場合
- 相続等で登記簿上の所有者と名義が違う場合
- 権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した場合
- 登記していなかった(未登記)場合
1-3-2.司法書士に登記手続きを依頼する費用
所有権移転や抵当権抹消などの登記手続きは、すべて自分で行うこともできます。しかし、手続きが煩雑で手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に手続きを依頼した場合は、登記内容や登記する不動産の価額にもよりますが、5万円程度が報酬の相場となっています。
1-4.印鑑登録証明書の発行費用
不動産の売買契約を締結する際には、契約書に押印する印鑑の登録証明書の提出を求められます。そのため、あらかじめ印鑑登録をして、印鑑登録証明書を取得しておかなければなりません。
印鑑登録証明書の発行費用は自治体によって異なりますが、役所の窓口での交付や郵送による請求の場合は300円程度、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで交付する場合は150〜200円程度です。
ちなみに、印鑑登録証明書の有効期間は3ヵ月なので、取得時期に注意しましょう。
2.家やマンションの売却でかかることがある費用
3つのポイント
- 住宅ローンが残っている場合は繰り上げ返済手数料が必要だが、無料の場合もある
- 家やマンションを売却して利益が出た場合は、その利益(譲渡所得)に対して納税が必要な場合がある
- 土地の境界があいまいな場合は測量費、建物が古い場合は解体費など、状況によってかかる費用がある
次に、家やマンションを売却したときに、状況によってはかかることがある費用を確認していきましょう。
不動産の売却で、必要となることがあるおもな費用は、次のとおりです。
- 住宅ローンの繰り上げ返済手数料:住宅ローンが残っている場合にかかる
- 譲渡所得税:売却して利益が出た場合に課せられる
- その他の費用:土地の測量費、引っ越し代など
2-1.住宅ローンの繰り上げ返済手数料
住宅ローンが残っている家を売却する場合は、住宅ローンを返済しなければなりません。その際に、住宅ローンの繰り上げ返済手数料が必要になる場合があります。
住宅ローンの繰り上げ返済手数料は、住宅ローンを借りた金融機関によって異なります。多くの場合、無料〜3万円程度です。
また、窓口、電話、インターネットなど、手続きの方法によっても手数料が変わります。一般的に、インターネットの手続きであれば、無料のところが多いです。
あらかじめ、住宅ローンを組んだ金融機関に確認しておきましょう。
2-2.譲渡所得税
家を買ったときよりも高く売却できて多くの利益が出た場合は、翌年の確定申告で売却で得た利益に対して税金を納めなければなりません。
この不動産を売却したときに出た利益は譲渡所得(じょうとしょとく)と呼ばれ、この譲渡所得に課せられるのが譲渡所得税です。譲渡所得税は、所得税と住民税から成ります。
売却して利益が出なかった場合や利益が少なかった場合は、譲渡所得税を納める必要はありません。
譲渡所得の計算は、次のとおりです。
このように、単に「売った額(売却額)」から「買った額(購入費)」を引くだけでなく、購入にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)も差し引くことができます。
差し引く額が多くなるほど譲渡所得が少なくなり、譲渡所得税を減らすことができます。売買にかかった費用を証明するものがあれば、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。
2-2-1.長期譲渡所得と短期譲渡所得
譲渡所得税を算出する際の税率は不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合に用いるのは短期譲渡所得の税率、5年超えの場合は長期譲渡所得の税率です。
長期譲渡所得になると、次の表のように、短期譲渡所得よりも税率が安くなります。
| 所有期間 | 譲渡所得税(※) | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超え | 15.315% | 5% | 20.315% |
※譲渡所得税には、2037年(令和19年)まで復興特別所得税が上乗せされています。
ここで注意しなければならないのは、適用期間のカウント方法です。
実際に所有していた年数ではなく、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかを判定します。
くわしくは、国税庁のサイトで確認してみてください。
2-2-2.所有期間10年超えだとさらに税率が軽減される
譲渡所得税の税率は、所有期間が10年を超えるとさらに低くなります。
税率は、課税される譲渡所得額が6,000万円以下の部分と6,000万円を超える部分とで、次の表のように異なります。
| 課税長期譲渡所得額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分について | 14.21% |
| 6,000万円超の部分について | 20.315% |
この特例も、売却した年の1月1日時点で所有期間を判定することになるため注意しましょう。
くわしくは、国税庁のサイトで確認してみてください。
国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
2-2-3.3,000万円のマイホーム売却時の特別控除
所有期間が5年を超える長期譲渡所得であっても、譲渡所得の2割もの額を納税しなければならないことに驚かれた方がいるかもしれません。
しかし、譲渡所得(売却利益)が出ても、マイホーム(居住していた家)を売却した場合には、必要要件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除される特例があります。
つまり、この特例が適用されれば、家やマンションを売却して譲渡所得が発生しても、3,000万円までなら税金が課せられないのです。
適用にはさまざな要件があるため、くわしくは国税庁のサイトで確認してみてください。
2-3.そのほかの費用
そのほかの費用は、状況によって大きく変わります。どのような費用がかかる可能性があるのかをみてみましょう。
2-3-1.土地の測量費用
土地や一戸建てを売却する際に、土地の面積や境界があいまいな場合は、測量や境界確定が必要となります。
測量にかかる費用は、30~40坪(100〜130㎡)程度の一般的な住宅地だと、30万~45万円程度が相場です。
測量費用については「土地の測量が必要なケースと費用についてまとめた」でくわしく説明しているので、ぜひご覧ください。
2-3-2.リフォームやハウスクリーニング費用
売却する家の状態によっては、リフォームやハウスクリーニングが必要な場合もあります。
ハウスクリーニングは、家の広さや作業箇所によっても変動しますが、5万〜20万円くらいが相場です。
一方、リフォームは高額な費用がかかるうえ、買主が購入後に自分の好きなようにリフォームしたいことも多いため、売却前に実施するのはあまりおすすめではありません。
独自で判断せず、不動産会社と相談してから決めましょう。
くわしくは「お家を売る前にリフォームするべき?それともそのまま売却するべき?」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
2-3-3.建物の解体費用
築年数が古い家の場合は、建物に価値がないため解体して更地にすることを条件に売却することが多いです。その費用を売主が負担しなければ、なかなか買い手がつきにくいこともあります。
家などの建物の解体費用は構造や大きさによって異なります。
木造で1坪あたり4万~5万円、軽量鉄骨造で1坪あたり6万~7万円くらいが相場です。
ただし、先に解体して更地にしてしまうと、固定資産税が上がるなどのマイナス面があるため、まずは古家付き土地として売り出すことがおすすめです。
解体費用については、「家の解体の相場っていくらくらい?解体前に確認しておくべきポイントも解説!」で説明しています。参考にしてみてください。
2-3-4.引越しや残置物の処分費用など
居住中に家を売却した場合は、引き渡しまでに引越しする必要があります。また、売却した家が空き家の場合も、残置物(置きっぱなしで残された荷物のこと)があれば処分しなければなりません。
引越し費用は時期や荷物の量にもよりますが、10万~30万円くらいを考えておくとよいでしょう。
また、残置物の処分費用は量と処分する物によりますが、10万〜50万程度かかることもあります。なぜなら、残置物の処分は「産業廃棄物収集運搬業」の認可を受けた業者でないと行うことができないからです。
なかには無許可で行う会社や、山に不法投棄するなどの悪質な行為をしている場合もあります。そのような業者にかかわらないためにも、信頼できる不動産会社などから紹介してもらえば安心です。
3.家を売却して手元に残るお金の計算方法
3つのポイント
- 売却代金から売却にかかるさまざまな費用を差し引いた額が最終的に手元に残る額
- 実際に売れないと売却代金がいくらになるのかわからないので、まずは相場価格で試算すると良い
- 相場価格を調べる方法として、周辺で似たような物件が売り出されている価格を調査する、インターネットで成約価格を調べるなどがある
最後に、家を売却して手元にいくら残るかの計算方法を説明します。
3-1.売却代金から売却にかかる費用を引いた額が手元に残る額
「家を売ったお金」から売却にかかった「諸費用」を引いた残りのお金が、最終的に手元に残る金額になります。
家の売却代金から、家を売却したときにかかる費用の合計額を差し引けば、手元に残るお金を計算することが可能です。
家の解体費用や土地の測量費用がかかる場合は、当然ですがその分も差し引くことになるため、手元に残る額は少なくなってしまいます。
3-2.家の売却代金は相場価格で代用する
手元に残る額を計算しようと思っても、「売却代金(家がいくらで売れるか)」は、実際に家を売りに出してみないことにはわかりません。
そのような場合は、今、売りに出したらいくらで売れそうかという「相場価格」を調べることで、おおよその売却代金の見当をつけることができます。
相場価格は、不動産会社の査定価格が適切かどうか判断するためにも必要です。家やマンションの売却が決まったら、まずは相場価格を調べるようにしましょう。
3-2-1.相場価格を調べる方法
自分で相場価格を調べる方法として、次のようなものがあります。
- 近隣で似たような物件がいくらぐらいで売り出されているかを調べる
- レインズ・マーケット・インフォメーションや不動産情報ライブラリなどで成約価格を調べる
近隣で似たような物件がいくらぐらいで売り出されているのかは、比較的調べやすいでしょう。
ただし、売り出し価格と成約価格とは異なることに注意が必要です。一般的に、売り出し価格は値引きを考慮して相場価格よりも高めに設定されています。目安として、売り出し価格は相場価格よりも1、2割程度高いと考えておきましょう。
レインズ・マーケット・インフォメーションは不動産流通機構が、不動産情報ライブラリは国土交通省が運営している不動産取引情報サイトです。 これらのサイトには実際に取引された成約価格が掲載されているため、相場価格の参考になります。
しかし、自分で相場価格を調べるのは大変です。不動産会社に査定を依頼すれば精度の高い相場価格がわかりますが、いきなり不動産会社に査定を依頼するのは気が引けるという人も多いでしょう。
そのような場合におすすめなのが「イクラ不動産」です。イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、簡単に素早く、無料&秘密厳守であなたのお家がいくらぐらいで売却できるのかを調べることができます。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 家やマンションを売却するときには、売却代金の4〜5%程度の費用がかかる。
- 家の売却で必ずかかるおもな費用は、仲介手数料、印紙税(収入印紙代)、登記手続きの費用の3つ
- 家の売却でかかることがあるおもな費用は、住宅ローンの繰り上げ返済手数料、譲渡所得税、測量や解体費用などがあげられる
- 家を売却して利益がたくさん出た場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税を納めなければならない
- 土地の境界が不明確な場合は測量費用が、古い建物を取壊して更地にするなら解体費用などもかかる
- 家やマンションなどの売却で手元に残るお金は、売却代金から売却にかかる費用を差し引いた額になる
- 売却代金はわからないので、今、売ったらいくらぐらいで売れそうかという「相場価格」を調べることで、おおよその計算ができる
- 相場価格を自分で調べるには、近隣で似たような物件の売り出し価格を調べる、レインズ・マーケット・インフォメーションや不動産情報ライブラリなどで成約価格を調べるなどの方法がある
家やマンションといった不動産の売却には、仲介手数料や印紙税などの費用がかかります。
また、引っ越し代や土地の測量費用などがかかることもあるため、売却代金がすべて手に入るわけではないことを理解しておくことが大切です。
家やマンションを売却して最終的に手元にいくら残るかを調べるためは、売却代金から売却にかかる費用を差し引かなければなりません。
売却額は実際に売り出してみないとわからないので、まず、いくらぐらいで家が売れそうなのか「相場価格」を調べる必要があります。そのためには、不動産会社による査定が必要です。
しかし、いきなり不動産会社に問い合わせをするのは気が引けるという方もいるでしょう。そのようなときは、「イクラ不動産」をぜひご利用ください。
「イクラ不動産」では、無料&秘密厳守であなたのお家がいくらぐらいで売却できるのかを調べることができます。
また、実際に不動産会社に相談してみたいとなった場合は、あなたにピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。不動産会社とのやりとりは、気軽なチャットです。
さらに、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにわからないことがあればいつでも相談できるので、安心して売却を進めることができます。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
- 合わせて読みたい
- 家を売却するとき、リフォームって必要?リフォーム費用もご紹介