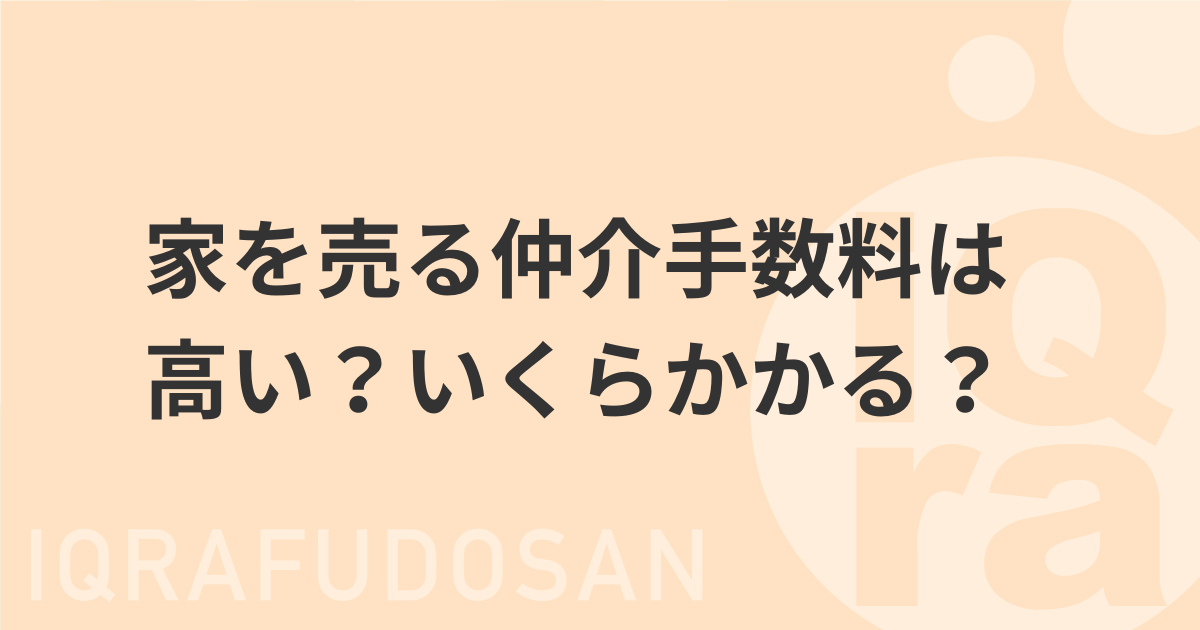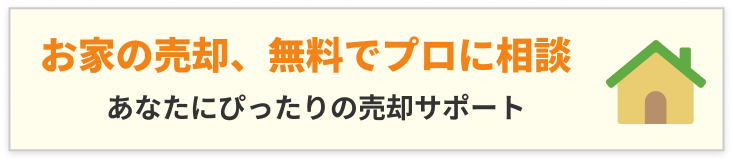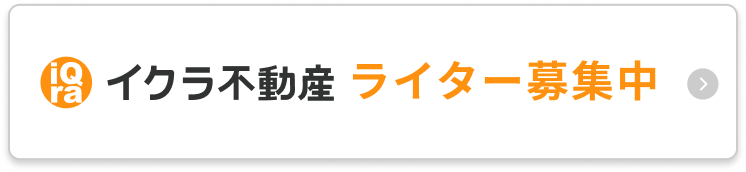マンションや一戸建て、土地といった不動産を売りたい場合、ほとんどの人が不動産会社に依頼します。そして、売却が成功した際に、不動産会社に支払うのが仲介手数料です。
不動産の売却を検討している人の中には、仲介手数料が高いと感じている人や、どのような費用が含まれていて、なぜかかるのかわからないという人もいることでしょう。また、不動産売却で損をしたくないと、少しでも仲介手数料が安い不動産会社を探そうとしている人もいるかもしれません。
しかし、仲介手数料の安さが、結果として不動産売却での損や失敗につながることもあるため注意が必要です。
こちらでは、不動産を売却するときにかかる仲介手数料とはどのようなものか、また、なぜ仲介手数料の安さが不動産売却失敗につながる恐れがあるのかについてわかりやすく説明します。
【この記事で具体的にわかること】
- 仲介手数料とはどのようなものか、またいくらかかるのか計算方法がわかる
- 仲介手数料の安さで不動産会社を選んではいけない理由がわかる
- 仲介手数料に関するよくある質問と回答がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 家やマンションなどの売却を考えている人
- 不動産売却にかかる仲介手数料の額を知りたい人
- 仲介手数料の額で不動産会社を選ぶべきか悩んでいる人
1.不動産仲介手数料とは?まずは基本を押さえよう
3つのポイント
- 仲介手数料とは、不動産取引が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬である
- 仲介手数料には、物件の広告費や契約手続きにかかる費用など、不動産取引を成立されるための費用が含まれている
- 多くの不動産会社にとって、仲介手数料は重要な収益源となっている
まず、仲介手数料についての基本的な知識を押さえておきましょう。
1-1.仲介手数料とは不動産会社に支払う「成功報酬」
仲介手数料とは、不動産の売買や賃貸の取引をまとめてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。
家やマンションといった不動産の取引には、専門的な知識が欠かせません。そのため、ほとんどの場合、不動産会社に売買や賃借の「仲介」を依頼することになります。
そして、依頼を受けた不動産会社が、売主(貸主)と買主(借主)の間に入って取引をまとめることで、双方から受け取ることができる「成功報酬」が「仲介手数料」なのです。
1-2.仲介手数料にはどのような費用が含まれるのか?
不動産会社が受け取る仲介手数料には、不動産取引を成立させるために必要となる次のような費用が含まれています。
- 物件の広告や宣伝費(チラシやポータルサイトへの掲載料など)
- 物件情報資料の作成費
- 内見案内にかかる費用
- 契約条件の調整や手続きにかかる費用
- 契約書類や重要事項説明書の作成にかかる費用
- 契約および引き渡しの手続きにかかる費用
不動産取引は大きな金額が動くため、入念な調査や準備が必要です。また、少しでも早く取引をまとめるためには、広範囲に向けて宣伝活動をしなければなりません。当然ですが、しっかりと調査をして広く宣伝活動をすればするほど費用がかかります。
また、仲介手数料は多くの不動産会社にとって、店舗の維持費や人件費にも直結している重要な収益源です。つまり、仲介手数料は、不動産会社が事業を維持していくための「生命線」であるとも言えるでしょう。
2.仲介手数料の計算方法・いくら支払うのか?
3つのポイント
- 仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法で計算方法が定められている
- 仲介手数料上限額の範囲内であれば自由に設定できるが、上限額いっぱいで請求されることが慣習となっている
- 「低廉な空家等の売買」における仲介手数料上限額の改定により、上限額の最低額は30万円(+消費税)となった
次に、不動産会社に家やマンションの売却を依頼した場合、仲介手数料をいくら支払うことになるのか、計算式を含めて説明します。
2-1.仲介手数料上限額の計算方法
不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業法」における「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって、次のように上限の額の計算方法が決まっています。
| 取引額の部分 | 計算式 |
|---|---|
| 200万円以下の部分について | 取引額の5%(+消費税) |
| 200万円超え〜400万円以下の部分について | 取引額の4%(+消費税) |
| 400万円超えの部分について | 取引額の3%(+消費税) |
たとえば、取引額が3,000万円の場合だと、仲介手数料の上限額は次のような計算式になります。
【取引額3,000万円の仲介手数料の計算式】
仲介手数料は、こちらの計算式で算出された上限額を超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。
しかし、上限いっぱいに設定するのが慣習であり、一般的です。
2-2.仲介手数料上限額の最低額は「30万円+消費税」
たとえば取引額が100万円の場合、先に説明した計算式だと、仲介手数料の上限額は「 200万円×0.05%=10万円(+消費税)」となります。しかし、実際問題として、不動産取引をこの仲介手数料の上限額で行うのはむずかしいケースが多いです。
そこで、2024年7月1日より宅地建物取引業法が、次のように改定されました。
取引額が800万円以下の「低廉な空家等の売買」の仲介手数料上限額:30万円(+消費税)
理由は「空き家」、特に「地方の空き家」増加問題です。
国としては、空き家の活用を掲げています、しかし、地方の空き家などは物件価格が低く、遠方になると通常より調査費がかかって不動産会社が赤字になることもあり、不動産会社側が売却を断るなど、不動産取引自体を敬遠するケースも見受けられたため、このような改定が実施されました。
ただし、不動産会社は媒介契約を結ぶ際に、あらかじめ売主に対して説明をして両者間で合意する必要があります。
不動産を売却する際の費用については、「お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
3.仲介手数料が安い不動産会社のリスク・知らないと損をする!
3つのポイント
- 仲介手数料は上限額だけ定められているので、安くしたりゼロにしたりすることは違法ではない
- 仲介手数料を安くするため物件の宣伝や広告費を削ることになり、売れにくくなって値引きせざるを得ないケースもある
- 仲介手数料を安くするよりも、上限額で支払って高く売却してもらうほうが得になることを知っておくことが大切
家やマンションなどを売却する際の費用を節約するために、仲介手数料が安い不動産会社を探す人も多く見受けられます。
しかし、仲介手数料が安い不動産会社に売却を依頼したため、結局、損をするといったケースもあるため注意が必要です。
3-1.なぜ仲介手数料を安くできるのか?
最近では、仲介手数料ゼロや半額にする不動産会社も増えてきています。
仲介手数料は、あくまでも法律で上限金額を決められているだけなので、仲介手数料を半額にしたりゼロにしたりすることは違法ではありません。
仲介手数料を値引くことで、集客数の増加が見込める場合があるのも事実です。
また、両手仲介(不動産会社が一つの取引で売主と買主の両方の依頼を受けること)の場合、売主または買主の一方から手数料を受け取ったり、両方から半額だけ受け取ったりしても利益が出ることがあるため、仲介手数料を安くしているケースもあります。
3-2.仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのはおすすめではない
仲介手数料の安さで、集客数を増やしている不動産会社もあります。
しかし、仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのはおすすめできません。なぜなら、集客するための宣伝や広告にかける費用が少なくなりがちなため、売れにくい原因になるからです。
仲介手数料による収益が減ると、どこかでその分を調整しなければなりません。店舗維持費や人件費を削るのはむずかしいため、宣伝や広告費を削ることになり、購入希望者が見つかりにくい状況に陥ります。そうなると、値下げせざるを得なくなり、結果として手元に入るお金が少なくなる恐れがあるのです。
3-2-1.仲介手数料を安くするより高く売るほうが得になりやすい
相場価格が3,000万円の家を売却した事例で考えてみましょう。
3,000万円の取引が成立した場合の仲介手数料の上限額は、消費税も含めると105万6,000円です。これが半額になると、約50万円、得したように思います。
しかし、仲介手数料を安くしたために買い手がなかなか見つからず、200万円値引きをすることになれば、結果として150万円の損です。仲介手数料を満額支払ってしっかりと売却活動をしてもらい、相場価格の3,000万円で売却してもらった場合よりも、手元に残るお金は150万円も少なくなってしまいます。
つまり、仲介手数料を節約するよりも、たとえ上限いっぱいの仲介手数料を支払ってでも、できるだけお家を高く売ってくれる不動産会社に頼むほうが最終的に早期、高値で売却できる率が高くなると言えます。
不動産会社がどのように購入希望者を集めるかについては、「「家を売るとき、不動産会社はどうやって買いたい人を集客しているの?」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
4.仲介手数料についてよくある質問
3つのポイント
- 仲介手数料は、売買契約時に半額、残代金決済・引渡し時に半額を支払うことが多い
- 不動産会社が売主に対して仲介手数料以外の広告料金などを請求することは宅建業法違反になる
- 契約解除になったら仲介手数料は返還されるが、売主や買主都合による解除の場合は返還されない場合がある
最後に、不動産を売却するときにかかる仲介手数料についてよくある質問をまとめました。
4-1.仲介手数料はいつ支払うの?
仲介手数料は成功報酬のため、不動産会社が仲介手数料の支払いを求める権利は、売買契約が成立した時点で発生します。
この時点で全額請求されたとしても違法ではありませんが、一般的には不動産取引は物件の引き渡しと決済まで継続するため、売買契約時に半額、残代金決済・引渡し時に半額を支払うことが多いです。
しかし、売買契約時または残代金決済・引渡し時に全額とするケースもあり、必ずしも半額ずつになるとは決まっていません。
売却依頼の媒介契約を結ぶ際に、いつ仲介手数料を支払うのか、不動産会社に必ず確認しましょう。
4-2.別途、広告料金を請求された場合は?
不動産会社から、特別に広告した分として、仲介手数料とは別に広告の料金を請求される場合があります。
しかし、不動産会社は売主に対し、別途広告の料金を請求することは許されていません。このような行為は、宅建業法違反です。
仲介手数料を定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の第6には、報酬(仲介手数料)の上限額の定めに続けて、次のような内容があり、不動産会社はこの条項を根拠にします。
依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額、及び当該代理または媒介に係る消費税額、及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額については、この限りでない。
所定の報酬とは別に広告の料金を請求ができるのは、東京高裁昭和57年9月28日判決(判時1058号70頁)の判決例に示された、次の内容を満たす場合に限られます。
- 通常必要とされる程度の広告宣伝費用は、営業経費として不動産会社の報酬(仲介手数料)の範囲に含まれている
- 広告の料金に相当する額とは、大手新聞への広告掲載料等、報酬(仲介手数料)の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味する
- 不動産会社が売主の依頼を受けていないのに、一方的に多額の費用を要する広告宣伝を行い、その費用の負担を売主に強要することは違反
- 売主から広告の依頼があり、その費用の負担について事前に売主の承諾があった場合に限る
- 事後で、上記と同視することのできる場合は、売主が広告を行ったこと、その費用の負担につき全く異議なくこれを承諾した場合に限る
不動産会社の多くが、広告料金のルールを誤解して、売主の了解されあれば、仲介手数料の他に広告料金をもらってもよいと考えています。その結果、宅建業法違反の広告料の授受が行われているケースが見受けられます。
売主の了解ではなく、売主からの依頼です。
「了解」とは、理解すること、のみこむことの意味であり、「依頼」は、他人に要件を頼むことの意味であるため、意味がまったく異なります。
もちろん、売主が自ら不動産会社に特別な広告を依頼した場合は、広告料金の支払いが必要です。
4-3.契約が解除になった場合は?
契約が解除になるにはさまざまなケースがありますが、住宅ローンが承認されなかった、火災や地震等の自然災害によって不動産が消滅してしまったなど場合は、不動産会社は報酬の請求権を失うので、支払った仲介手数料がある場合は返還されます。
売主または買主の都合により手付解除になった場合は、仲介手数料を全額請求される場合があります。
手付解除とは、売主、買主共に合意により定めた手付解除期日までであれば、理由を問わず買主は手付金の放棄、売主は手付倍返し(手付金を返した上で、手付金と同額の金員を支払うこと)をすることによって不動産売買契約を解除することができるというものです。
しかし、不動産会社の考えによっては減額されるケースや手数料を支払わなくていいケースもありますので、媒介契約を結ぶ前に、万が一のことも考えて、確認しておくべきです。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 仲介手数料とは不動産取引が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬で、物件の広告費や契約手続きにかかる費用など、不動産取引を成立されるための費用が含まれている
- 仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法で次のように取引額に応じて計算方法が定められている
(200万円以下の部分×0.05+200万円超400万円以下の部分×0.04+400万円超の部分×0.03)×1.1(消費税) - 仲介手数料上限額の範囲内であれば自由に設定できるが、上限額いっぱいで請求されることが慣習となっている
- 「低廉な空家等の売買」における仲介手数料上限額の改定により、上限額の最低額は30万円(+消費税)となった
- 仲介手数料は上限額だけ定められているので、安くしたりゼロにしたりすることは違法ではないが、宣伝や広告費を削ることになり、売れにくくなって値引きせざるを得ないケースもある
- 仲介手数料を安くするよりも、上限額で仲介手数料を支払って高く売却してもらうほうが得になることを知っておくことが大切
- 仲介手数料は、売買契約時に半額、残代金決済・引渡し時に半額を支払うことが多い
- 不動産会社が売主に対して仲介手数料以外の広告料金などを請求することは宅建業法違反になる
- 契約解除になったら仲介手数料は返還されるが、売主や買主都合による解除の場合は返還されない場合がある。媒介契約締結時に確認しておくのがおすすめ
家やマンションを売却する際にかかる費用の中でも、仲介手数料は大きな割合を占めるため、仲介手数料の安い不動産会社を探す人もいるかもしれません。
しかし、仲介手数料が数十万円安くなったとしても、売却額が数百万円安くなってしまったら元も子もありません。
仲介手数料の額ではなく売却活動をしっかりとしてくれる不動産会社を選べば、より早く、高く売ってくれる可能性が高くなるため、最終的に手元に残る額が多くなります。
そのような優良な不動産会社を探している方におすすめなのが、「イクラ不動産」です。
イクラ不動産なら、売却したい不動産がある地域にある不動産会社の売却実績がひと目でわかるため、本当に売却に強い信頼できる不動産会社を選ぶことができます。
また、イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、無料で簡単に素早く相場価格を知ることが可能です。
さらに、売却でわからないことがあれば、イクラ不動産の専門スタッフに無料でいつでも相談できるため、安心して売却を進めることができます。
ご利用はすべて無料&秘密厳守です。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
- 合わせて読みたい
- 【不動産売却の基礎知識まとめ】初めて家を売るときに知っておくべきこと
- 不動産売却における減価償却とは?計算方法を知っておこう
- 契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを確認
- マンションを売るとき仲介手数料は値引きしてもらえる?交渉のポイントを確認
- 家の解体の相場っていくらくらい?解体前に確認しておくべきポイントも解説!
- 不動産を売るタイミングはいつ?3つのお悩みポイントを解決する
- イクラ不動産とは
- 売るのか貸すのかどちらにすべき?賃貸のメリットとデメリットについてまとめた
- 本当に春と秋が家を売るベストシーズン?不動産売買の真実を徹底検証
- なぜ投資用不動産のオーナーチェンジ物件は居住用の物件より安いのか
- レインズとはなにかわかりやすくまとめた