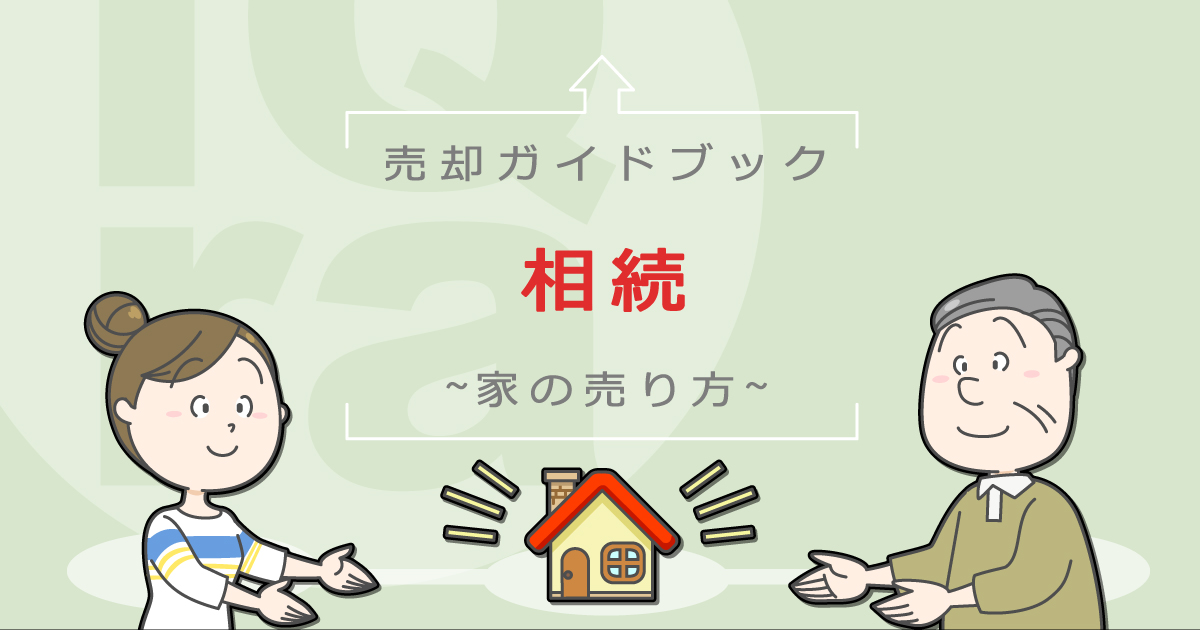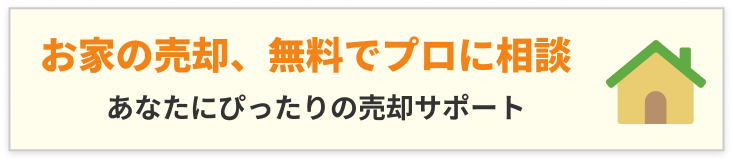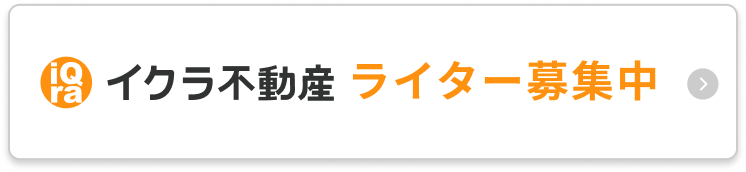兄弟など複数の相続人で不動産を相続すると、どのように分けるか分割方法でトラブルになりがちです。
さらに、実家に住んでいている相続人がいると、分割のための売却がしづらいという問題も発生します。
こちらでは、兄弟など複数人で実家を相続するときにトラブルを避けてスムーズに分割できる方法と、実家に住んでいる相続人がいるため売却できない場合の対処法についてわかりやすく説明します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 兄弟(複数の相続人)で家や土地といった不動産を分割相続する方法がわかる
- 兄弟の法定相続分の割合や遺言や寄与分がある場合などについてわかる
- 相続した家に住み続けたい兄弟(相続人)いるけれども、家を売却したい場合の対処法がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 兄弟で実家を相続することになった人
- 相続した実家を兄弟でトラブルなく分割したい人
- 相続した実家を売却したいけれども、住んでいる相続人がいる場合の対処法を知りたい人
不動産売却について基本から解説
- 実家の売却完全ガイド!売却方法や手順、税金などを生前、相続後、空き家別に解説
- 相続した不動産の売却方法から流れ、手続き、相続税対策まで徹底解説!
- 相続した家を解体する注意点は?メリット・デメリット、解体費用について解説
- 家や土地などの相続不動産がいらない場合の相続放棄や処分方法をわかりやすく解説
「売却一年生」TOPに戻る
1. 相続した不動産の分割方法をおさらいする
3つのポイント
- 相続した不動産を複数の相続人で分割する方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つ
- 相続した不動産を売却すれば、分割時のトラブル回避だけでなく税金や管理費用がかからなくなるのでおすすめ
- 空き家のまま放置して「特定空き家」になると、さまざまな不利益につながるので注意する
家や土地といった不動産の相続は、現金や品物よりも分割がむずかしいためトラブルが発生しやすくなります。
まず、兄弟であるかどうかにかかわらず、複数の相続人で不動産を分割する方法をおさらいしておきましょう。
2-1. 相続財産の分割方法と不動産の場合について
相続した財産(不動産)を複数の相続人で分ける方法は、次の4つです。
| 分割方法 | どのような方法か | 不動産の場合 |
|---|---|---|
| ①現物分割 | そのままの状態で財産を分ける | 不動産を分割(分筆)し、相続人それぞれが分割した不動産の所有者になる |
| ②換価分割 | 財産を売った現金を分ける | 不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける |
| ③代償分割 | 財産を受け取った者が、ほかの者に差額金などを支払う | 相続人のうちの一人が不動産の所有者となり、ほかの相続人が相続すべき不動産分の代金を支払う |
| ④共有分割 | 複数人が共同で財産を所有する | 複数の相続人が共同で不動産の名義人となる(共有名義にする) |
この4つのなかで、相続した不動産を分けるおすすめの方法は②の換価分割です。
相続した不動産の利用予定がなければ、売却した代金を相続人で分ける方向で検討すると良いでしょう。
2-2. 相続した不動産を売却するメリット
相続した家や土地といった不動産を相続人で分ける際は、売却した現金を分ける換価分割がおすすめです。
相続した不動産を売却するメリットとして、次の3つがあげられます。
- 相続財産分割時のトラブルが生じにくい
- 不動産の管理費や税金がかからなくなる
- 一定期間内に売却すると特例や控除が受けられる
それぞれのメリットをくわしく説明します。
2-2-1.相続トラブルが生じにくい
相続人が複数いる場合、亡くなった人の遺言状や法律に則って相続財産(遺産)を分割します。
これは、相続財産が現金や物品であっても家や土地などの不動産であっても同じです。
しかし、不動産の場合だと1つとして同じものがなく、また定価もないため現金のように明確に分けることができません。
そのため、特に相続財産を分割する際、不動産のままで分けるよりも、売却した現金を分けるほうがトラブルが生じにくいと言えます。
2-2-2.管理費や税金がかからなくなる
所有者が亡くなったとしても、家や土地などの不動産には、固定資産税が毎年課せられます。
また、適切に維持するための管理費用が必要です。マンションであれば、管理費や修繕積立金の支払いがあります。
しかし、売却してしまえば、それらの費用はかかりません。相続人が複数いる場合も、誰がどれだけ負担するかで揉める心配がなくなります。
2-2-3.特例や控除を受けられる
不動産を相続した場合、相続税がかかります。また相続した不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税も納めなければなりません。
しかし、一定期間内に相続して売却すれば、相続税や譲渡所得税の特例や控除を受けられます。
そのため、いずれ売却するのであれば、適用できる期間内に売るのがおすすめです。
2-3. 相続した不動産を空き家で放置するリスク
相続した不動産をどうすれば良いかわからず、とりあえず相続人全員の共有名義にして、空き家にしたまま放置するケースもよく見受けられます。
しかし、特に戸建ての家の場合に注意しなければならないのが、この空き家のままの放置です。
先にも述べたとおり、空き家であっても固定資産税が課せられます。また家をきちんと維持していくためには、管理費用が必要です。
適切な管理をせずに放置していると、建物が傷んだり雑草が生えたりして廃屋になる可能性があります。
廃屋になって各自治体の「空き家条例」に抵触すると、所有者へ勧告や措置命令が出され、固定資産税の額が跳ね上がったり、強制的に建物が解体され費用を請求されたりする恐れがあるため注意が必要です。
空き家条例については、「空き家予備軍とは?「空き家」になる前にとるべき対策を解説!」の記事で説明しています。ぜひ一読してみてください。
これらの理由から、相続したまま放置している空き家がある場合は、できるだけ早めに売却するのがおすすめです。
相続した不動産や放置している空き家を少しでも早く、良い条件で売りたいのであれば、そのような売却を得意としている不動産会社を探す必要があります。
しかし、どの不動産会社に任せれば良いのか見極めるのは困難です。
そのような場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。
売りたい相続不動産がある地域で、相続物件や空き家の売却を得意とする、売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことができます。
さらに、イクラ不動産独自の価格シミュレーターで、簡単に素早く相場価格を知ることも可能です。
連絡は売主であるお客様からのため、不動産会社からのしつこい営業電話やメールの心配もありません。
2.兄弟の法定相続分についてのおさらい
3つのポイント
- 法定相続人とは民法で規定された相続人となる人のことで、親が亡くなった場合の兄弟は法定相続人となる
- 法定相続分とは民法で規定された法定相続人が受け取れる相続財産の割合のことで、兄弟は原則として同じ割合
- 遺言がある場合や寄与分、特別受益がある場合は、兄弟の相続分は同じにならないことがある
次に、兄弟で遺産を相続することになった場合、どのような割合で相続することになるかについてもおさらいしておきましょう。
遺言書があれば遺言書の内容に沿って遺産分割することになりますが、遺言書がない場合は、遺産を相続するのは法定相続人です。
2-1.法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって規定された一定の順序に従って相続人となる人のことで、配偶者と一定の血族(けつぞく:亡くなった人の血縁者)からなります。
まず、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人です。そして、配偶者は、ほかの血族相続人と共同して相続します。
法定相続人の順位は次の表のとおりです。
| 血族相続人 | 内容 |
| 第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく:養子を含む子供・孫など) | 常に相続人となります。子供が死亡の場合は孫が相続人となります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます」)。 |
| 第2順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など) | 直系卑属がいない場合、相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人とななります。 |
| 第3順位 被相続人の兄弟姉妹 | 直系卑属・尊属共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が死亡の場合、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。 |
配偶者がいない場合は、相続人の順位によって法定相続人が決まります。たとえば、配偶者がいなくて子どもがいる場合は、相続人は子どもだけです。亡くなった人の子ども2人(兄と弟)がいて兄が亡くなっていた場合、兄に子ども(亡くなった人にとっての孫)がいれば、兄の子どもと弟が相続人になります。
したがって、第1〜3順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはありません。あくまでも第1順位がいなければ第2順位といったように、次の順位が相続人となります。
こちらの記事で説明する「兄弟」とは、第3順位である被相続人(亡くなった人)の兄弟ではなく、第1順位である被相続人の子どもが兄弟の場合についてです。
2-2.法定相続分とは
法定相続分とは、民法によって規定されている、法定相続人がどの程度の相続財産を受けとれるかの取り分(割合)のことです。
| 法定相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者と直系卑属(子供・孫など)の場合 | 配偶者1/2 子供(孫)1/2(複数の場合1/2を人数で分けます。) |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合 | 配偶者2/3 父母(祖父母)1/3(複数の場合1/3を人数で分けます。) |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数の場合1/4を人数で分けます。) |
| 配偶者がいない場合 | それぞれ法定相続人となる順位の中で均等に分配 |
被相続人に配偶者がおらず、子供が2人いる場合だと、その2人の子供(兄弟)への相続は平等に2分の1ずつになるのが基本です。兄弟が3人なら、3分の1ずつになります。
2-3.兄弟の法定相続分が平等にならないケース
法定相続分は、兄弟であれば平等です。
しかし次の3つのケースでは、兄弟の相続分が平等にならないことがあります。
- 遺言があるケース
- 寄与分があるケース
- 特別受益があるケース
それぞれのケースを説明します。
2-3-1.遺言があるケース
法定相続分より優先されるのが、亡くなった方による遺言(ゆいごん・いごん)です。
たとえば「兄には自宅を、弟には現金を」といった遺言があれば、そのとおりに相続されることになり、自宅の価額が3,000万円で現金が1,000万円といった不平等が生じることがあります。
ただし、遺言で「すべての相続資産を兄に」と書かれていたような場合だと、弟が主張すれば「遺留分」が保証され、弟が遺産の一部を相続することが可能です。
民法で最低限保証されている相続割合のこと。兄弟2人が相続人の場合、兄弟それぞれの遺留分は1/4。たとえば、遺産総額が1億円の場合、遺言で兄に全財産を相続させるとなっていても、弟は2,500万円の遺留分を主張して受け取ることができる。
2-3-2.寄与分があるケース
寄与分(きよぶん)とは、亡くなった方の財産の維持や管理に貢献した人に与えられるものです。
たとえば、兄が亡くなった被相続人と同居していて、亡くなるまで生活の面倒を見ていたり介護費用を負担していたりした場合は、兄に対しての寄与分が認められ、相続分の割合が変わる可能性があります。
2-3-3.特別受益があるケース
特別受益(とくべつじゅえき)とは、亡くなった人が生前、特定の相続人に対してだけ資金を提供していたような場合に考慮されるものです。
兄だけが、亡くなった人から生活の面倒を見てもらっていたりマイホーム費用などの負担をしてもらっていたりすれば、兄に対して特別受益があったと見なされる可能性があります。
たとえば、相続財産が1,000万円で兄の特別受益が500万円だった場合、みなし相続財産は特別受益を加算した1,500万円です。弟が相続するのはこのうちの半分なので750万円となり、兄は特別受益を除いた250万円を相続します。
この特別受益を考慮した計算方法は、「特別受益の持ち戻し」と呼ばれるものです。
ただし、遺言書に「兄の特別受益を持ち戻すことを免除する」との記載があれば、遺言に書かれていることが優先されます。
3.相続した実家を兄弟で分割する4つのケース
3つのポイント
- 「現物分割」で不動産を兄弟で分けるのは、土地なら可能だが現実問題としてむずかしい
- 「共有分割」で不動産の所有者を相続人全員にすると、将来的にトラブルを生じやすい
- 相続した家に住む人がいる場合は「代償分割」、利用予定がない場合は売却して「換価分割」するのがおすすすめ
相続した家などの不動産を兄弟(複数の相続人)で分割するときに取れる方法は、最初に説明した次の4つです。
- 現物分割
- 共有分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれの方法で相続した不動産を兄弟で分割するとどのようになるか、ケース別にくわしく説明します。
3-1.①「現物分割」のケース
現物分割で相続した不動産を兄弟で分けるケースでは、不動産をそのままの形で分割することになります。
たとえば、300平方メートルの土地を相続して兄弟3人で現物分割した場合、それぞれが相続する土地は100平方メートルずつです。
ただし、建物がある場合だと公平に分割することはむずかしいため、あまり現実的ではありません。
・納得して相続すれば、相続後にもめる可能性が低い
・物理的に公平に分けることができる
・狭い土地や建物がある場合は分割しづらい
・兄弟にとって家が不要な場合は成立しにくい
3-2.②「共有分割」のケース
共有分割で相続した不動産を兄弟で分けるケースでは、相続する家を兄弟が共有で所有することになります。
たとえば、2人の兄弟が共有で家を2分の1ずつ相続するなら、所有権の持分割合はそれぞれ2分の1ずつです。
・公平に分割することができる
・どちらか一方の独断で売却や活用をすることができなくなる
・将来的に兄弟の配偶者や子などに所有権が移行し、家の共有者が増える可能性がある
3-3.③「代償分割」のケース
代償分割で相続した不動産を兄弟で分けるケースでは、遺産が家だけのような場合、相続人の一人が家の所有権すべてを相続し、ほかの相続人の相続分を代償金で支払うことになります。
たとえば、2人の兄弟が評価額3,000万円の家を2分の1ずつ相続する場合だと、兄が弟に1,500万円の代償金を支払うことで、家の名義を自分(兄)だけのものにすることが可能です。
・公平に分割することができる
・相続後にもめる可能性が低い
・兄弟のどちらかが自宅に住む場合に向いている
・家の資産価値がどれくらいか評価が重要になる
・家を相続する方は代償金としてまとまった金額が必要
3-4.④「換価分割」のケース
換価分割で相続した不動産を兄弟で分けるケースでは、相続した家を売却して現金化してから兄弟で分けることになります。
相続財産である家が3,000万円で売れた場合、2人の兄弟が2分の1ずつ相続のであれば、それぞれが受け取る額は1,500万円ずつです。
・公平に分割することができる
・相続後にもめる可能性が低い
・売却する手間や諸費用がかかる
最初にも述べたように、兄弟をはじめとする複数人で家や土地などの不動産を相続した場合、特に使い道がないのであれば、売却して代金を相続人で分ける換価分割がおすすめです。
換価分割であれば公平に分けることができるため、相続不動産における兄弟間のトラブルを回避しやすくなるでしょう。
換価分割のデメリットである「売却する手間」を避けたいのであれば、仲介で売却するのではなく買取を利用するのも一つの手です。買取であれば、売却活動不要ですぐに不動産を現金化することができます。
くわしくは、「【相続×不動産売却のまとめ】相続した不動産の扱いについて基本から解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
4.相続した実家に住みたい相続人がいる場合の対処法
3つのポイント
- 相続した家に住みたい人がいる場合は、「代償分割」するのが基本となる
- 家に住み続ける相続人の資力がなく代償金を支払えない場合は、リースバックの利用を検討するという手もある
- リースバックを使って家を売却すれば、売却後も賃貸として住み続けることができる
兄弟など複数人で実家を相続した場合、全員の意向がそろわない場合もあります。
特にトラブルになりやすいのが、これまで亡くなった人と同居していた相続人が、これまでと同じように住み続けたいという理由で売却に反対するケースです。
ここでは、相続した家に住み続けたい相続人がいる場合の対処法について説明します。
4-1.「代償分割」が基本となる
兄弟で相続した実家に住みたい相続人がいる場合は、「代償分割」が基本となります。
相続した家に住みたい相続人が所有権を相続し、ほかの相続人に対して、相続分に相当するお金を代償金として支払うという方法です。
たとえば、評価額が3,000万円の実家を兄弟3人で相続し、兄が実家に住み続けたいとします。
この場合だと、兄が家の所有権を相続して、2人の弟に1,000万円ずつ支払えば公平に分割できるというわけです。
4-2.リースバックを使えば住んでいる相続人がいても売却できる
先に説明したように、相続した実家に住み続けたい兄弟がいる場合は、代償分割が基本です。
しかし、住み続ける相続人にほかの相続人に代償金が支払えるだけの資力がなければ、代償分割はできません。
そうすると、実家を売却して兄弟で換価分割するしかありませんが、住み続けたい相続人は実家を出ていくことになります。
そのような問題の解決方法としておすすめなのが、リースバックです。
リースバックを利用すれば、家を売却してまとまった売却代金を得て、そのあと、賃貸として住み続けることができます。
相続した家をリースバック会社に買い取ってもらった売却代金を相続人で分けたあとで、実家にこれまで住んでいた相続人が賃貸として住み続ければ、代償分割と換価分割の問題が一度に解決できます。
リースバックの仕組みや利用の流れについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」でわかりやすく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 相続した家を空き家のまま放置すると、「空き家条例」に抵触してさまざまな不利益を被ることがあるため注意
- 相続財産の分割方法は、次の4つ。家などの不動産しか相続財産がない場合も同じ
・現物分割(不動産そのものを分ける方法)
・共有分割(不動産を共有名義で所有する方法)
・代償分割(不動産を得る人がほかの兄弟に代償金を支払う方法)
・換価分割(不動産を売却した代金を分ける方法) - 相続した不動産が広い土地だと現物分割も可能だが、土地が狭い場合や建物がある場合には分割はむずかしい
- 共有分割は、将来、売却したり賃貸に出したりしたい場合、全員の承認を得る必要があるためトラブルになりやすい
- 兄弟だけで相続財産を分ける場合、遺言がなければ原則として兄弟の人数で平等に分割することになる
- 遺言があればその内容に沿って分割する。分割内容に不服がある場合は法定寄与分を請求することができる
- 兄弟で実家を分割する場合は、後々トラブルになりにくい代償分割か換価分割がおすすめ
- 相続した家に住み続けたい兄弟(相続人)がいる場合は、代償分割が基本となる
- 家に住んでいる相続人が代償金を支払えない場合は、リースバックを利用するという方法もある
実家をはじめとする家や土地などの不動産を兄弟で相続した場合、どうしても分割方法や分割割合でトラブルに発展しやすくなりがちです。
相続した家や土地などを兄弟(複数の相続人)で分ける方法として、現物分割、共有分割、代償分割、換価分割の4つがあります。
この中でトラブルになりにくい分け方は、不動産を売却した代金を相続人で分ける換価分割です。
しかし、家を売ってしまうと住むところがなくなってしまう兄弟(相続人)がいるなど、売却がむずかしい場合もあるでしょう。
そのような場合は、リースバックを利用するのもおすすめです。
相続した不動産の売却をどの不動産会社に頼めばよいのかわからない方やリースバックについて相談したい方は、ぜひイクラ不動産をご利用ください。
無料&秘密厳守で相続した不動産の相談ができるだけでなく、売却実績が豊富な不動産会社やリースバック会社がわかります。
さらに、わからないことがあれば宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専門スタッフにいつでも無料で相談できるため、不動産売却がはじめての方におすすめです。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。