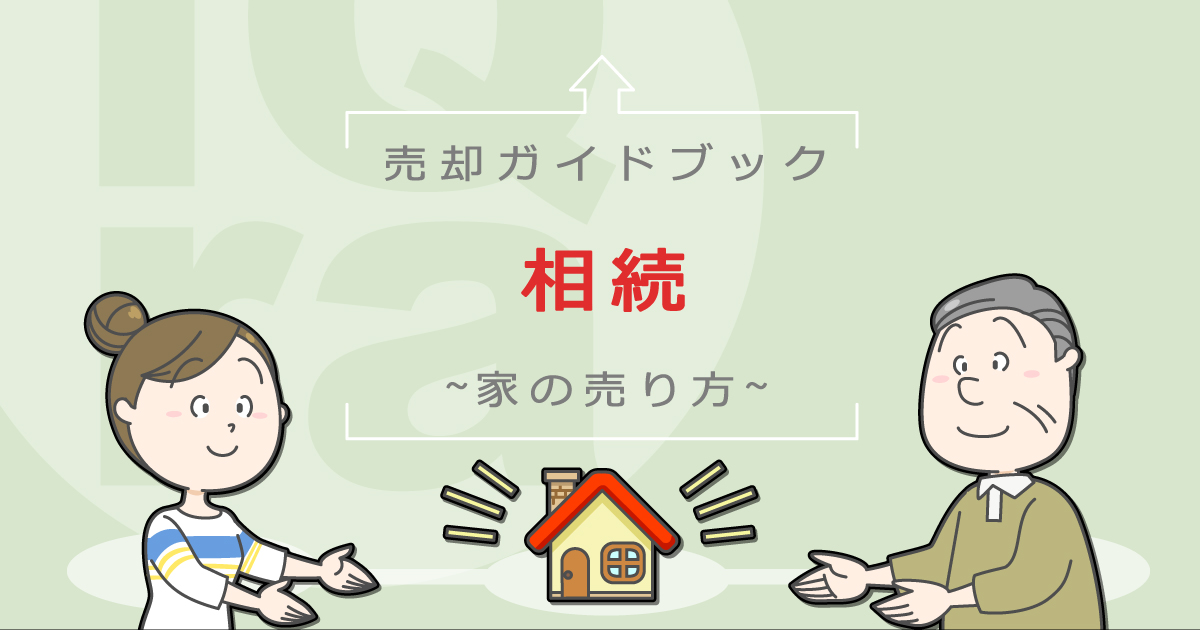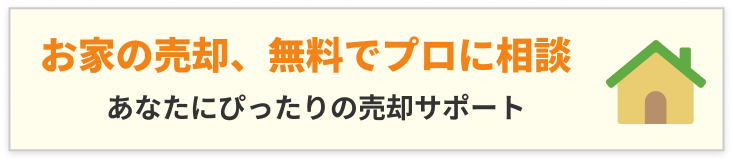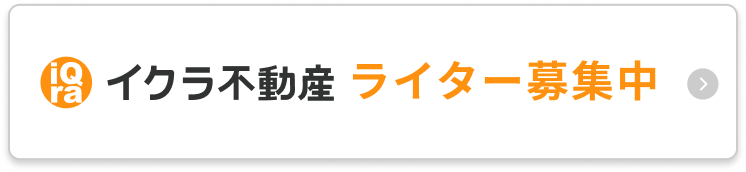相続した家が古かったり傷みがひどかったりする場合、解体を検討するケースも多いでしょう。
しかし、いざ解体するとなると、勝手に解体しても良いのか、解体するデメリットはないのか、解体費用は誰が負担するのかなど、わからないことだらけです。
こちらでは、相続した家を解体するときの注意点やメリット、デメリット、解体費用などについてわかりやすく説明します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 相続した家を解体する流れや注意点がわかる
- 相続した家を解体するリスクやデメリット、メリットなどがわかる
- 相続した家を売却できそうな額と解体費用とを調べるおすすめの方法がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 相続した家の解体を検討している人
- 相続した家を解体する流れや方法について知りたい人
- 相続した家を解体するメリットやデメリットを知りたい人
不動産売却について基本から解説
- 実家の売却完全ガイド!売却方法や手順、税金などを生前、相続後、空き家別に解説
- 相続した不動産の売却方法から流れ、手続き、相続税対策まで徹底解説!
- 実家を兄弟で相続!住んでいる人がいてもトラブルを回避してスムーズに分割する
- 家や土地などの相続不動産がいらない場合の相続放棄や処分方法をわかりやすく解説
「売却一年生」TOPに戻る
もくじ
1.相続した家を解体するときの流れ
3つのポイント
- 遺言がなく家の相続人が複数いる場合は、遺産分割協議の際に家の解体についても取り決めておくと良い
- 相続登記をしなくても建物の解体は可能だが、解体後の土地を売却するのであれば相続登記が必須となる
- 家を解体したら、解体後1ヵ月以内に滅失登記をしなければならない
まず、家の相続が発生してから解体するまでの流れについて説明します。
相続発生から解体までの大まかな流れは次のとおりです。
- 家の相続人を確定する
- 相続登記申請をする
- 解体費用を負担する人を決める
- 滅失登記申請をする
順番に、くわしく説明します。
1-1.家の相続人を確定する
遺言書があれば、その内容に従って実家の相続人が決まります。遺言書がなければ、実家を相続するのは法定相続人全員です。
誰が実家を相続するのか、どのように実家を分けるのかが決まっていない場合は、遺産分割協議を開いて決めることになります。
家の相続人が複数いる場合は、できれば遺産分割協議の際に、家の解体の同意や解体費用の負担についても取り決めておくと良いでしょう。
遺言のある相続については、「遺言書がある場合の家の相続手続きについてわかりやすく説明する」で、相続人が複数いる場合の話し合いについては、「家を相続したときの話し合いの方法についてまとめた」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-2.相続登記申請をする
家の相続人が決まれば、家の所有者を亡くなった人から相続人に変更するための相続登記申請をします。
相続登記申請をしなくても家の解体は可能ですが、家を解体したあとの土地を売却するのであれば、相続登記は必須です。
また、2024年4月から相続登記申請の義務化が開始されたため、相続した家を解体したり売却したりするかどうかにかかわらず、相続が発生してから3年以内に相続登記申請をしなければなりません。
過去に相続した不動産についても、相続申請の義務化が適用されます。相続登記申請をせずに放置していた不動産がある場合は、早めに手続きをしましょう(相続申請義務化開始から3年以内)。
相続登記について、くわしくは「相続した家の売却に必要な相続登記とは?手順と義務化についても解説」で説明しています。ぜひ読んでみてください。
1-3.解体費用を負担する人を決める
家の解体費用を誰が負担するのかについても、あらかじめ協議しておかなければなりません。
解体費用の負担人として考えられる選択肢は、次のいずれかでしょう。
- 持ち分の割合に応じて相続人で折半
- 土地の所有権を相続した人が負担
- 解体後の土地を転用する人が負担
解体費用負担の割合まで話し合って決めておけば、相続人同士でもめる可能性は低くなります。
また、解体業者から家の解体費用の見積もりを取っておけば、話し合いをスムーズに進めやすくなるでしょう。
家の解体費用については、「家の解体の相場っていくらくらい?解体前に確認しておくべきポイントも解説!」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-4.滅失登記申請をする
家を解体したら、解体後1ヵ月以内に、その家がなくなったことを法務局で登記しなければなりません。これを滅失登記といいます。
原則として、滅失登記申請をするのはその家の名義人です。よって、相続登記によって家の名義人となった相続人が行うことになります。
相続人が複数いる場合は、そのうちの1人が代表して手続きすることも可能です。その際には、相続人であることを証明するため、遺産分割協議書相続人のや戸籍謄本などを提出します。
滅失登記申請の流れは、次のとおりです。
- 建物滅失登記申請書を法務局からもらってくる
- 解体業者から建物とりこわし証明書と印鑑証明書をもらう
- 建物のあった場所の住宅地図の印刷を準備する
- 必要書類を持って法務局へ提出
相続した家に抵当権が設定されている場合は、解体する前に金融機関などの抵当権者の承諾が必要になります。
抵当権が付いている不動産の相続については、「借金で抵当権のついている家を遺産相続した場合の対処方法」で説明しているので、参考にしてみてください。
2.相続した家を解体するリスクとデメリット
3つのポイント
- 家を解体することで、固定資産税の優遇措置が受けられなくなるリスクがある
- 家の解体費用を上乗せした額で、更地にした土地を売却できるとは限らない
- 再建築不可物件の場合、一旦、家を解体すると新たな家を建てられなくなる
相続した家を解体するリスクやデメリットとして、次のようなものがあげられます。
- 固定資産税が跳ね上がることがある
- 解体費用を土地の売却額に上乗せできるとは限らない
- 再建築不可の物件だと家が建てられなくなる
2-1.固定資産税が跳ね上がることがある
家が建っている土地は、固定資産税の評価額が最大で6分の1になる優遇措置が取られています。
この優遇措置は更地になってしまえば適用外となるため、建物を解体することで、今の固定資産税が大幅に増えることになりかねないからです。
売却したり新しい家を建てたりする予定がない場合は、とりあえず解体するのは避けるほうが良いでしょう。
2-2.解体費用を土地の売却額に上乗せできるとは限らない
相続した家の売却を検討する際に、「解体して更地にする方が売却しやすそう」と考える人も多いです。
しかし、家を解体したからといって、必ずしも解体費用を土地の金額に上乗せできるとは限りません。
建物の解体費用のおおよその目安額は、次の表のようになっています。
| 建物の構造 | 一坪あたりの解体費用 |
|---|---|
| 木造 | 4~5万円/坪 |
| 鉄骨造 | 6~7万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 6~8万円/坪 |
つまり、30坪の木造一戸建てを解体するのであれば、150万円前後の解体費用が必要になるということです。
逆に古家がある状態でも「古家付きの土地」として売れることがあるため、解体費用と売却額との兼ね合いを考えれば、そのまま売却した方が得になるケースもあります。
売却活動の途中で「やはり解体しないと需要がなさそうだ」との判断すれば、そこで更地にすることも可能です。
相続した家の売却を検討しているのであれば、まずはそのままの状態で、不動産会社に売却相談することをおすすめします。
更地にしてから売却するかどうかについては、「空き家や古い家付きの土地は更地にして売却すべき?判断基準をご紹介」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
2-3.再建築不可の物件だと家が建てられなくなる
相続した家が古いと、現在の建築基準法で建てられておらず、再建築不可物件の場合があります。
再建築不可物件とは、現在の建築基準法における接道義務などを満たしていないため、建物を建てることができない土地のことです。
もし再建築不可物件であれば、一旦、家を取り壊してしまうと、新たに家を建てることができません。
再建築不可かどうかは、不動産会社に調べてもらうことができます。売却を考えているのであれば、相談してみると良いでしょう。
再建築不可物件については、「再建築不可物件は売却できる?査定相場価格や再建築を可能にする方法を解説」で説明しているので、ぜひ一読してみてください。
3.相続した家を解体するメリット
3つのポイント
- 相続した家(建物)を管理するための費用や手間がかからなくなる
- 物件によっては、更地にすることで売却しやすくなることがある
- 旧耐震基準で建てられた家の場合、解体することで「相続空き家の3,000万円控除」の適用が受けやすくなる
相続した家を解体するメリットとして、次のようなものがあげられます。
- 家の管理にかかる費用や手間が不要になる
- 更地のほうが売れやすくなることがある
- 「相続空き家の3,000万円控除」を適用しやすくなる
3-1.家の管理にかかる費用や手間が不要になる
相続した家を利用しないからといって、何もせずに空き家のまま放置しておくことはできません。相続した以上は、きちんと管理が必要です。
近くにある場合だとそれほど管理に手間はかからないかもしれませんが、遠方にある場合だと費用も手間もかかります。月々の費用はそれほどではなくても、何年も続くとかなりの額になるでしょう。
建物部分を解体して更地にすれば、少なくとも建物の管理は不要になります。
空き家の管理については、「空き家管理サービスの比較と選び方を紹介!空き家は売却がおすすめの理由も解説」でくわしく説明していしているので、ぜひ読んでみてください。
3-2.更地のほうが売れやすくなることがある
相続した家の場所や立地によっては、家を解体して更地にするほうが売れやすくなる場合があります。
また、駐車場などの事業用の土地を探している人や新築用の土地を探している人がいる場合は、更地しておくほうが売れやすいでしょう。
しかし、先にも述べたように勝手な判断で解体せず、必ず不動産会社に相談をして、更地にするほうが売れやすいことを確認してから解体することが大切です。
3-3.「相続空き家の3,000万円控除」を適用しやすくなる
不動産を売却した際の利益には、所得税と住民税が合わせた譲渡所得税が課税されます。
しかし、相続した空き家を相続した年から3年後の年末までに売却するなどの条件を満たせば、「相続空き家の3,000万円控除」の適用で、売却益から最大3,000万円の控除が可能です。
ただし、この控除は「昭和56年5月31日以前に建築された戸建て」を相続した場合で、「その家を耐震補強して売却した場合」か「その家を解体して更地にして売却した場合」にしか適用されません。
つまり、相続した家が、昭和56年5月31日以前に建築された戸建てで、かつ家を取得した金額より高い金額で売れる場合であれば、家を解体してから売却した方が結果として得になる可能性があると言えます。
ただし、節税効果よりも解体費用のほうが高くつく場合もあるため、事前に売却できそうな額と解体費用とをしっかりと調べておくことが大切です。
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
4.売却できそうな額と解体費用とを調べるには?
3つのポイント
- 相続した家の解体を検討する場合は、そのまま売却したらいくらになるかと解体費用とを調べておくことが大切
- 相続した家のエリアで売却に強い不動産会社を探したい場合は、イクラ不動産の利用がおすすめ
- 最安値の解体業者を探したい場合は、クラッソーネで見積もりを取るのがおすすめ
相続した家や土地がいくらで売れるかを調べたい場合は、無料&秘密厳守で利用できる「イクラ不動産」でご相談ください。
イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、豊富な売却実績から簡単に相場価格がわかるため、売却益がどれぐらい出るのかおおよその額を把握することが可能です。
さらに、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフに相場価格を調べてもらったり、売却時のアドバイスをもらったりできます。
また、最安値の解体工事会社を探したい場合は、国内最大級の解体工事一括見積りサイト「クラッソーネ」がおすすめです。
解体工事の見積もり依頼から比較、工事依頼まで簡単にご利用いただけます。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 相続した家を解体する流れは、次のとおり
・家の相続人を確定する
・相続登記申請をする
・解体費用を負担する人を決める
・滅失登記申請をする - 相続登記をしなくても家の解体は可能だが、相続した不動産を売却する際は相続登記申請は必須
- 相続登記申請が義務化されたため、売却する予定がなくても相続登記申請はしなければならない
- 相続した家を解体するデメリットは、次のとおり
・土地の固定資産税が跳ね上がる場合がある
・土地の売却費用に解体費用を上乗せできるとは限らない
・再建築不可物件の場合、解体すると新たに家を建てられない - 相続した家を解体するメリットとして、次のようなものがある
・建物の管理にかかる費用や手間が不要になる
・更地にするほうが売れやすくなる場合もある
・「相続空き家の3,000万円控除」が適用しやすくなることがある - 家を解体する前に、いくらで売れるのか、解体費用がいくらかかるのかを調べておくことが大切
相続した古い家は、解体して更地にするほうが売れやすくなる場合があるのも事実です。
しかし、無計画に家を解体することで、土地の固定資産税が高くなったり売却額で解体費用を回収できなかったりする恐れがあります。
また、再建築不可物件であれば、一旦、家を取り壊してしまうと、新しい家を建てることができません。
相続した家を解体して更地にすることを検討しているのであれば、相続人や固定資産税などの兼ね合いを考慮しなければならないため、まずは不動産会社に相談するのがおすすめです。
いきなり不動産会社へ相談することに抵抗がある人は、まずは、無料&秘密厳守で利用できる「イクラ不動産」でぜひご相談ください。
イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、豊富な売却実績から簡単に相場価格がわかるため、どれぐらいで売れそうかを調べることができます。
また、実際に不動産会社に相談したいとなった場合は、あなたにピッタリ合った売却に強い不動産会社を選べるだけでなく、わからないことがあれば宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので安心です。信頼できる不動産会社を紹介してもらうこともできます。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。