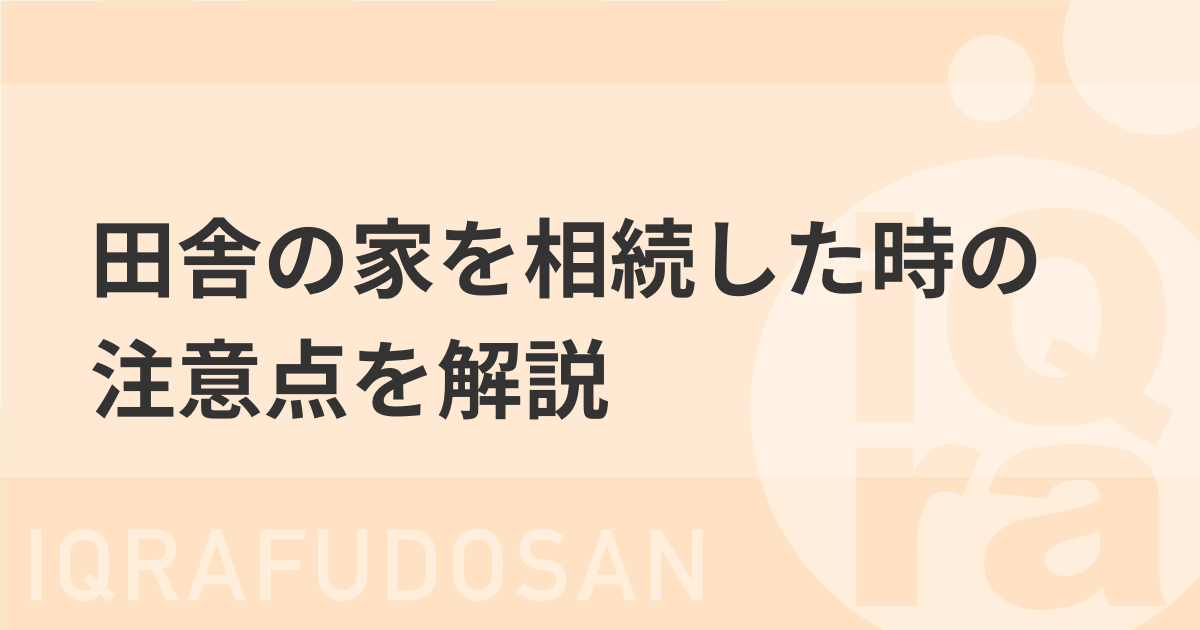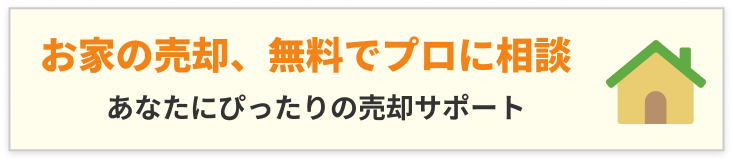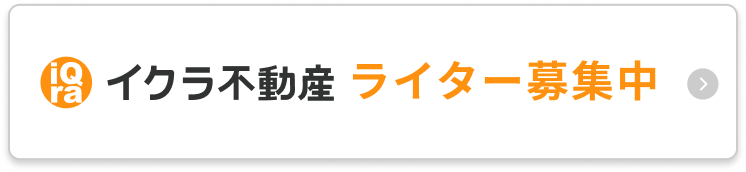田舎の家を相続したときに、「どうすればいいのかわからない」という悩みを抱える方は少なくありません。
特に、遠方に住んでいる場合や今後住む予定がない場合は、適切な対応を取らないと金銭的負担や管理の手間が増え、後々大きな問題になる可能性があります。
こちらでは、使う予定のない田舎の家を相続したときの注意点をわかりやすく説明します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 田舎の家を相続したときに、まず考えるべきポイントがわかる
- 相続した田舎の家をどうすべきか、判断基準がわかる
- 田舎の家を相続したときの疑問点とその回答がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 田舎の家を相続して、どうすれば良いのかわからない人
- 相続した田舎の家を放置したままにしている人
- 相続した田舎の家を売却する方が良いのか放棄すべきなのか判断基準を知りたい人
もくじ
1.田舎の家を相続…どうすればいい?まず考えるべきポイントを解説
田舎の家を相続したものの、どうすれば良いかわからないときに、まず考えるべきポイントについて解説します。
1-1.相続した田舎の家を放置するのは危険!
相続した田舎の家がいらないからといって、そのまま放置するのは危険です。
「住まないから」「すぐに売れなさそうだから」といって放置しておくと、次のような思わぬリスクや負担につながることがあります。
- 固定資産税や維持費がかかる
- 老朽化による倒壊や近隣トラブルのリスク
- 不法投棄や不法占拠などの犯罪につながる
たとえ住んでいなくても、 固定資産税の支払い義務は発生します。そして、適切な状態を保つには、管理費や維持費が必要です。
また、台風や地震で損壊して近隣住民に被害を与えた場合は、所有者責任を問われ、損害賠償を請求されるケースもあります。
さらに、害虫や害獣問題につながるだけでなく、誰も出入りしない家は不審者に狙われやすく、不法侵入や不法占拠、放火といった犯罪を引き起こすかもしれません。
1-2.家族や親族と話し合い、方向性を決めることが大切
家族や親族といった複数の相続人がいる場合は、まずしっかりと話し合いをしたうえで、どうするかの方向性を決めましょう。
決まらないまま時間が経つと管理責任が曖昧になり、結局、誰も何もしないまま放置されることになりかねません。
相続人同士の話し合いでは、次のようなことを決めておきましょう。
- 誰が相続するのか?(誰が名義を持つのか)
- 共有名義にするのか?
- 共有名義にした場合、管理や維持の負担をどうするか?
- 売却するのか活用するのか?
2024年4月より相続登記が義務化されました。したがって、売却してもしなくても、不動産を相続したときは、必ず相続登記をしなければなりません。
誰が相続登記をするのかも含めて、相続した田舎の家をどうするのかを話し合っておきましょう。
相続登記については、「相続した家の売却に必要な相続登記とは?手順と義務化についても解説」をぜひ読んでみてください。
1-3.「売る・活用する・放棄する」3つの選択肢を整理しよう
相続した田舎の家をどうするかの選択肢として、「売る」「活用する」「相続放棄する」の3つがあります。
それぞれの特徴を理解し、自分にとって最適な方法を選びましょう。
① 売却する|「住まないなら売る」のが最も合理的
今後住む予定がなく、管理の負担を減らしたい場合は、売却するのが最も合理的な選択肢です。
売却することで、固定資産税や維持費の支払いが不要になるだけでなく、まとまった現金を得られます。
ただし、田舎の家は売れるまでに時間がかかることがあるため、早めに査定を依頼し、市場価値を確認することが大切です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 固定資産税や管理費が不要になる | 田舎の物件は売れにくいケースがある |
| 現金化できる(相続人で分けやすい) | 売却までに時間がかかることがある |
相続した家の売却については、「相続した不動産を売却する流れや手続き、やるべきことをわかりやすく解説」でくわしく説明しています。
② 活用する|「売るのは迷う…」なら貸し出しや別用途の検討を
「すぐに売るのは迷う」「できれば資産として活用したい」という場合は、貸し出しや別の用途で活用するという方法もあります。
たとえば、賃貸にすれば家賃収入を得られますし、駐車場や倉庫として貸し出すことも可能です。
ただし、管理の手間がかかるほか、借り手が見つかるかどうかは立地や需要に左右されるため、事前にしっかりとした市場調査が必要になります。
| 活用方法 | 特徴 |
|---|---|
| 賃貸として貸し出す | 家賃収入を得られるが、借り手が見つからないリスクあり |
| 駐車場や倉庫として利用 | 維持コストが低いが、収益性はエリア次第 |
| セカンドハウスとして利用 | 活用するなら定期的な管理が必要 |
活用を考える場合は、自治体の「空き家バンク」に登録することで、移住希望者や地域の活性化プロジェクトに活用される可能性もあります。
相続した家の活用については、「相続した家の3つの活用方法とメリット・デメリットについてまとめた」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
③ 相続放棄する|「維持も売却もむずかしい」なら手放す選択肢
売るのもむずかしく、また管理もできない場合は、相続放棄して所有権を手放すという方法もあります。
相続放棄をすれば固定資産税や維持費の負担から解放されますが、家だけではなくほかの相続財産も放棄することになります。
また、次の相続順位の親族(兄弟や甥姪)に負担が移る可能性がある点にも注意が必要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 固定資産税や維持費の負担がなくなる | 家だけを放棄することはできない |
| 相続人間のトラブルを回避できる | 次の相続順位の親族に負担が移る可能性がある |
相続放棄には期限(相続発生後3ヵ月以内)があるため、早めに判断し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
相続放棄については、「家や土地などの相続不動産がいらない場合の相続放棄や処分方法をわかりやすく解説」でくわしく説明しているので、ぜひ一読してみてください。
2.相続した田舎の家をどうする?判断基準を解説
相続した田舎の家は、「売る」「活用する」「相続放棄する」 という3つの選択肢がありますが、どれを選ぶべきか迷う人も多いでしょう。
決断のポイントは、自分の状況に合った方法を選ぶことです。
ここでは、どの方法を選ぶべきか、判断基準をくわしく解説します。
2-1. 「売る」のがベストなケースとは?
住む予定がなく、管理がむずかしい場合は、売却が最も合理的な選択です。
特に、次のようなケースでは、早めに売るほうがベストな判断となります。
| 状況 | 売却すべき理由 |
|---|---|
| 遠方に住んでいて管理できない | 長期的に管理するのが難しく、放置するとリスクが増大する |
| 固定資産税・維持費が負担になっている | 住んでいなくても税金や修繕費がかかり、年々負担が増える |
| 市場価値があるうちに売りたい | 需要があるうちに売却すれば、より良い価格で売れる可能性が高い |
田舎の家は買い手がつくまでに時間がかかることもあるため、「売ると決めたら早めに行動する」ことが重要です。
不動産会社に査定を依頼し、市場価格を知ることで、「本当に売れるのか?」を判断しやすくなります。
2-2. 「活用する」のが適しているケースとは?
「売るのは迷う」「資産として活かしたい」という場合は、賃貸やセカンドハウスとして活用する方法も選択肢になります。
しかし、活用には管理の手間が伴うため、次のようなケースに該当するかを確認しましょう。
| 状況 | 活用方法 |
|---|---|
| 定期的に帰省する | セカンドハウスとして利用し、将来的に住む可能性を残せる |
| 親族が住む予定がある | 親族に貸し出し、維持管理の負担を減らすことができる |
| 賃貸に出して収益を得たい | 家賃収入を得ることで、維持費をカバーできる可能性がある |
「貸す」と「売る」どちらが得かは、「維持費・管理の手間・収益性」を考えると判断しやすくなります。
| 項目 | 貸す(賃貸・活用) | 売る(売却) |
|---|---|---|
| 収益性 | 家賃収入を得られる | 売却時にまとまった資金が入る |
| 管理の手間 | 定期的な管理が必要(修繕・入居者対応など) | 売却後は管理不要 |
| 長期的なメリット | 資産として残る | 早めに売れば高値で売れる可能性 |
2-3. 「相続放棄」を検討すべきケースとは?
「売ることも活用することも難しい」「維持管理もできない」場合は、相続放棄を検討するという選択肢もあります。
しかし、相続放棄にはルールや注意点があるため、事前にしっかり理解しておくことが重要です。
| 状況 | 相続放棄すべき理由 |
|---|---|
| 売ることも活用することも難しい | 田舎すぎて買い手がつかず、活用の選択肢もない |
| 管理や維持費の負担を避けたい | 固定資産税・修繕費が高額で、相続後の負担が大きい |
| 相続人間でトラブルを避けたい | 不動産の分割が難しく、相続争いのリスクがある |
相続放棄には、いくつかの制約があるため、以下のポイントに注意しましょう。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 「家だけ」を相続放棄することはできない | ほかの相続財産(預貯金など)も一括で放棄する必要がある |
| 相続権が次の順位の親族に移る | 兄弟や甥姪に負担が移り、トラブルの原因になる可能性あり |
| 放棄しても一時的に管理責任が発生することも | すぐに完全に手放せるわけではなく、一定期間は管理義務が生じる |
3.田舎の家を相続したときのQ&A「売りたくても売れない!」そんなときの対処法
最後に、田舎の家を相続したときによくある疑問点や質問について、Q&A形式でわかりやすく説明します。
Q.なかなか売れないときはどうすればいい?
A.高く売ろうと思わない
売れない原因は多くの場合、価格の問題だと言えます。
田舎の家の売却は、極論で言ってしまえば、無料でもいいと思うくらいの気持ちが必要です。
査定価格が500万円だったから、500万円で売れるだろうと考えるかもしれません。しかし、そもそも査定価格とは、不動産会社が周辺相場を参考に算出する「予想金額」なので、必ずしもその価格で売れるわけではないことを理解しておきましょう。
売れない期間が続くのは、「その金額では欲しい人がいない」ということであり、妥当な金額ではない証拠です。
査定価格を基準にするのではなく、問い合わせ数などをもとに、買い手のニーズを考えて価格を引き下げていくことを考えてみてください。
Q.どうしても売れない場合の対策は?
A.買取の利用を検討してみる
なかなか売れない家は、一般の人ではなく不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」の利用を検討してみましょう。
一般消費者向けに売却する「仲介」の方が高く売ることができますが、なかなか売れない田舎の家は、待っていてもいつまでも売れない可能性があります。
価格面で妥協することができれば、早く確実に売却することができるため、買取の利用を検討してみるのがおすすめです。
買取については、「不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説」で説明してますので、ぜひ読んでみてください。
Q.田舎の家を売るのは大変では?
A.持ち回り契約や代理人契約を活用すれば、手間を大幅に減らせる
田舎の家を売るとなると、「何度も現地に行かないといけないのでは?」 と不安に思う方が多いです。
しかし、実際には 「持ち回り契約」や「代理人契約」 を活用すれば、行き来の回数を最小限に抑えられます。
- 持ち回り契約:売主・買主が別々に契約書を確認・署名する方式。対面での契約が不要。
- 代理人契約:親族や専門家に売却手続きを依頼できるため、売主本人の負担が軽減。
また、売却物件がある地域の不動産会社に依頼すれば、地元の市場に詳しいプロが対応してくれるため、スムーズに進められます。
代理人契約については、「所有者以外が家などの不動産売却を代理でする方法と委任する際の注意点」で説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
Q.いらない田舎の家だけを相続放棄できる?
A.不動産だけを相続放棄することはできない
相続放棄をする場合、不動産だけを選んで放棄することはできず、すべての相続財産を手放さなければなりません。
また、相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人(兄弟や甥姪など)に移るため、親族間でのトラブルにつながる可能性もあります。
どうしても相続できない場合は、自治体への寄付や売却、無償譲渡 など、別の選択肢を検討してみても良いでしょう。
借金があって家を相続放棄した場合でも、家の管理義務は残ります。くわしくは「借金のため家を相続放棄!それでも残る家の管理責任と免れるための方法」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 田舎の家を相続した場合、次のような理由から放置しないようにすることが大事
・固定資産税や維持費がかかる
・老朽化による倒壊や近隣トラブルのリスク
・不法投棄や不法占拠などの犯罪につながる - 相続した田舎の家は、「売却する」「活用する」「放棄する」のいずれかになる
- 住む人がおらず、将来、利用予定もない場合は、売却するのがおすすめ
- 「売るのは迷う」「資産を残したい」という場合は、賃貸やセカンドハウスとして活用する
- 売却もできず活用も大変だという場合は、相続放棄するという選択肢もある
- 相続放棄をする場合は、不動産だけでなくすべての相続財産を放棄することになる点に注意
- 持ち回り契約や代理人契約を利用すれば、田舎の家の売却にかかる負担を減らすことができる
- なかなか売れない場合は、売出価格を見直したり買取の利用を検討したりする
いらない田舎の家を相続した場合は、空き家のまま放置しておくリスクや維持費用のことを踏まえると、思いきって売却してしまうのがおすすめです。
売却するのであれば、高く売ろうと考えず、仲介で売れない場合は買取の利用を検討してみても良いでしょう。
いずれの場合にせよ、まずはいくらぐらいで売れそうか、相場価格を知っておくことが大切です。
相続した田舎の家の相場価格を調べたい場合は、無料&秘密厳守で利用できるイクラ不動産をぜひご利用ください。
イクラ独自の価格シミュレーターを使えば、簡単に素早く相場価格を調べたり、売却したい家がある地元の不動産会社を探したりすることが可能です。
さらに、わからないことがあれば宅建士の資格を持つイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので、安心して売却を進めることができます。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。