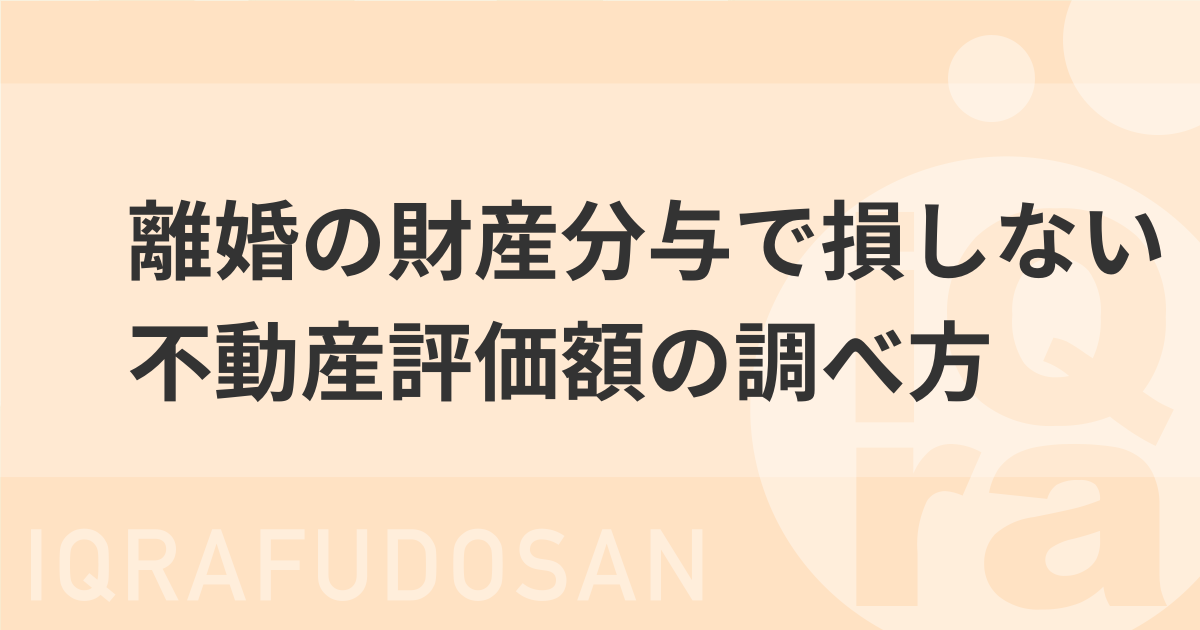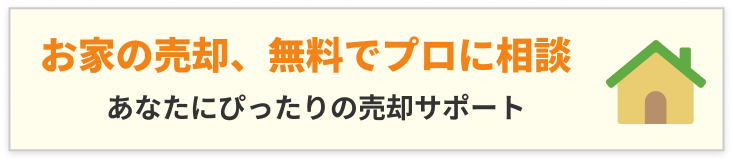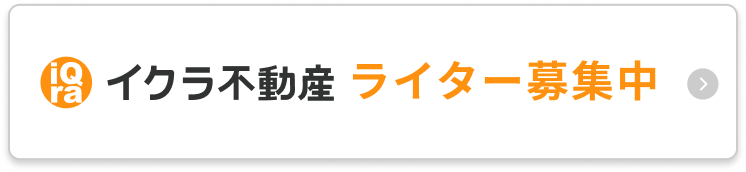不動産の売却や離婚での財産分与の際、多くの人が直面する課題が「家やマンションの正確な価値をどう把握するか?」という問題です。
こちらは、実際に「イクラ不動産」に寄せられたご相談の一例になります。
【実際の相談事例】
💬 離婚の財産分与で、夫は家の価値を2,500万円と言っていますが本当でしょうか?
もし実際は3,500万円だったら、私は500万円も損することになるのでは…正確な評価額を知る方法を教えてほしいです。
この相談者の懸念は決して過度なものではありません。
離婚時の不動産の財産分与では、「評価額」の正確な把握が重要な要素となり、適切な調査を行わないと数百万円の差が生じるケースがあるからです。
本記事では、不動産評価額の調べ方を解説し、離婚の財産分与で適切な評価を行うためのポイントを、法的根拠と実際の調査方法に基づいて解説します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 離婚で家を財産分与する際に不動産評価額を事前に調べておく必要がある法的根拠と実務上の理由がわかる
- 不動産評価額を調べる4つの方法(実勢価格・公示地価・路線価・固定資産税評価額)の特徴と離婚時の適用場面がわかる
- 離婚で家の評価額について争いになった場合の解決手順と対処法がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 離婚で家の財産分与を検討している人
- 財産分与における不動産評価額の調査方法を知りたい人
- 離婚時の家の評価額で争いになった場合の対処法を知りたい人
1.離婚時に不動産評価額が必要な理由-財産分与の法的根拠と実務
離婚の際、財産分与で争いになるケースは決して珍しくありません。
特に、家やマンションといった不動産は、高額であるうえ定価が存在しないため、財産分与において慎重な対応が求められる資産だといえます。
まず、離婚する際に家やマンションの評価額がなぜ必要なのかを法的根拠と実務上の理由を踏まえて説明するとともに、財産分与の基本をおさらいしておきましょう。
1-1.財産分与の法的根拠と基本ルール
離婚時の財産分与は、民法第768条に規定されています。同条では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされており、これが財産分与請求権の法的根拠となります。
離婚の際、夫婦が結婚生活の中で築いた財産は「共有財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分け合うことが基本的な考え方です(清算的財産分与)。
この共有財産には、預貯金や株式、保険といった金融資産に加えて、家やマンションなどの不動産も含まれます。
一方で、結婚前から所有していた財産や、相続や贈与によってそれぞれが取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外となる場合が一般的です。
ただし、結婚後に家の増築やリフォームを行っていたり、夫婦の共有資金からローンを返済していたりすると、特有財産と共有財産との切り分けが複雑になります。
結婚前に購入した家やマンションが離婚の財産分与でどうなるのかについては、「結婚前に買った家は離婚時の財産分与の対象?相手の家をもらうことはできる?」で、親から頭金を出してもらった場合の財産分与については「離婚の際、家の頭金を親や結婚前の貯金から出した場合の財産分与について解説」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-2.財産分与で不動産が重要な位置を占める理由
家やマンションなどの不動産は、一般的に高額な資産である場合が多いものです。預貯金や株式などに比べて金額が大きくなりやすく、財産分与において大きなウエイトを占めることになります。
そのため、不動産をどのように扱うかは離婚時の財産分与において重要な検討事項になります。
また、不動産には住宅ローンや名義の問題が関わることが多くあります。ローンの残債をどう処理するのか、名義が夫婦どちらになっているのか、連帯保証人がついているかなど、現金や預貯金のように単純に「半分ずつ」では解決しない複雑さがあることが多いのが実情です。
結果として財産分与に時間や労力がかかり、争いも生じやすくなる傾向があります。
離婚の財産分与で家やマンションの名義がどうなるかについては、「離婚後の家は、夫婦「どっちのもの」になるの?名義は関係ある?」で、住宅ローンがどうなるかについては「離婚時の住宅ローン対策!ローンの借り換え、名義変更について解説」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-3.不動産評価額を事前に把握することの重要性
不動産を財産分与の対象とするうえで、まずは家の「評価額」を正確に把握することが重要です。
適切な評価額の調査を行わないと、次のような問題が生じる可能性があります。
1-3-1.不公平な財産分与になってしまう
評価額とは「その家やマンションにどの程度の価値があるか」を金額で表したものです。そのため、家の評価額によって財産分与の内容が変わることになります。
たとえば、夫婦の財産として「家」と「3,000万円の預貯金」があるケースで考えてみましょう。
【家と「3,000万円の預貯金」がある財産分与の例】
家の評価額が3,000万円の場合
3,000万円+3,000万円=6,000万円
→夫婦1人の取得分は3,000万円
家の評価額が4,000万円の場合
3,000万円+4,000万円=7,000万円
→夫婦1人の取得分は3,500万円
このように、家の評価額と3,000万円の合計を夫婦が2分の1ずつにする場合だと、家の評価額がいくらになるかによって、それぞれが取得できる額が変わってきます。
特に、家をどちらかが取得する代わりに相手に代償金を支払うケース(代償分割)では、家の評価額が高くなると代償金の金額が高額になるので、家を取得する側への影響が大きく、代償金をもらう側には有利になる可能性があります。
結果として、一方が不利益を被ったり、後から「納得できない」という問題が生じたりするケースがあります。
💡 評価額の違いが財産分与に与える影響
上記の例のように、評価額の違いで500万円の差が生まれる可能性があります。離婚協議前に適切な評価額を把握しておくことで、合理的な財産分与の実現につながります。
1-3-2.住宅ローン残債との関係を把握できない
評価額を把握していないと、売却した際にローンが完済できるのかどうかの判断ができません。
ローン残債が評価額を上回る場合(オーバーローン)は、財産分与どころか債務が残ってしまうことがあります。
オーバーローンについては、こちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
1-3-3.売却プランを立てられない
適切な評価額を把握して初めて、どのくらいの期間でどの程度の金額での売却が見込めるのか、具体的な売却計画を立てることができます。
評価額が不明なままでは、不動産会社への査定依頼や売却活動の優先度も決めにくいでしょう。
2.不動産評価額を離婚時に調べる方法
⚠️ 評価額調査の適切なタイミング
- 離婚協議が始まる前に評価額を把握しておくことで、協議を適切に進められる
- 相手が提示する金額の妥当性を客観的に判断できる
- 代償金の協議で適切な根拠を示すことができる
財産分与する際に用いられる家の評価額の調査方法には、次の4種類があります。
- 実勢価格(じっせいかかく)を調べる
- 公示地価(こうじちか)を調べる
- 路線価(ろせんか)を調べる
- 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)を調べる
ただし、相手が代償金を支払うケースなどでは、家の評価額を低く見積もるために路線価や固定資産税評価額による評価を主張してくることがあるため注意が必要です。
ここでは、それぞれの評価額の調査方法を詳しく説明します。
2-1.① 実勢価格を調べる
実勢価格とは、実際に不動産の市場で取引されている金額で、最も一般的に利用されているものです。
離婚で家やマンションの評価額を調べる場合は、実勢価格が最も適していると考えられます。
💡 離婚時の実勢価格の適用場面
- 売却を前提とした財産分与:離婚後に家を売却して現金で分割する場合
- 代償分割での代償金算定:一方が家を取得し、相手に代償金を支払う場合
- 調停・審判での客観的評価:裁判所が判断する際の重要な参考資料として
- 協議での説得材料:相手が提示する金額の妥当性を検証する場合
不動産の実勢価格を調べる方法には、次の3つがあります。
2-1-1.過去の類似の取引事例を調べる
まず、自分で自宅と類似の取引事例を調べてみる方法(取引事例比較法)です。近隣で同じような条件の家が最近売れているかどうかを調べれば、その金額と同程度の金額で売れることが想定できます。
取引事例は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」や不動産流通機構の「レインズマーケットインフォメーション」で調べることができます。
ただし、自分で取引事例を調べるには限界があり、また、マンションや一戸建て、土地はそれぞれ査定方法が異なります。
そのような場合に活用できるのが、イクラ不動産です。イクラ不動産を利用すれば、無料&秘密厳守で家やマンションの相場価格を知ることができます。
自分で相場価格を調べる方法については、「不動産の相場価格とは?自分でネットで調べる方法をわかりやすく解説!」でも詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
2-1-2.不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する
不動産鑑定士に依頼をして、家やマンションの評価額を算出してもらう方法もあります。
鑑定評価を行うことは不動産鑑定士の独占業務です。
【不動産鑑定士の業務の一例】
不動産鑑定士に依頼すれば、正確な不動産評価額を算出してもらうことができますが、費用がかかることが課題です。
鑑定の費用は不動産や鑑定の目的によって大きく異なりますが、数十万円かかります。そのため、鑑定が必要となるのは、オフィスや大規模な開発を要する土地などを売買するときが多いです。
このような場合は、最低でも数億円の取引になります。お金を借り入れて売買することが多く、貸す銀行としても不動産としての正確な価値がいくらなのか評価(担保)しておく必要があるからです。
離婚の財産分与では、調停や審判で証拠能力のある評価が必要な場合に不動産鑑定士への依頼が検討されます。
ただし、高額な費用がかかるため、まずは他の方法で評価額を把握し、どうしても合意に至らない場合の最終手段として位置づけられることが多いです。
査定と鑑定の違いについては、「土地の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
2-1-3.不動産会社に査定を依頼する
不動産会社に依頼をすれば、無料で査定してもらうことができます。
不動産会社による査定が無料である理由は、鑑定士資格を持っていない不動産会社が査定価格に費用を請求することは法律違反になるからです。
ただし、不動産会社は、売却(仲介)を前提としていない価格査定は基本的に行いません。なぜなら、不動産取引が成立した際に、不動産会社が成功報酬として受け取る仲介手数料に査定にかかる費用も含まれているからです。
したがって、不動産会社に査定依頼すると、売却するかどうか決まっていなくても、いつ売却予定かを聞かれることになります。離婚で家やマンションの売却を検討しているのであれば、不動産会社に査定を依頼すると良いでしょう。
イクラ不動産なら、査定価格を知りたいだけの場合でも実勢価格を調べることができるので、まだ売却するかどうか決まっていない段階での査定に適しています。
さらに、離婚で家を売却することになった場合は、離婚での家やマンションの売却に強い不動産会社をランキング形式で選ぶことができます。
2-2.② 公示地価を調べる
公示地価とは、毎年、国土交通省が主体となって調査している、全国の基準地点における地価です。
地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示します。3月中旬ごろに、全国の主要な新聞紙面で公表されるので、目にしたことがある人も多いでしょう。
実勢価格を参考にして、不動産鑑定士による鑑定や調査などによって国が決定しており、土地を取引する際の指標とされています。
公示地価は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べることができます。
💡 離婚時の公示地価の適用場面
- 実勢価格データが不足する地域:取引事例が少ない地方や特殊な立地での評価
- 公的な価格指標として:調停や審判で裁判所が参考にする客観的な基準
- 中立的な評価基準が必要な場合:当事者双方が合意しやすい公的な価格
- 概算評価の基準として:詳細な査定前の大まかな価値把握
2-3.③ 路線価を調べる
路線価とは、土地の相続税や贈与税を計算するときに使われる評価額です。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」とがありますが、単に「路線価」とする場合は「相続税路線価」を指します。
路線価は、公示地価の8割程度に設定されています。そのため、路線価を1.25倍すればおよその公示地価がわかります。
路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
⚠️ 離婚時の路線価の適用場面と注意点
- 相手方が低い評価を主張する場合:代償金を低く抑えたい側が路線価での評価を主張することが多い
- 税務上の評価と混同される場合:相続税評価との違いを理解せずに使用されるケース
- 簡易的な概算として:初期段階での大まかな価値把握(ただし実勢価格とは大きく乖離)
- 注意:離婚の財産分与では実勢価格の8割程度の評価となるため、適正な分与には適さない場合が多い
2-4.④ 固定資産税評価額を調べる
固定資産税評価額は、固定資産税や建物の相続税と贈与税を計算するときに使われる評価額です。
市町村が3年に1回改定して決定しており、公示地価の7割程度の金額になります。つまり、固定資産税評価額を1.43倍すれば、おおよその公示地価がわかります。
固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税の納税通知書や、市町村の固定資産課税台帳で確認することができます。
⚠️ 離婚時の固定資産税評価額の適用場面と注意点
- 手軽に確認できる評価として:固定資産税納税通知書から簡単に把握可能
- 相手方が低い評価を主張する場合:路線価と同様、低い代償金を主張する際に使用されることが多い
- 初期段階での参考値として:協議開始前の大まかな価値把握
- 重要な注意点:実勢価格の約7割の評価となるため、実際の財産分与では適正な評価額とは言えない
- 建物部分の評価:土地だけでなく建物の評価も含まれているが、実勢価格とは大きく乖離する場合が多い
📝 離婚時の評価方法選択のポイント
- 最優先:実勢価格 – 売却や代償分割を検討する場合
- 補完的:公示地価 – 実勢価格データが不足する場合や公的基準が必要な場合
- 注意が必要:路線価・固定資産税評価額 – 実勢価格より大幅に低いため、相手方の主張には慎重に対応
3.離婚の際、不動産評価額で問題が発生した場合の対処法
最後に、離婚で財産分与をする際に、家の評価額について問題が発生した場合の対処法について説明します。
3-1.基本的には話し合いで解決する
離婚時の家の評価額について問題が発生した場合、基本的には夫婦で話し合って解決することになります。第三者に入ってもらうなどして、どちらかが損をしたり得をしたりしないよう、公平な評価額になるよう話し合ってみましょう。
夫婦間で家の評価額について争いになった場合は、売却することも考慮に入れて、それぞれが自分の信頼する不動産会社で査定書を取得して、平均値を取るのがおすすめです。
その際、明らかに突出して高い査定額や低い査定額のものは外すようにしても良いでしょう。
3-2. 最終的には調停や裁判で裁判所に決めてもらう
どうしても離婚協議において夫婦で評価額の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。
その際、家を取得したい方が相手に相当額を支払って代償分割をしたいと希望する場合は、代償金の支払い能力が必要です。代償金を支払う資力がない場合は、売却か競売手続きで家を売り、その売却代金を夫婦で分けることになります。
家を取得する方に代償金の支払い能力があり、かつ夫婦で評価額について話し合ったものの合意に至らない場合は、最後は不動産鑑定を行って審判手続きによって不動産の価格が決まります。
ただし、不動産鑑定費用をはじめ、裁判にかかる費用や弁護士費用などが必要です。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 離婚で家やマンションなどの不動産を財産分与する際は、民法第768条に基づき、家の価値となる「評価額」を基準にして計算することになる
- 家の評価額を適切に把握しておかないと、次のような問題が生じる可能性がある
・不公平な財産分与になってしまう
・住宅ローン残債との関係を把握できない
・売却プランを立てられない - 離婚の財産分与で家の評価額を調べる場合は、不動産の価値の評価方法の一つである実勢価格を用いることが一般的
- 不動産鑑定士に評価を依頼すると、正確な評価額を算出してもらえるが費用がかかる
- 不動産会社による家の査定と評価額の算出は無料だが、売却することが前提となる場合が多い
- 路線価や固定資産評価額は実勢価格よりも低く設定されているため、使用する際は注意が必要
- 離婚での家の評価額で揉めたときは、夫婦それぞれの評価額の平均値を求めるのも一つの解決方法
- 離婚での家の評価額の話し合いがまとまらない場合は、調停・審判手続きを利用し、不動産鑑定を行って不動産の価値を決定する
離婚の際、家やマンションの評価額が決まらないと財産分与の話がまとまりません。そのため、双方がどこかの点で妥協して、話合いを進めていくことになります。
どうしても話し合いで納得できず、不動産会社の査定では家の評価額を決められない場合は、不動産鑑定士に鑑定をしてもらい、それを根拠として裁判所で決めてもらうしかありません。しかし、鑑定は査定とは異なり、何十万円もの費用がかかってしまうことを踏まえておく必要があります。
とはいえ、離婚の財産分与を話し合っている時点で、まだ売却することを決まってもいないのに、いきなり不動産会社に査定を依頼したり、相談するということにハードルを高く感じてしまうのは普通のことです。
離婚することになり、とりあえず自宅の査定価格を知りたいという場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。
無料&秘密厳守で簡単に素早く家や査定価格がわかるだけでなく、離婚による売却に強い不動産会社をランキング形式で選べます。さらに、家やマンションの売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので安心です。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。