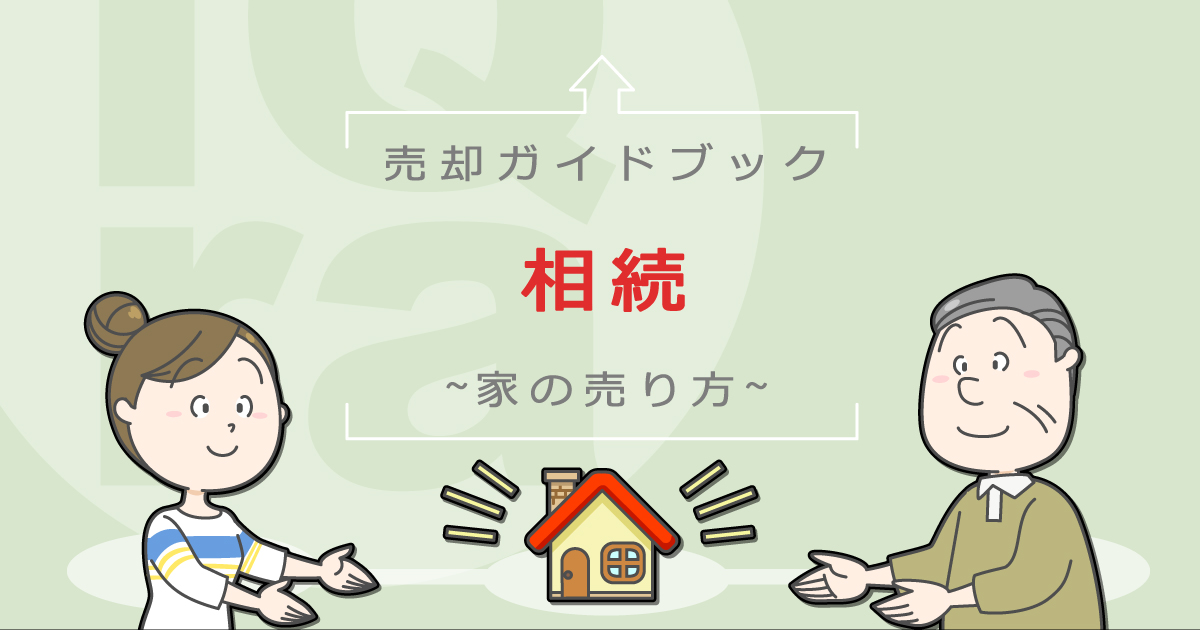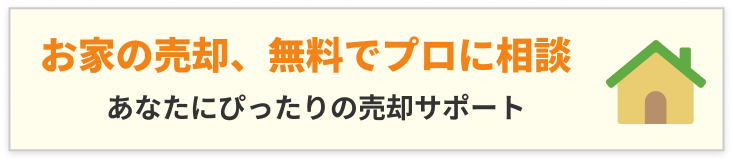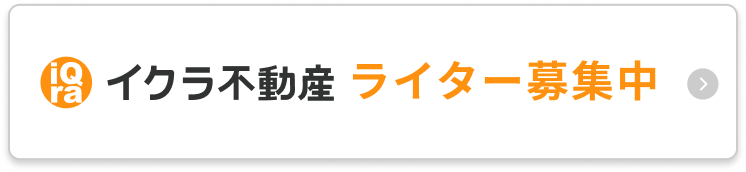家や土地などの相続した不動産を売却する際にかかる費用は、相続登記にかかる費用、売却にかかる費用、相続税の3種類です。
こちらでは、相続した不動産を売却する際にかかる3種類の費用について、それぞれいくら必要なのかをわかりやすく説明します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 相続した家などの不動産を売却するときにかかる、相続登記の費用、売却にかかる費用、相続税の3つの費用についてわかる
- 相続登記費用は、司法書士に依頼するかどうかで変わる。また、相続税の額や相続税がかかるかどうかは、相続した不動産の評価額によって決まる
- 相続登記をすれば、通常の不動産売却を同じように売ることができる。売却にかかる費用も通常の売却と同じだけかかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 実家や土地などの相続した不動産の売却を考えている人
- 相続した不動産を売却する際にかかる費用の内訳やおおよをの額を知りたい人
- 相続した不動産の売却方法と注意点を知りたい人
1.相続した不動産の売却の流れと費用
まず、実家や土地などの不動産の相続が発生して、その不動産を売却する際の流れと、どのような費用がかかるのかを確認しておきましょう。
不動産の相続が発生してから、仲介で売却するまでの大まかな流れと、それぞれの段階でかかる費用をまとめました。
| 相続から売却までの流れ | 内容 | 費用 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 相続人を確定する | 遺言書がなければ遺産分割協議書を作成する | ①司法書士への報酬(自分で作成すれば不要) | 相続が発生してからすぐに |
| 相続登記申請をする | むずかしい場合は司法書士に依頼する | ①司法書士への報酬(自分で申請すれば不要) ①相続登記の登録免許税 |
不動産の相続を知った日から3年以内 |
| 相続した不動産を売却する | 不動産会社に売却を依頼する | ②不動産会社への仲介手数料(仲介で売却した場合) ②売買契約書の印紙税 ②住宅ローン完済の事務手数料(住宅ローンが残っている場合) ②抵当権抹消手続きの費用(住宅ローンが残っている場合) |
|
| 譲渡所得税を納める | 相続した不動産を売却して利益が出た場合のみ | ②売却益の額と所有年数に応じて譲渡所得税額が決まる | ・相続した不動産を売却した翌年の確定申告で納税する |
| 相続税を納める | 相続税が発生する場合のみ | ③相続した不動産の評価額に応じて相続税額が決まる | ・相続発生を知った日から10ヵ月以内 |
この表のとおり、不動産を相続して売却する際にかかる費用は、①相続登記にかかる費用、②相続した不動産の売却にかかる費用、③相続税の3種類です。
それぞれについて、くわしく説明します。
2.相続した不動産の相続登記にかかる費用
相続登記とは、家の名義を亡くなった人から相続した人に変更する手続きのことです。相続登記をしなければ、相続した不動産を売却することができません。
さらに、2024年4月から相続登記申請が義務化されたため、売却する、しないにかかわらず、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、過料の対象となります。注意しましょう。
相続登記には、次の3つの費用がかかります。
- 登録免許税
- 登記に必要な書類を取得するための費用
- 司法書士の依頼費用(自身で登記する場合は不要)
それぞれについて、説明します。
2-1.登録免許税
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、相続登記にかかる税金です。
相続登記の登録免許税は、不動産の価値の指標となる「固定資産税評価額」に、登録免許税の税率0.4%を乗じて計算します。
相続登記の登録免許税の計算式
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額は、毎年、市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。手元にない場合は、役所で照会することができます。
2-2.相続登記に必要な書類の取得費用
相続登記の申請には、亡くなった人と相続する人の戸籍謄本や住民票などを一緒に提出する必要があります。いずれも亡くなった人との関係性を証明するのに必要な書類です。
基本的な相続登記に必要となる書類や取得費用は、次のとおりです。
| 必要な書類 | 費用 |
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 (複数の自治体で複数取得しなければならない場合もある) |
戸籍1通 450円 除籍等1通 750円 |
| 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票 | 300円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 1通 450円 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 1通 300円 |
| 家を登記する人全員の住民票 | 1通 300円 |
| 相続する家の登記簿謄本 | 1通 600円(ネット謄本の場合335円) |
相続人1人ずつ上記の書類を集めるのは大変なので、後述する司法書士に依頼することもできます。
その場合、1通あたりおよそ1500円が取得費用として別途かかるので、相続人全員分まとめて15通ぐらいで2万円以内ぐらいで依頼することができます(相続人が多すぎると別途かかります)。
ただし、印鑑登録証明書だけは司法書士でも取得できず、本人が取得しなければなりません。
2-3.司法書士に相続登記を依頼する費用
スムーズに相続登記を進めるために、司法書士に報酬を支払って相続登記を依頼しても良いでしょう。
相続登記に添付する書類の取得は、ときに時間と手間を要します。
特に亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得する作業は、亡くなった人の足跡をたどって自治体を回らなければならないこともあります。
司法書士は「不動産登記」の専門家です。相続人に代わって登記申請する代理権を持っているので、複雑な相続登記でも必要な書類の取得から申請まで一手に任せることができます。
相続に関する揉め事がなければ、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬は、法定相続人や相続遺産についての調査も含めて依頼すると平均6万円程度、遺産分割協議書の作成も依頼すると、さらに平均6万円程度が追加されます。
先の説明した提出書類の取得も含めて司法書士に依頼すると、取得にかかる実費にプラス10万円ほどかかるとみておきましょう。
相続についての相談先は「家を相続したときの相談窓口はどこが良いのか比較してみた」でくわしく説明していますので、ぜひご覧ください。
3.相続した不動産の売却にかかる費用
相続登記が完了すれば、相続した実家や土地などの不動産は相続人の所有物となるため、通常の不動産売却を同じように売却することができます。
したがって、通常の不動産売却と同じように、相続した不動産を仲介で売却する際には、次のような費用が必要です。
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 売買契約書に課せられる印紙税
相場価格に近い額で売りやすい仲介ではなく、買取で売却すれば売却額は安くなりますが、仲介手数料不要ですぐに現金化することが可能です。
仲介と買取の違いなど、不動産の売却方法については、「家の売り方は4種類!売却理由や状況に合った売却方法の選び方を解説」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
不動産売買の際の所有権移転登記の登録免許税は、一般的に買主が負担することが多いため、売主側が用意する必要はありません。
また、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、次のような費用もかかります。
- 住宅ローンの繰り上げ返済事務手数料
- 抵当権抹消登記の登録免許税と手続きの費用
さらに、相続した不動産の売却によって売却益が出た場合は、譲渡所得税を納めなければなりません。
一つずつ、説明していきます。
なお、不動産を売却した際にかかる費用や売却の流れについては、「【不動産売却の期間・流れ・費用のまとめ】初めての不動産売却で知っておくべきこと」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
3-1.仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社に不動産の売却を依頼して、売却が成功した際に不動産会社に支払う手数料のことです。
仲介手数料は、宅地建物取引業法で不動産会社が受け取れる上限額が定められており、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。
ただし、上限額いっぱいに設定している不動産会社がほとんどです。
仲介手数料の上限額の計算は、次の表のようになります。
| 売買代金(税抜) | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 400万円以下の場合 | 18万円+消費税(必要経費を含む) |
| 400万円を超える場合 | 売買代金✕3%+6万円+消費税 |
仲介手数料については、「家を売るときの仲介手数料はいくら?高い?なぜかかるの?」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
3-2.印紙税
売買契約が決まれば、売買契約書を作成します。
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書なので、定められた金額の収入印紙を貼付し、消印することによる納税が必要です。
印紙税の税額は、契約書に記載されている取引額によって次のように定められています。
おもな印紙税の額は、次のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 100万円を超え〜500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え〜1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え〜5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え〜1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え〜5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
※2027年(令和9年)3月31日までは軽減税率適用
(国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
3-3.住宅ローンが残っている場合にかかる費用
次に、相続した不動産に住宅ローンが残っていた場合にかかる費用を説明します。
3-3-1.住宅ローンの繰り上げ返済手数料
相続した不動産を売却する際に、住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンを完済しなければなりません。その際に、住宅ローンの繰り上げ返済手数料が必要になる場合があります。
住宅ローンの繰り上げ返済手数料は、住宅ローンを借りた金融機関によって異なります。多くの場合、無料〜3万円程度です。
3-3-2.抵当権抹消登記手続きの費用
住宅ローンが残っている場合や、住宅ローンを完済していても抵当権を外していない場合は、抵当権抹消登記の手続きをしなければなりません。
抵当権抹消登記の費用は、一つの不動産につき1,000円です。
また、抵当権抹消登記手続きも自分でできますが、司法書士に依頼することもできます。その場合は、1〜2万円ほどの報酬が必要です。
3-4.相続した不動産の売却で得た利益にかかる税金(譲渡所得税)
通常の不動産売却と同様に、相続した不動産を売却した際に売却益が出た場合は、その利益に対して「譲渡所得税」が課せられます。
ただし、得た利益すべてに課せられるのではなく、譲渡所得税が課せられるのは、その不動産の取得時や売却時にかかった費用を差し引いた額(課税譲渡所得)です。
譲渡所得税の計算式は、次のようになります。
譲渡所得税は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超えの場合は長期譲渡所得になります。
| 所有期間 | 譲渡所得税(※) | 住民税 | 合計 |
| 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超え | 15.315% | 5% | 20.315% |
※譲渡所得税には、2037年(令和19年)まで復興特別所得税が上乗せされている
※所有年数が10年を超えると、さらに税率が低くなる「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」が適用できる場合がある
ただし、譲渡所得(売却利益)が出ても、相続した家がマイホーム(居住していた家)であった場合には、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除される特例があります。そのため、課税譲渡所得が3,000万円までなら、譲渡所得税はかかりません。
また、相続した不動産を売却した場合、要件を満たせば相続税を取得費にすることができる特例(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)を適用できる場合があるため、さらに譲渡所得を抑えることができます。
くわしくは、「【相続×不動産売却のまとめ】相続した不動産の扱いについて基本から解説」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。
4.相続税
相続した不動産を売却する場合であっても、不動産の価額によっては相続税を納めなければなりません。
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を相続したとき、相続人が受け取った財産に課せられる税金です。
相続税の対象となるのは、相続した財産の総額になります。
不動産以外の財産があれば、相続税の対象はすべての財産を合計した額です。しかし、相続した財産が不動産だけであれば、相続税の対象となるのはその不動産の評価額になります。
相続税については「相続した家に相続税がかかる?かからない?計算方法や家の評価額の調べ方も解説」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
4-1.不動産の評価額を算出する
家や土地などの不動産は、現金や預貯金のように金額を固定して計算できるものではないため、相続税評価額(そうぞくぜいひょうかがく)を算出する必要があります。
建物部分については、固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)がそのまま相続時の評価額です。
戸建ての敷地や土地などの評価額を出すには、路線価(ろせんか)を使った計算が必要になります。
4-2.相続税評価額から基礎控除額を差し引く
相続税評価額のすべてに相続税が課税されるわけではありません。課税されるのは、基礎控除額(きそこうじょがく)や控除額などを差し引いた額です。
基礎控除額は、次のように計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、民法によって規定された一定の順序に従って相続人となる人のことで、配偶者と一定の血族(けつぞく:亡くなった人の血縁者)からなります。
まず、配偶者は必ず相続人となります。また、配偶者だけ相続するわけではなく、必ず配偶者と血族相続人が共同して相続します。
第1〜3順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも第1順位がいなければ第2順位といったように、次の順位で相続人となります。
つまり、故人の子と故人の親や、故人の親と故人の兄弟姉妹が一緒に相続人になることはありません。
| 血族相続人 | 内容 |
| 第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく:養子を含む子供・孫など) | 常に相続人となります。子供が死亡の場合は孫が代襲相続(だいしゅうそうぞく)で相続人となります。 |
| 第2順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など) | 直系卑属がいない場合、相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人とななります。 |
| 第3順位 兄弟姉妹 | 直系卑属・尊属共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が死亡の場合、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。 |
4-2-1.相続税の配偶者控除
配偶者は亡くなった人の財産形成に大きく貢献し、生計をともにしていたことが考慮されるため、相続税が大幅に軽減されます。
配偶者の税額控除額 = 法定相続分相当額と1億6000万円のいずれか大きい額を上限
4-2-2.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例の適用が受けられるのは、次のうちの誰かが相続した場合です。
- 配偶者
- 同居していた親族
- 配偶者も同居親族もいない場合、別居していて一定条件を満たす親族
③の場合の「一定条件」は少し複雑で、その家に相続開始の3年以内に本人やその配偶者、本人と特別な関係性の者が住んだことのない相続人、かつその家を相続税の申告まで所有している人となります。
小規模宅地等の特例が適用されると、330平方メートルまでの土地であれば、減額割合は80%です。
つまり、2,000万円の相続税評価額の土地だと400万円に評価額が減額されることになり、当然、相続税も安くなります。
4-3.相続税率を乗じて相続税を算出する
ここまでで説明した、
・家を含めた相続資産の総額
・基礎控除額
・評価額が下がる特例や控除
が把握できれば、金額に応じた税率と控除額によって相続税が算出できます。
【相続税の速算表】
| 取得価格 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続した不動産が、評価額3,000万円の家と3,000万円の現金の計6,000万円で、配偶者と長男と次男が相続するケースを想定し、相続税を計算してみましょう。各々が相続する割合は、次のとおりとします。
配偶者:1/2
長男:1/4
次男:1/4
まずは基礎控除額を出します。
3,000万円+600万円×3=4,800万円
法定相続人の数が3人なので、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産の総額が6,000万円なので、基礎控除額を引いても1,200万円残ります。この部分が相続税の課税対象となります。
控除しきれなかった1,200万円を各々の相続割合ごとに割り振ります。
配偶者:600万円
長男:300万円
次男:300万円
これが各々の取得価格となります。ここに上記の速算表に応じた税率をかけると、各々の相続税は次のようになります。
配偶者:60万円
長男:30万円
次男:30万円
ただし配偶者には特別控除がありますので、この場合の相続税はゼロです。子どもには控除はないので、長男、次男ともに30万円を納税する必要があります。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 不動産を相続した際にかかる費用は、大きく分けると相続登記にかかる費用、相続した不動産の売却にかかる費用、相続税の3つ
- 相続登記にかかる費用は、次の3つ
・登録免許税
・登記に必要な書類を取得するための費用
・司法書士の依頼費用(自身で登記する場合は不要) - 相続登記後は、通常の不動産と同じように売却することができる。売却にかかる費用も、通常の不動産売却と同じ
- 相続した不動産の売却にかかる費用は、次のとおり
・仲介手数料
・印紙税
(住宅ローンが残っている場合)
・住宅ローン完済事務手数料
・抵当権抹消登記手続きの費用
(売却益が出た場合)
・譲渡所得税 - 相続税は、相続した財産の総額から基礎控除などを差し引いた額に課せられる
不動産を相続した場合は、相続登記や相続税などの費用が必要です。また、相続した不動産を売却する際にも費用がかかります。
相続した不動産の売却額から相続税を支払うことも可能ですが、相続税の納付期限である10ヵ月以内に売却しなければなりません。相続した不動産の売却には、早くても3〜4ヵ月程度かかるため、相続登記にかかる期間も考慮したうえで、早めに行動することが大切です。
相続した不動産を売却したい場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。
無料&秘密厳守でいくらぐらいで売却できそうかがわかるだけでなく、相続物件がある地元で売却に強い不動産会社を選べます。
さらに、わからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも無料で相談できるので、安心して売却を進めることができます。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。