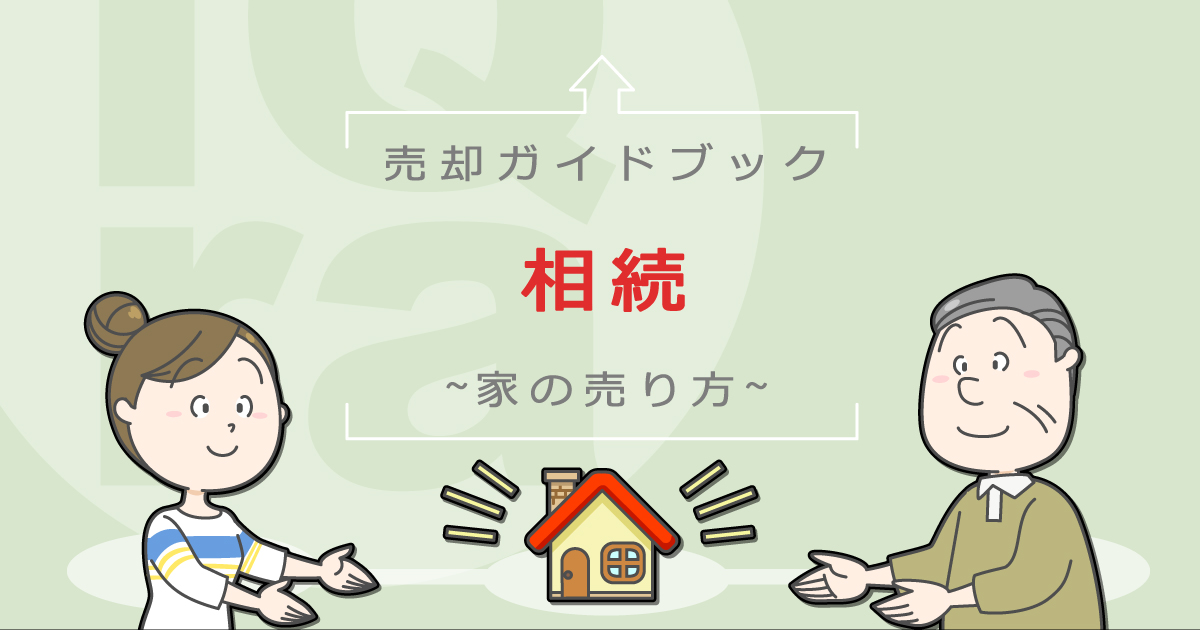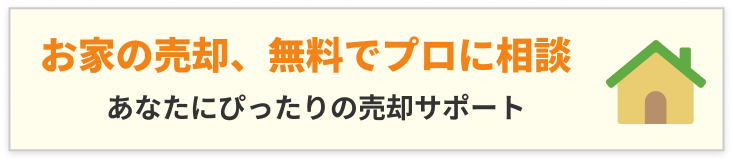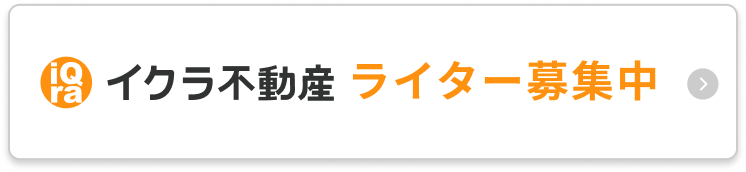この記事は、相続した不動産を売却する際の手続きや流れ、相続税対策などの取り扱い全般についてわかりやすくまとめたものです。
家や土地などの不動産を相続して売却したいけれども、どうすれば良いのかわからずに悩んでいる場合は、ぜひ一読して参考にしてみてください。
【この記事で具体的にわかること】
- 不動産を相続したときと売却する際の流れとやるべきこと
- 不動産を相続したときや売却する際にかかる税金や費用
- 相続した不動産売却時によくある疑問点と回答
- この記事はこんな人におすすめ!
- 不動産を相続することになったが、どうすれば良いのかわからずに困っている人
- 相続した不動産の売却方法を知りたい人
- 相続した不動産を売却する際にかかる費用を計算しておきたい人
不動産売却について基本から解説
- 実家の売却完全ガイド!売却方法や手順、税金などを生前、相続後、空き家別に解説
- 実家を兄弟で相続!住んでいる人がいてもトラブルを回避してスムーズに分割する
- 相続した家を解体する注意点は?メリット・デメリット、解体費用について解説
- 家や土地などの相続不動産がいらない場合の相続放棄や処分方法をわかりやすく解説
「売却一年生」TOPに戻る
1.相続した不動産はどうすれば良いのか?
3つのポイント
- 相続した不動産は、売却する、相続した人が住む、賃貸に出す、空き家のままにしておく、のいずれかの方法を取ることが多い
- 相続した不動産の使い道が特になければ、売却するのがトラブルが少ないのでおすすめ
- 相続した家を空き家にしたまま放置すると、思わぬ損をすることになるので注意する
相続した家や土地などの不動産をどうしようかと悩まれている方も多いでしょう。
相続した不動産は、次の4つの方法のいずれかを取ることがほとんどです。
- 売却する
- 相続した人が住む
- 賃貸に出す
- 空き家のままにしておく
当面、使う予定がない相続不動産は、売却するのがおすすめです。
なぜ売却がおすすめなのか、ほかの方法はどうなのかを1つずつくわしく説明します。
1-1.相続不動産は売却するのがおすすめの理由
まず、なぜ相続した家や土地などの不動産は、売却するのがおすすめなのかを説明します。
1-1-1.相続人同士のトラブルが生じにくい
相続人が複数いる場合、亡くなった人の遺言状や法律に則って相続財産(遺産)を分割します。
これは、相続財産が現金や物品であっても家や土地などの不動産であっても同じです。
しかし、不動産の場合だと1つとして同じものがなく、また定価もないため、現金のように明確に分けることができません。
そのため、特に相続財産を分割する際は、不動産のままで分けるよりも、売却して現金を分けるほうがトラブルが生じにくいと言えます。
1-1-2.不動産の管理費や税金がかからなくなる
所有者が亡くなったとしても、家や土地などの不動産には、固定資産税が毎年課せられます。
また、適切に維持するための管理費用が必要です。マンションであれば、管理費や修繕積立金の支払いがあります。
しかし、売却してしまえば、それらの費用はかかりません。相続人が複数いる場合も、誰がどれだけ負担するかで揉める心配がなくなります。
1-1-3.特例や控除を受けられる
不動産を相続した場合、相続税がかかります。また相続した不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税も納めなければなりません。
しかし、一定期間内に相続して売却すれば、相続税や譲渡所得税の特例や控除を受けられます。
そのため、いずれ売却するのであれば、適用できる期間内に売るのがおすすめです。
1-2.売却以外の方法のメリットとデメリット
相続した不動産の取り扱いとして、売却以外の方法もあります。
しかし、売却以外の方法は、メリットよりもデメリットが多くなりやすいため、あまりおすすめではありません。
ここでは、相続した不動産の売却以外の方法のメリット、デメリットを説明します。
1-2-1.相続した人が住む
相続した不動産が家やマンションであれば、もちろん、相続した人がそのまま住むことも可能です。亡くなった人の同居者が家を相続した場合は、売却よりもこちらの方法が自然な流れかもしれません。
ただし、複数人で相続して居住希望者が2人以上いる場合、誰が住むかで揉める可能性があります。
また複数人の共有不動産にして、住むことになった相続人がほかの相続人に賃料を支払うとなると、手続きや清算などでトラブルになりやすいと言えるでしょう。
1-2-2.賃貸に出す
相続した不動産を売るのではなく、賃貸に出すこともできます。賃貸に出せば、家賃を固定資産税や管理のための費用に充てることも可能です。
しかし、賃貸に出している家やマンションの管理は思った以上に手間や労力がかかります。
当然ですが、入居者がいない間は家賃収入はありません。不動産会社に入居者の募集や管理を委託すれば、その分の管理委託費が必要です。
また相続人が複数いる場合、家賃収入や管理費用をどのように分けるのか、また連絡係を誰にするのかといったことを決める必要があります。
そのようなことを鑑みると、複数人で賃貸に出すのは、あまりおすすめだとは言えないでしょう。
1-2-3.空き家のままにしておく
相続した不動産をどうすれば良いかわからず、空き家にしたままのケースもよく見受けられます。
しかし、特に戸建ての家の場合に注意しなければならないのが、この空き家のままの放置です。
先にも述べたとおり、空き家であっても固定資産税が課せられます。また家をきちんと維持していくためには、管理費用が必要です。
適切な管理をせずに放置していると、建物が傷んだり雑草が生えたりして廃屋になり、近隣住民とのトラブルになる可能性があります。
さらに、廃屋になって各自治体の「空き家条例」に抵触すると、所有者へ勧告や措置命令が出され、強制的に建物が解体され費用を請求される恐れがあるため注意が必要です。
空き家条例については、「空き家予備軍とは?「空き家」になる前にとるべき対策を解説!」の記事で説明しています。ぜひ一読してみてください。
これらの理由から、相続したまま放置している空き家がある場合は、できるだけ早めに売却するのがおすすめです。
相続した不動産や放置している空き家を少しでも早く、良い条件で売りたいのであれば、そのような売却を得意としている不動産会社を探す必要があります。
しかし、どの不動産会社に任せれば良いのか見極めるのは困難です。
そのような場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。
売りたい相続不動産がある地域で、相続物件や空き家の売却を得意とする、売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことができます。
さらに、イクラ不動産独自の価格シミュレーターで、簡単に素早く相場価格を知ることも可能です。
連絡は売主であるお客様からのため、不動産会社からのしつこい営業電話やメールの心配もありません。
2.不動産の相続発生から売却するまでの流れと手続き
3つのポイント
- 相続した不動産を売却する際は、まず相続登記をして不動産の名義変更をしなければならない
- 相続した不動産を売却するときは相続人全員の同意が必要
- 相続登記後の売却の流れは通常の売却と同じ
相続した不動産を売却しようとしても、何から手をつければ良いのかわからない人も多いです。
ここでは、不動産の相続が発生したときから、相続した不動産を売却するまでの流れと手続きを説明します。
不動産の所有者が亡くなってから相続した不動産を売却するまでの流れは、大きくまとめると次の3ステップです。
| ステップ① | 不動産の所有者が亡くなった手続きをする |
|---|---|
| ステップ② | 相続登記をして不動産の所有者の名義変更をする |
| ステップ③ | 相続した不動産を売却する |
相続した不動産の売却の流れや手続きについては、「相続した不動産の売却方法や流れ、手続き、やるべきことをわかりやすく解説」でよりくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
2-1. ステップ①:不動産の所有者が亡くなった際の手続きをする
不動産の所有者が亡くなった場合、遺族がやるべきことは、次の表のとおりです。
| 期限 | やるべきこと |
|---|---|
| 亡くなってからすぐ(7日以内) | 死亡届の提出 |
| 亡くなってすぐ〜相続登記まで | 遺言書の有無の確認 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合) |
| 14日以内 | 年金受給停止手続き(厚生年金の場合は10日以内) |
| 住民異動届け(世帯主の変更届け) | |
| 健康保険・介護保険の手続き | |
| 3ヵ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4ヵ月以内 | 所得税の準確定申告(※) |
| 10ヵ月以内 | 相続税の申告 |
| 3年以内 | 相続した不動産の名義変更(相続登記) |
※亡くなった人が確定申告が必要である場合、相続人が代わりに所得税の申告を税務署で行うこと。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
これらの手続きと平行して、誰が、どのように遺産を相続するかを決めます。
遺言書があれば、遺言書の内容に従って不動産をはじめとする遺産の分け方が決まります。したがって、まずは遺言書の確認が必要です。
遺言書がない場合は、相続人を決めるための遺産分割協議を開いて、相続人と遺産の分け方を確定しましょう。
2-2. ステップ②:相続登記申請をして不動産の名義変更をする
不動産の相続人が決まれば、相続登記申請をして不動産の名義人の変更をします。相続登記をしなければ、相続した不動産を売却することができません。
相続登記申請は、次の書類と相続登記の申請書を合わせて、法務局に提出して手続きします。
| 取得場所 | |
|---|---|
| 亡くなった不動産所有者の戸籍謄本 | 居住していた市区町村役場 |
| 亡くなった不動産所有者の住民票の除票 | 居住していた市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 居住している市区町村役場 |
| 相続人全員の住民票 | 居住している市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 居住している市区町村役場 |
| 登記事項証明書(登記簿の写し) | 不動産所有者(または法務局) |
| 不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所有者(または市区町村役場) |
| 遺産分割協議書または遺言書(検認を受けたもの) | 相続人で作成したもの・不動産所有者 |
書類を揃えるのが大変だったり手続きがむずかしかったりする場合は、司法書士に依頼しても良いでしょう。
司法書士への報酬の目安は、次のとおりです。
【司法書士への報酬の目安】
- 相続登記手続きだけの場合:数万円〜10万円程度
- 遺産分割協議書の作成なども含む:10万〜15万円程度
2-2-1.相続登記申請の義務化に注意
相続登記がなされず、所有者がわからなくなった土地や空き家が増えてきたため、2024年4月から相続登記申請の義務化が施行されました。
これにより、相続による不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となります。
義務化される前に相続した不動産で、相続登記申請をしていない場合も対象となるため、相続登記をせずに放置している不動産がある場合は、早めに相続登記申請をしましょう。
くわしくは、「相続した家の売却に必要な相続登記とは?手順と義務化についても解説」で説明しています。ぜひ読んでみてください。
2-3.ステップ③:相続した不動産を売却する
相続登記が完了し、不動産の名義が亡くなった人から相続人に移れば、相続した不動産を売却できるようになります。
相続した不動産を売却する場合でも、売却方法は通常の不動産売却と同じです。
売却方法は、大きく分けると「仲介」と「買取」の2種類があります。それぞれメリットとデメリットがあるため、目的に合った方法を選ぶようにしましょう。
仲介と買取、それぞれのメリットとデメリット、特徴をまとめたものが次の表です。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 買い手 | 一般消費者 | 不動産会社 |
| 売却期間 | 平均3〜6ヵ月 | 即日〜1週間も可能 |
| 売却額 | 相場価格に近い額 | 相場価格の7割前後 |
| 仲介手数料 | 売却金額×3%+6万円(+消費税) | 基本的に不要 |
| メリット | 相場価格に近い額で高く売ることができる | そのままの状態ですぐに現金化できる |
| デメリット | 買い手が見つかるまで売れない(売却活動に時間がかかる) | 仲介で売るより安くなってしまう(相場価格の7割程度) |
売却期間がかかっても少しでも高く売りたい場合は仲介、売却期限が迫っているなどすぐに不動産を現金化したい場合は買取がおすすめです。
仲介で売却する際の流れについては、「不動産仲介とは?家を希望に近い価格で高く売却できる方法を解説!」で、買取を利用して売却する際の流れについては、「不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
- 合わせて読みたい
- 相続する不動産を売るときの流れ(マンション・戸建て・土地編)
- 相続した家の共有持分を家族(親族)に売る時の注意点についてまとめた
- 相続した家を売るときに必要な相続登記の手続き方法をまとめた
- 相続した家を解体するときの注意点をわかりやすく説明する
3.相続した不動産を売るときにかかる費用や税金
3つのポイント
- 相続した不動産売却時にも、通常の不動産売却と同じように仲介手数料などの売却費用がかかる
- 相続した不動産を売却する際、控除や特例を適用すれば税金が安くなるが、期限があるので注意する
- 相続した不動産が居住用だったかどうかや所有年数で、控除や特例の適用が変わる
相続した不動産を売るとなった際、いくらぐらいのお金がかかるのか気になります。
相続した不動産の売却時に発生する費用は、大きく分けると次の3つです。
- 相続した不動産の売却にかかる費用
- 売却して利益が出た場合に課せられる税金
- 相続税
それぞれ、どのような費用で、どれくらいかかるのかをわかりやすく説明します。
3-1.相続した不動産の売却にかかる費用
相続した不動産を売却する場合であっても、売却にかかるお金は通常の不動産売却と同じです。
不動産会社に依頼して、仲介で相続した不動産を売却する場合は、次のような費用がかかります。
- 仲介手数料(400万円超の取引額の場合 【原則】取引額の3%+6万円+消費税)※
- 印紙税(取引額による。1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円)
- 抵当権抹消登記の費用(住宅ローンが残っている場合に必要。2〜5万円程度)
- 住宅ローン返済事務手数料(住宅ローンが残っている場合に必要。金融機関によって異なる)
※800万円以下の「「低廉な空家等」の取引の場合、【原則】による上限を超えて「30万円×1.1倍の金額」以内の請求が可能
ほかにも、土地の測量費用や建物の解体費用などがかかる場合があります。
一般的に、仲介で不動産を売却する際の費用は、売却額の5%程度と言われています。
あらかじめ売却に際してどのような費用がかかるか、不動産会社に確認しておくようにしましょう。
買取業者や不動産会社に、直接不動産を買い取ってもらう買取での売却であれば、不動産会社に支払う仲介手数料は基本的に不要です。
ただし、買取を利用した場合、売却額は仲介で売却する場合より3割程度安くなります。
不動産売却にかかる費用については、「家やマンションの売却にかかる費用を解説!手元に残るのは結局いくら?」でくわしく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
3-2. 相続した不動産を売却して得た利益に課せられる税金
相続した不動産を売却して利益が出た場合、その利益分に対して「所得税」と「住民税」から成る「譲渡所得税」が課せられます。
譲渡所得税が課せられるのは、売却額ではなく、売却額から売却にかかった費用を差し引いた「課税譲渡所得」に対してです。
課税譲渡所得額の額は、次の計算式で算出されます。
課税譲渡所得=売却額−(取得費+譲渡費用)−控除額
取得費とは、売却した不動産を取得した際にかかった費用の総額です。不動産を購入した費用以外にも、購入する際に不動産会社に支払った仲介手数料なども含まれます。
譲渡費用とは、売却した際にかかった費用の総額です。売却時に不動産会社に支払った仲介手数料なども含まれます。
この課税譲渡所得に、譲渡所得税の税率を乗じたものが、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、相続人で売却代金を分割したあとではなく、分割する前の全額に対して課せられます。
3-2-1.譲渡所得税の税率は所有年数によって変わる
譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた年数が5年以下か5年を超えるかによって変わります。
親などから相続した不動産の売却時には、所有年数を引き継ぐことが可能です。
所有期間による譲渡所得税の違いは、次の表のようになります。
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 課税譲渡所得×39.63% | ||
|---|---|---|---|
| 所得税:30% | 住民税:9% | 復興特別所得税:所得税額の2.1% | |
| 長期譲渡所得
(所有期間5年超) |
課税譲渡所得×20.315% | ||
| 所得税:15% | 住民税:5% | 復興特別所得税:所得税額の2.1% | |
所有期間のカウント方法は、実際に所有していた期間ではなく、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかです。注意しましょう。
3-2-2.所有年数が10年を超えると税率がさらに下がる
住まいとして使われていた不動産を相続して売却した際に、所有期間が10年を超えていれば、売却して得た利益(譲渡所得)のうち6,000万円以下の部分については、次のように税率がさらに低くなる特例があります。
| 10年超所有の居住用不動産の譲渡所得 | 6,000万円以下の部分 | 譲渡所得税率:14.21% |
|---|---|---|
| 6,000万円超の部分 | 譲渡所得税率:20.315% |
譲渡譲渡所得税が出た場合は、売却した翌年に確定申告をして納めなければなりません。
譲渡所得税や確定申告については、売却を依頼する不動産会社に相談してみましょう。
3-3.相続税
亡くなった人の遺産を相続した場合は、その額に応じた相続税を納めなければなりません。相続した不動産にも相続税が課せられます。売却したとしても同じです。
ただし、相続した財産の全額に相続税がかかるわけではなく、法律で定められた「基礎控除」を差し引いた額に課税されます。
基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
相続した財産の総額から、この計算式で算出された基礎控除額を差し引いた額に相続税が課せられます。
たとえば、相続した財産の総額が1億円で法定相続人として妻と子2人がいる場合、相続税が課せられる額の計算式は次のとおりです。
1億円−(3,000万円+3人✕600万円)=5,200万円
-
- 妻の相続分として課税される額:5,200万円✕1/2=2,600万円
- 子①の相続分として課税される額:5,200万円✕1/4=1,300万円
- 子②の相続分として課税される額:5,200万円✕1/4=1,300万円
※配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は残りの1/2を人数で割る
相続税の基となる額を算出したら、その額に税率を乗じて控除額を差し引き、相続税額を相続人ごとに計算します。
相続税の税率と控除される額については、国税庁のサイトで確認してみてください(国税庁「No.4155 相続税の税率」)。
ただし、配偶者は税額軽減が適用されるため、1億6,000万円までは相続税がかかりません(※国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」)。
相続税の計算については、「相続した家に相続税がかかる?かからない?計算と評価額、節税方法も解説」でくわしく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
3-3-1.不動産の相続税を取得費にする「取得費加算の特例」
相続した不動産を売却する際、適用できる控除や特例がいくつかあります。適用要件を満たしている場合、それらを使えば税金を抑えることが可能です。
「取得費加算の特例」とは、相続した不動産を一定期間内に売却するなどの要件を満たせば、相続税として支払った額の一部を取得費として計上できる特例です。
取得費として加算できる相続税額は、次の計算式で求められます。
取得費として加算計上できる相続税の額=譲渡した人が納付する相続税額✕(譲渡資産の相続税の課税価格÷債務控除前のその人の相続税の課税価格)
取得費として計上できる額が多くなれば、課税譲渡所得額が減るため、結果として譲渡所得税が安くなります。
取得費加算の特例は、相続が発生した日から3年10ヵ月以内(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)に売却しないと適用できません。
相続してから期間が空いている不動産を売却する際は、適用期間がいつまでかを確認しておきましょう。
3-3-2.譲渡所得税が軽減される「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続して売却した不動産が住まいとして使われていた場合、一定の要件を満たせば、課税譲渡所得額から最高3,000万円まで控除できるという特例です。
つまり、居住用として使われていた戸建てを売却して利益を得たとしても、その額が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかかりません。
ただし、取得費加算の特例との併用はできないため、どちらが得になるかをあらかじめ計算しておきましょう。
また、この特例を適用するためには、そこに住まなくなってから3年が経過する年の12月末までに売却する必要があります。適用する場合は、期限を確認しておくことが大切です。
居住用として使われていた家(建物)を取り壊したあとの土地にも適用できる場合があります。
適用要件や適用できるかどうかについては、国税庁のサイトで確認してみてください。
国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
4.相続した不動産売却に関するQ&A
相続した不動産を売却する際に、よくある疑問点とその説明をまとめました。それぞれ、くわしく説明している記事もあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
4-1.売却しても住み続けたい相続人がいる場合は「リースバック」がおすすめ
〈質問〉
〈回答〉
相続人のうち、その家にこれまで住んでいた人がいる場合、売却されると住むところがなくなるので困るというケースがあります。
しかし手持ちの資金がないため、相続した家を売却しないとほかの相続人への代償金が支払えないといった場合におすすめなのが、リースバックです。
リースバックを利用すれば、家の売却代金としてまとまった額のお金を受け取ってから、その後、賃貸としてこれまでと同じように住み続けることができます。
つまり、家の売却代金を相続人で分け、その家に住んでいた相続人は、家賃を支払うことでこれまでと同じように住み続けることができるのです。
リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」でくわしく説明しています。ぜひ読んでみてください。
4-2.相続人の代表者が売却する場合は委任状があればできる
〈質問〉
〈回答〉
相続人が複数いる不動産を売却する場合、相続人全員の同意と売買契約書への署名捺印が必要です。
すべての相続人が売買契約に立ち会うのが大変な場合は、売買契約を結ぶ際の代表者(相続人代表者)を決めて、代表者のみで契約をするという方法もあります。
代用者を任命する際は、次のような内容を記載した委任状を作成し、相続人全員で署名捺印をします。
- 売買金額(取引額)
- 受領する手付金の額
- 違約金の額および契約解除の条件や期限
- 引き渡しおよび決済の時期
- 売却にかかる費用の負担について
委任状にこれらの権限の範囲を設定しておくことで、代表者が勝手に取引内容を変更するのを防ぐことができます。
委任状の作成については、「所有者以外が家などの不動産売却を代理でする方法と委任する際の注意点」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
4-3.相続した不動産の評価額を調べる方法
〈質問〉
〈回答〉
相続した財産が不動産の場合、売却せずに相続税を算出するためには、その不動産の価値がいくらぐらいかという「評価額」が必要です。
建物と土地とでは評価額の算出方法は異なるため、別々の計算方法になります。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は、毎年4月〜6月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」で確認できます。
更地や戸建ての敷地といった土地の評価額は、「路線価方式」による算出が基本です。
路線価とは、国税庁が出している「路線価図」に記載されている路線(道路)に面する土地、1平方メートル当たりの価額を指すもので、公示地価の約8割の価格に設定されています。
この路線価に、評価したい土地の面積と土地の形状や道路の接面状況などによる補正率とを乗じて評価額を算出します。
計算式は次のとおりです。
土地の相続税評価額=路線価✕面積(㎡)✕補正率
路線価が定められていない場所は、「倍率方式」を用います。倍率方式とは、固定資産税評価額に評価倍率表で定められている倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
次のような計算式になります。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額✕評価倍率表で定められた倍率
相続した家や土地の評価方法については、「相続した家の評価額の計算方法をわかりやすく説明する」でくわしく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
4-4.相続した不動産が売れない場合は買取を利用してみる
〈質問〉
〈回答〉
相続した不動産がなかなか売れない場合は、不動産会社を変えてみるのも一つの方法です。
特に、田んぼなどの農地や山林、市街化調整区域にある物件などの場合、それらの売却が得意な不動産会社と苦手な不動産会社があります。
また、一般の消費者から買い手を探す仲介ではなく、不動産会社に直接買い取ってもらう買取なら売却できるケースが多いです。
売却したい物件がある地元で、買取が得意な不動産会社や売れにくい物件の売却が得意な不動産会社を探したい場合は、ぜひイクラ不動産をご利用ください。
不動産の相続は、ほかの相続財産と同じように相続放棄が可能です。しかし、不動産をはじめとする遺産の相続を放棄する場合は、原則としてほかの相続財産すべてを放棄しなければなりません。土地はいらないけれど、預貯金は相続したいといったことはできないため注意しましょう。
不動産の相続を放棄した場合、その不動産を相続するのは、自分以外のほかの相続人です。
相続人が次々と放棄をして、最終的に相続する人がいなくなった場合は国庫に帰属することになりますが、「相続財産管理人の選任」が必要になります。この点にも注意しなければなりません。
くわしくは「いらない家を相続したらどうすればよいのかわかりやすくまとめた」で説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 相続した不動産は、次のような理由から売却するのがおすすめ
・相続財産分割時の相続人同士のトラブルが生じにくい
・不動産の管理費や税金がかからなくなる
・一定期間内に売却すると特例や控除が受けられる - 不動産を相続して売却する際の大まかな流れは次のとおり
1.不動産の所有者が亡くなった手続きをする
2.相続登記をして不動産の所有者の名義変更をする
3.相続した不動産を売却する - 相続した不動産を売却する際にかかるお金には、次のようなものがある
・仲介手数料などの売却にかかる費用
・売却して得た利益にかかる譲渡所得税
・相続した不動産の価額に応じて課せられる相続税 - 相続税や譲渡所得税が課せられる場合であっても、控除や特例を適用すれば税金が安くなることがある
- 売却しても住み続けたい相続人がいる場合は「リースバック」の利用を検討すると良い
- 委任状があれば、相続人の代表者が売却することができる
- 相続した不動産が売れない場合は、買取での売却を検討してみると良い
家や土地などの不動産を相続した場合、特に利用予定がなければ売却するのがおすすめです。
特に相続人が複数いる場合、売却すれば公平に分割しやすくなります。また、相続した不動産が遠方にある場合などは、売却してしまえば、管理費用だけでなく手間や時間もかかりません。
相続した不動産を売却する際に気になるのが、税金や売却にかかる費用です。相続した不動産を売却する際の特例や控除には、適用できる期限があるため注意しましょう。
また、売却して得た利益に課せられる税金の控除や特例にも期限があるため、売却するなら早めに行動することが大切です。
相続した不動産をスムーズに売却したい場合は、弁護士や税理士、司法書士などと連携している相続物件の売却に強い不動産会社に依頼しましょう。
イクラ不動産なら、不動産会社の売却実績がわかるため、売却に強いだけでなく、相続物件の扱いが得意な不動産会社がわかります。もちろん無料&秘密厳守です。
さらに、売却前や売却中にわからないことや不安なこと、不動産会社に質問しにくいことなどがあれば、イクラ不動産の宅建士の資格を持った専門スタッフに、いつでも無料で相談できるので安心して売却を進めることができます。
やりとりは売主様から始める気軽なチャットなので、不動産会社からのしつこい営業の心配などがありません。
相続した家や土地などをどうしようかと悩んでいる方は、ぜひイクラ不動産をご利用ください。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明しています。