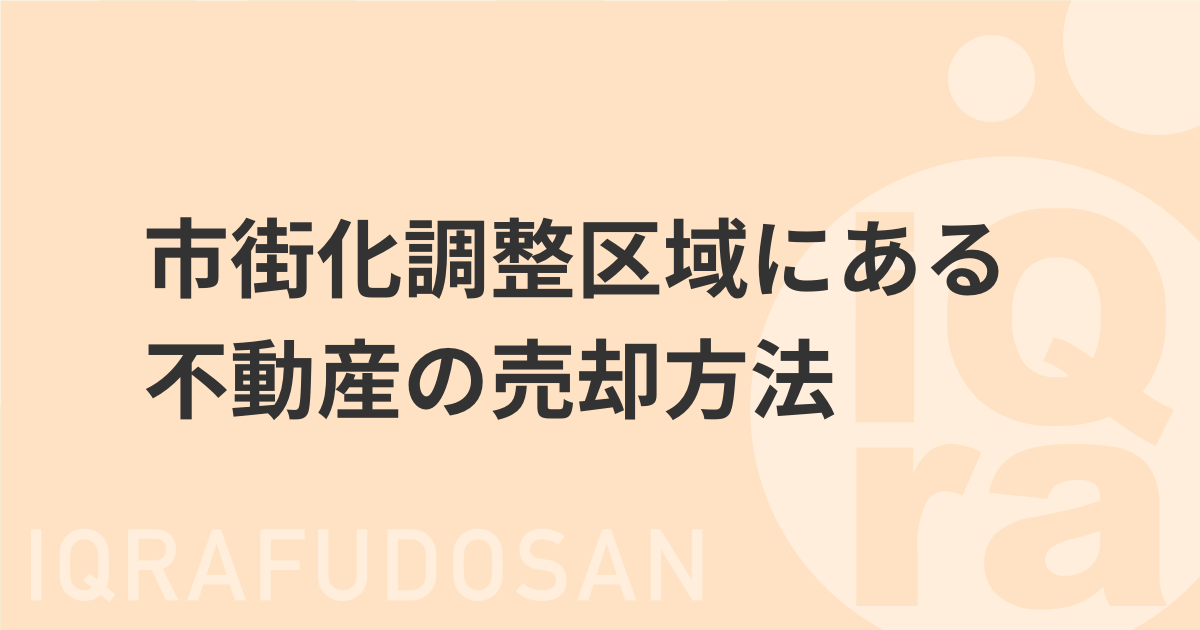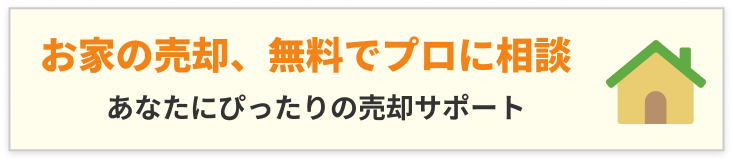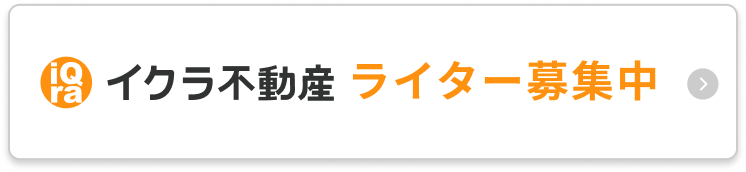市街化調整区域にある土地や建物は、一般的に「売れにくい」と思われがちです。なぜなら、原則として家などの建築・開発が厳しく制限されている区域だからです。
こちらは、実際に「イクラ不動産」に寄せられたご相談の一例になります。
【実際の相談例】
💬 市街化調整区域に建っている家を売りたいのですが、知り合いから売却がむずかしく、ほとんど値がつかないと言われました…
できれば少しでも高く売りたいのですが…
市街化調整区域の物件が売れにくいのは事実です。しかし、正しい知識を持ち、ポイントを押さえれば売却は決して不可能ではありません。
むしろ、買主の不安を解消し、専門知識を持つ不動産会社と連携することで、スムーズな売却が実現できます。
こちらでは、市街化調整区域の基礎知識から、売却を阻む具体的な壁、そしてその壁を乗り越えるための実務的なステップ、さらには売却を成功に導く不動産会社の選び方まで、徹底的に解説します。
この記事で具体的にわかる3つのポイント
- 市街化調整区域にある不動産がなぜ売れにくいのか、その根本理由がわかる
- 売却前に「役所で何を」「どのように」調査すべきか、具体的な行動がわかる
- 市街化調整区域の売却に本当に強い不動産会社の選び方がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 売却したい家や土地が市街化調整区域にある人
- 市街化調整区域にある不動産売却の具体的な注意点と対策を知りたい人
- 信頼できる不動産会社を見極め、売却を成功させたい人
不動産売却について基本から解説
- 【売れない・売れにくい不動産×解決策のまとめ】家が売れない原因と売るために売主がやるべき対策
- 別荘を売却するには?売れにくい理由と上手に売る方法を解説
- ゴミ屋敷の物件を売却、買取する方法と売却にかかる費用について解説
「売却一年生」TOPに戻る
もくじ
1. 市街化調整区域とは?初心者でも分かる基礎知識
いざ、不動産を売却しようとした際に、「市街化調整区域」という言葉に直面して困惑する人も多いことでしょう。
市街化調整区域とは、都市計画法によって定められた地域区分の一つであり、都市開発が制限されるエリアのことです。
まずは、市街化調整区域についての基本を押さえていきましょう。
1-1. 市街化区域と市街化調整区域の違い
「市街化区域」と「市街化調整区域」は、名前が似ていますが、その役割や性質は次のように大きく異なります。
- 市街化区域
市街化を促進するエリア。住宅地や商業地としての開発が積極的に進められる。建物の建築やインフラ整備がしやすく、一般的に不動産価値も高い傾向にある - 市街化調整区域
市街化を抑制するエリア。都市としての計画的な開発を防ぐために指定される。原則として建物の新築や大規模な開発は制限され、不動産としての流動性は低くなることが多い
この市街化区域と市街化調整区域に分けることが「区域区分(線引き)」と呼ばれるものです。
まとめると、市街化区域は「開発を進める地域」、市街化調整区域は「開発を抑える地域」という違いがあります。
1-2. 市街化調整区域に指定される理由
市街化調整区域に指定されるおもな理由は、無秩序な都市拡大を防ぎ、計画的な街づくりを進めるためです。
具体的には、次のような背景があります。
- 自然環境や農地の保護
無計画な開発による自然破壊や農地の減少を防ぐため、一定のエリアを市街化調整区域に指定します。 - インフラ整備の効率化
都市開発が無秩序に進むと、道路や上下水道などのインフラが非効率に整備されてしまいます。それを防ぎ、計画的に整備するために区域が分けられています。 - 人口集中の抑制
人口が都市の中心部に集中しすぎることを防ぎ、バランスよく居住地を配置するためにも市街化調整区域が活用されています。
市街化調整区域を設けることにより、都市環境の乱れを防ぎ、持続可能な街づくりを維持することが期待できます。
1-3. 市街化調整区域のメリットとデメリット
市街化調整区域のメリットとデメリットは、次のとおりです。
1-3-1.市街化調整区域のメリット
- 自然環境が保たれている
市街化が進みにくいため、豊かな自然や静かな環境が維持されやすい - 固定資産税が低い
市街化調整区域内の土地は、市街化区域に比べて固定資産税や都市計画税が低く抑えられることが多い - 農業や自然利用に適している
建物の建築が制限される代わりに、農地や自然を活かした用途には適している
1-3-2.市街化調整区域のデメリット
- 開発や建築の制限
原則として建物の新築や大規模な開発が認められないため、不動産の価値が低くなりやすい - 売却が難しい
建築制限があるため、需要が少なく、買い手が見つかりにくいことが多い - 将来的な土地利用の不確実性
市街化区域に変更される可能性も低く、将来的に土地を有効活用する見通しが立てにくい
市街化調整区域にある物件の売却を検討する際には、これらのメリットやデメリットを理解しておくことが大切です。
2. なぜ売れない?市街化調整区域の物件が持つ3つの壁
市街化調整区域に指定された土地や物件は、一般的な市街地に比べて売却がむずかしいと言われています。
その理由は、利便性が悪い田舎にあるため価格が安くなりやすいほか、開発や建築に対する制限が多く、買主にとって不都合なことが多いことが影響しているからです。
買主にとって不都合となる、市街化調整区域のおもな壁として、次の3つがあげられます。
- 【建築の壁】建物に対する厳しい制限
- 【資金調達の壁】住宅ローンの高いハードル
- 【手続き・費用の壁】インフラ負担と複雑な手続き
一つずつ、くわしく見ていきましょう。
2-1.【建築の壁】建物に対する厳しい制限
市街化調整区域は、無秩序に建物を建てて市街地を拡大することを防ぐ目的で定められています。
そのため、市街化調整区域で家を建てるときには、自治体からの開発許可や建築許可が必要です。建て替えや大規模なリフォームの際も同様の扱いになります。基本的に、都市計画法に適合する建築物以外を建てることは認められません。
具体的には、開発行為(山林や水田などを住宅用の土地にするための宅地整備工事)を行うためには、開発許可を取る必要があります。また、すでに宅地であっても、家を建て直したりする場合は、建築許可が必要です。
都市計画法によって、市街化調整区域で建築を認められる建物は、農業や林業、漁業を営む人々が建てる建物などに厳しく制限されています(都市計画法の第29条及び法第34条)。
2-2.【資金調達の壁】住宅ローンの高いハードル
市街化調整区域にある土地や家の購入で住宅ローンを組む際、融資の審査が非常に厳しくなります。
住宅ローンは、万が一返済が滞ったときのために、購入した土地や建物を担保にします。建築や活用に制限がある市街化調整区域の不動産は、担保価値が低く評価されがちです。
金融機関がチェックする厳しい視点
住宅ローン審査では、単なる「土地の評価額」だけでなく、以下のような点も重要視されるため、金融機関によって判断が大きく異なります。
- 再建築の可否:将来、問題なく建て替えができる土地か
- 用途変更の可能性:住宅以外の活用が見込めるか
- インフラ接続状況:上下水道や道路が整備されているか
メガバンクなどは融資に消極的な一方、JA(農協)や地域の地方銀行・信用金庫などは、地域事情を理解しているため比較的柔軟な審査が期待できるケースもあります。
しかし、一般的には融資を受けにくいため、買主はある程度の自己資金を求められます。これが購入のハードルを上げ、結果として売れにくさにつながるのです。
2-3.【手続き・費用の壁】インフラ負担と複雑な手続き
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域なので、行政は水道・電気・ガスなどのインフラ整備を積極的に行いません。
そのため、買主が電気やガス、水道などのインフラ設備の費用を負担しなければならない場合があります。
都市ガスではなくプロパンガスであったり、下水道が未整備で浄化槽の設置が必要だったりすると、費用面だけでなく利便性の観点からも敬遠されることがあります。
新築や建て替えを希望する買主にとっては、開発許可や建築許可を得られるかどうかが不確実であること、そしてその手続きが非常に煩雑であることが大きなリスクとなり、物件の市場価値を下げています。
3. 売却を成功させるための4ステップと事前調査
市街化調整区域の不動産が売れるかどうかは、買主が目的の建物を建てられるかどうかにかかっています。
「行政から許可をもらえるのであれば購入する」という買主が多いため、売主側で事前に調査を行い、物件の可能性を明確にしておくことが交渉をスムーズに進めるカギとなります。
3-1.【STEP1】役所での事前調査を徹底する
まず最初に行うべきは、物件所在地の役所(市役所・町役場など)での調査です。
役所のどこで、何を調べる?
- 担当部署:都市計画課、開発指導課、建築指導課など(自治体により名称は異なる)
- 調査内容:
- 区域指定の状況:都市計画法34条11号・12号などの区域指定(後述)の対象か
- 許可履歴の有無:過去に開発許可や建築許可が下りているか
- 法的制約の確認:建築基準法43条(接道義務)や都市計画法34条各号の適用状況
- 調査方法:物件の地番を伝え、窓口で相談します。多くの場合、「開発相談申出書」や「調査依頼書」といった書類を提出して、正式な見解を求めます。
この調査は専門知識を要するため、売却を依頼する不動産会社に必ず行ってもらうようにしましょう。この段階での調査能力が、その不動産会社の専門性を測る試金石となります。
3-2.【STEP2】物件のポテンシャルを確認する
役所調査と並行して、売却したい物件がどのような条件を持っているかを確認します。
- 自治体の区域指定(開発許可が出やすいエリア)か
2000年の法改正で、自治体が指定した区域内であれば、一定の条件で住宅開発が認められる「区域指定制度」ができました。[●●市 区域指定制度]などで検索し、対象エリアか確認しましょう。 - 指定(線引き)の時期と建物の関係
建物が市街化調整区域に指定される前(線引き前)からある場合、既存の権利が尊重され、一定の条件内であれば建て替えが認められることが多いです。建物の建築年月日(固定資産税納付書で確認)と、自治体の線引き年月日を照合します。【重要】線引き前建物の建て替え条件
「線引き前」の建物だからといって、自由に建て替えられるわけではありません。
一般的に「同規模・同用途」と解釈され、具体的には以下のような条件が課されることが多いです。
- 所有者の変更以外の、建築物の用途変更をしないこと(住宅は住宅として)
- 敷地の拡大などの開発行為をしないこと
- 住宅については既存建築物の延床面積1.5倍までであること
ただし、これらの条件は自治体によって解釈や基準が異なる場合があります。「1.5倍まで」という規定も、全ての自治体で共通ではありません。必ず役所の担当部署で確認しましょう。
- 土地の地目
登記上の地目が「宅地」か、それとも「畑」「山林」かを確認します。特に地目が農地(田・畑)の場合、売却のハードルが非常に高くなります。【要注意】農地を含む物件の売却
地目が農地の場合、農家以外の人に売るには「農地転用許可(農地法第5条)」が必要です。これは農業委員会が厳しく審査し、特に市街化調整区域では「転用の必要性が極めて明確」でなければ許可は下りません。自治体によっては事実上不可能に近いケースもあり、最大の注意が必要です。
- 例外的な「用途地域」の有無
原則として市街化調整区域に用途地域は定められませんが、例外的に指定されている場合があります。これは1970年~1980年代に大規模開発された、いわゆるニュータウンなどに見られるケースです。もし物件が「第一種低層住居専用地域」などの用途地域内にあれば、建築できる建物の種類は制限されるものの、計画的な開発が許可されたエリアであるため、売却のハードルは大きく下がります。
3-3.【STEP3】価格の相場観を把握する
物件のポテンシャルがある程度わかったら、価格の目安を調べます。
価格差の目安を知る
市街化調整区域の物件は、隣接する市街化区域と比べて、条件により30%~50%程度、あるいはそれ以上に価格が低くなるのが一般的です。
例えば、市街化区域の坪単価が30万円の地域でも、調整区域内の土地は坪単価10万~15万円程度になる、といったケースは珍しくありません。
※これはあくまで一例です。価格は土地の個別条件や地域によって大きく変動します。
この価格差を理解した上で、複数の不動産会社に査定を依頼し、現実的な売却価格を見極めることが重要です。
3-4.【STEP4】売却戦略を立てる(誰に売るか)
調査結果と価格の相場観をもとに、どのような買主にアプローチすべきか、具体的な戦略を立てます。
3-4-1. 隣地の所有者
市街化調整区域の物件を売却する際、まず最初に打診すべき最も有力な候補が隣地の所有者です。
隣地所有者にとっては、土地を買い増すことで敷地を一体化でき、資産価値の向上に繋がる可能性があるからです。たとえば、親族を近くに住まわせたい、庭や駐車場を拡張したいといったニーズに応えられます。
ここで交渉がまとまれば、市場で広く買い手を探す手間が省け、スムーズに売却できる可能性が高まります。
3-4-2. 既存の建物を活用したい人(田舎暮らし希望者など)
大規模な建て替えや新築を望まず、既存の建物をそのまま、あるいは小規模なリフォームで利用したいと考えている層も重要なターゲットです。
特に、物件が「線引き前宅地」などで、許可なしに再建築が可能(条件あり)な場合は、静かな環境で暮らしたい田舎暮らし希望者や、セカンドハウスを探している人にとって魅力的に映ります。
このような買主には、建物の状態だけでなく、周辺の自然環境や静けさといった付加価値をアピールすることが有効です。
3-4-3. 専門の不動産買取業者
個人への売却がむずかしい場合、専門の不動産買取業者への売却は非常に現実的な選択肢になります。
なぜなら、買取業者は、個人とは異なる視点で土地の価値を評価するため、一般の住宅としては活用が困難でも、資材置場、駐車場、太陽光発電用地など、事業者向けの活用ノウハウや独自の売却ルートを持っているからです。
売却価格は市場価格よりも低くなる傾向がありますが、「早く現金化したい」「買主探しに時間をかけたくない」「契約不適合責任を負いたくない」といった場合には、大きなメリットがあります。
4.【買主の不安を解消】契約時に盛り込むべき重要特約
市街化調整区域の売買で最も買主が恐れるのは「買ったはいいが、目的の建物が建てられなかった」という事態です。
この不安を解消し、交渉をスムーズに進めるために、契約書に特別な条項を盛り込むことが極めて重要になります。
4-1.停止条件付き契約(白紙解除特約)を活用する
停止条件付き契約とは、万が一、買主が想定していた開発許可や建築許可が得られなかった場合は、この売買契約は無かったことになり、支払った手付金などは全額返還されるという内容の特約です。
これを契約に盛り込むことで、買主は許可申請という不確実なハードルに安心して挑戦できます。
また、売主にとっては、買主が見つかりやすくなるという大きなメリットが発生するため、市街化調整区域の売買では、この特約を付けるのが一般的です。
さらに、この特約の存在を知っているかどうか、そして適切に売主と買主へ提案できるかどうかも、不動産会社の専門性を見極めるポイントになります。
5. 市街化調整区域の売却に本当に強い不動産会社の選び方
これまで見てきたように、市街化調整区域の物件売却は非常に専門的で、不動産会社の力量が成功を大きく左右します。
5-1. 専門知識と実績を持つ会社を選ぶ
次のポイントを確認したうえで、信頼できる不動産会社を見極めましょう。
- 市街化調整区域の取り扱い実績が豊富か
過去の具体的な売却事例や、現在扱っている物件について聞いてみましょう。 - 役所調査や法規制の知識が深いか
「都市計画法34条のどの号が使えそうか」「この土地の接道義務はクリアできるか」といった専門的な質問に、明確に答えられる担当者を選びましょう。 - 地元に密着し、独自の販路を持っているか
地元の開発業者や、隣地所有者へのアプローチなど、独自のネットワークを持つ会社は頼りになります。
5-2. 必ず複数社を比較検討する
市街化調整区域の物件は査定額が不安定なため、1社の査定だけで判断するのは非常に危険です。
必ず複数の不動産会社から査定を取り、提案内容を比較しましょう。
複数社比較が必要な理由
- 適正な売却価格を見極めるため
不動産会社によって査定額が数百万円単位で異なることも珍しくありません。複数社の査定額を比較することで、売却価格の妥当なラインが見えてきます。 - 各社の専門性と対応力を比較できる
査定の根拠や売却戦略を詳しく説明してくれるか、役所調査に積極的かなど、対応を通じて会社の姿勢や能力を判断できます。 - 自分に合った売却戦略を見つけるため
「買取」を強く勧める会社もあれば、「じっくり仲介で高値を目指しましょう」と提案する会社もあります。自分の方針に合った会社を選ぶことができます。
しかし、数ある不動産会社の中から、市街化調整区域の売却が得意な会社を自力で複数探し出すのは大変な労力がかかります。
そのような場合におすすめなのが、「イクラ不動産」です。
「イクラ不動産」では、無料&秘密厳守で、市街化調整区域のような専門性の高い物件の売却実績が豊富な不動産会社を探すことができます。
さらに、不動産の売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持つイクラの専門スタッフにいつでも無料で相談できるので安心です。
6. 今後の見通し:規制緩和の可能性について
最後に、少し未来の話に触れておきましょう。
これまで市街化調整区域の規制は固定的と考えられてきましたが、人口減少や社会構造の変化を背景に、全国の一部の自治体では、区域区分(線引き)そのものを見直したり、廃止したりする動きが出てきています。
また、既存集落の維持や空き家対策のために、これまでよりも柔軟に開発許可を運用する方針を打ち出す自治体も増加傾向です。
もし、将来的に市街化調整区域にある物件を売却する予定があるなら、そのエリアの「都市計画マスタープラン」などを確認し、動向に注目しておくことも有益かもしれません。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 市街化調整区域は建築・開発が厳しく制限されるため、売却には専門知識が不可欠。
- 売却を阻むのは「建築制限」「住宅ローン」「煩雑な手続き」の3つの壁。
- 売却の第一歩は、役所の都市計画課などで「開発許可の見込み」などを調査すること。
- 農地を含む場合は「農地転用許可」のハードルが極めて高いことに注意。
- 市街化区域に比べ3~5割安くなるケースも。現実的な価格設定が重要。
- 買主の不安を拭うため「許可が下りなければ白紙解約」という特約を契約に盛り込むのが一般的。
- 売却成功のカギは、市街化調整区域の売却実績が豊富で、役所調査能力の高い不動産会社を選ぶこと。
- 必ず複数社を比較検討し、査定額と売却戦略の両方から信頼できるパートナーを見つけること。
市街化調整区域の不動産売却は、確かに簡単ではありません。しかし、この記事で解説したように、一つひとつの課題をクリアし、正しい知識で武装すれば、道は必ず開けます。
何よりも重要なのは、売主一人で抱え込まず、専門家である不動産会社の知見を最大限に活用することです。
市街化調整区域にある不動産の売却を成功させたいのであれば、市街化調整区域の不動産売却にくわしい不動産会社へ依頼することが最も重要なポイントになります。
市街化調整区域の売却を依頼できる不動産会社を探したい場合は、ぜひ、「イクラ不動産」を利用してみてください。
無料&秘密厳守で簡単に素早くお家の査定価格がわかるだけでなく、市街化調整区域の売却に強い、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社が選べます。
また、市街化調整区域にある物件の売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので安心して売却を進めることが可能です。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
不動産売却について基本から解説
- 【売れない・売れにくい不動産×解決策のまとめ】家が売れない原因と売るために売主がやるべき対策
- 別荘を売却するには?売れにくい理由と上手に売る方法を解説
- ゴミ屋敷の物件を売却、買取する方法と売却にかかる費用について解説
「売却一年生」TOPに戻る
- 合わせて読みたい
- 埋蔵文化財がある土地に建つ家の売却はどうやるの?ポイントを確認
- 都市計画道路予定地って売却できる?事業決定前なら可能です
- 【お家の売却】送電線下の家は安くなる?売却に影響するポイントを確認
- 店舗住宅って売却できる?売却方法と注意点をわかりやすく解説
- 底地を売却したい!高く売れる方法を見つけよう
- 雑種地とは?地目が雑種地の一戸建てを売却する方法
- 隣地と高低差のある土地を売却するには?売却が難しい理由を解説
- 結露しやすい家は売却できるの?結露が発生する原因と売却方法3選
- 区画整理地だけど売却できる?事業段階ごとの売却の傾向と注意点
- 液状化した土地に建つ家は売却できる?売却方法と注意点をチェック
- 雨漏りした家を売却したい!上手に売却するためのポイントを解説
- ひな壇になっている土地の売却はどうやるの?
- ひび割れのある家を売るには?上手に売るコツを確認
- 旧耐震基準の家でも売れる?不安解消から高値売却のコツまで徹底解説!
- お風呂がない家でも売れる?売却方法を工夫しよう!
- 越境物のある家を売却するには?スムーズに売却する方法を解説
- 湿気の高い家は売却できる?原因と対策を知っておこう
- 連棟住宅の売却はむずかしい?ポイントと注意点をチェックしよう
- 水路に接した家や土地を売却するには占用許可が必要って本当?
- 傾いている家でも売却できる?傾きの調べ方や売却方法を解説
- マンション1階は安いし売れにくい?少しでも高く売却する方法を解説
- 3階建ての家を売却するときは安くなるの?デメリットを知っておこう
- 日当たりが悪い家だけど売却したい!上手に売却するコツを紹介
- 葬儀場近くの家の売却は難しい?価格への影響をチェック
- 【墓地に近い家】売却したいけど安くなるの?ポイントを押さえよう
- 台風被害にあった家の売却で注意すべきことは?3つのポイントを解説
- 団地の売却を成功させよう!高く売るためのポイントを解説
- 平屋を売却したい!平屋ならではのメリットを知っておこう
- ペットを飼っていた家は査定額や売却価格が下がるの?ポイントを解説
- 川沿いにある家は売却するときに売れづらいって本当?
- 浸水想定区域にある家は売却できる?ハザードマップと価格との関係
- 浸水した家は安くなる?できるだけ高く売却する3つの方法
- 借地の家はなぜ安いの?査定方法と高く売却する方法をまとめた
- 再建築不可物件は売却できる?査定相場価格や再建築を可能にする方法を解説